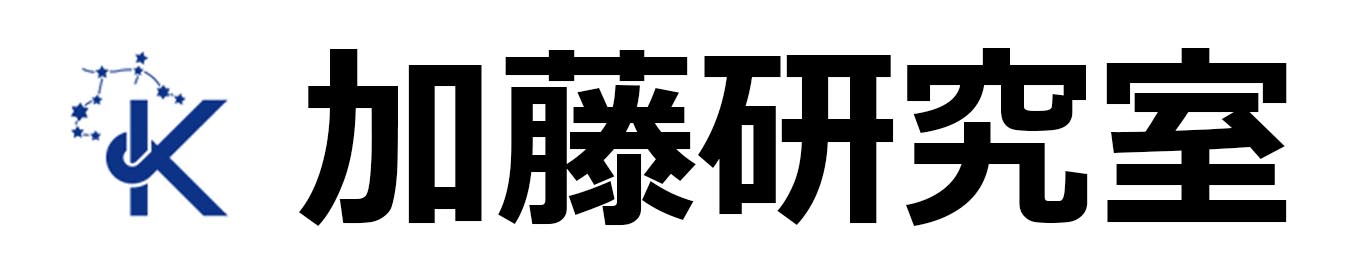メンバー
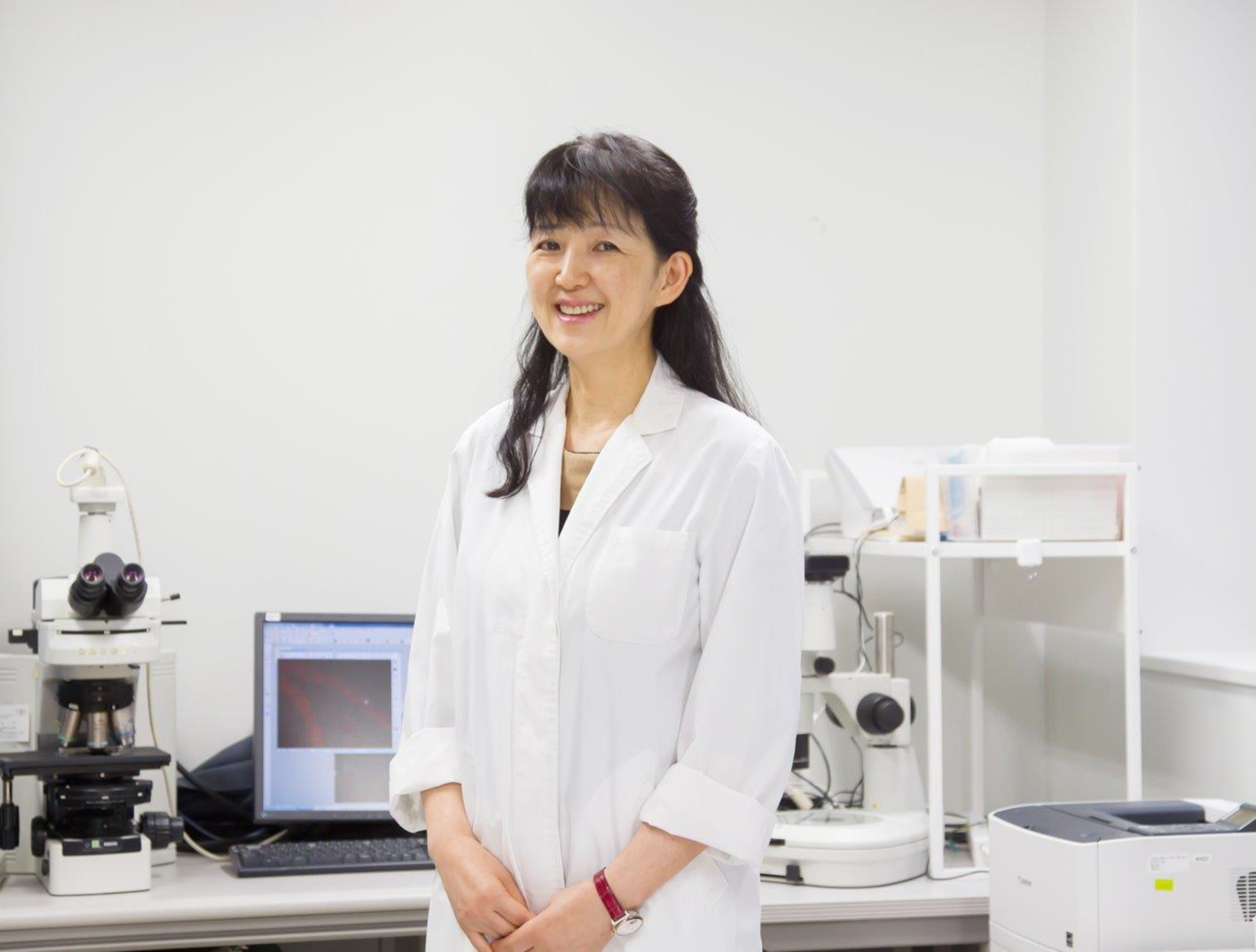
教授 加藤 啓子
私たちは一つのことを究めることによって初めて真理やものごとの本質を体得することができます。究めるということは一つのことに精魂込めて打ち込み、その核心となる何かをつかむことです。一つのことを究めた体験は、他のあらゆることに通じます。私たちと共に神経可塑性の探求の旅に出かけませんか!
kato@cc.kyoto-su.ac.jp
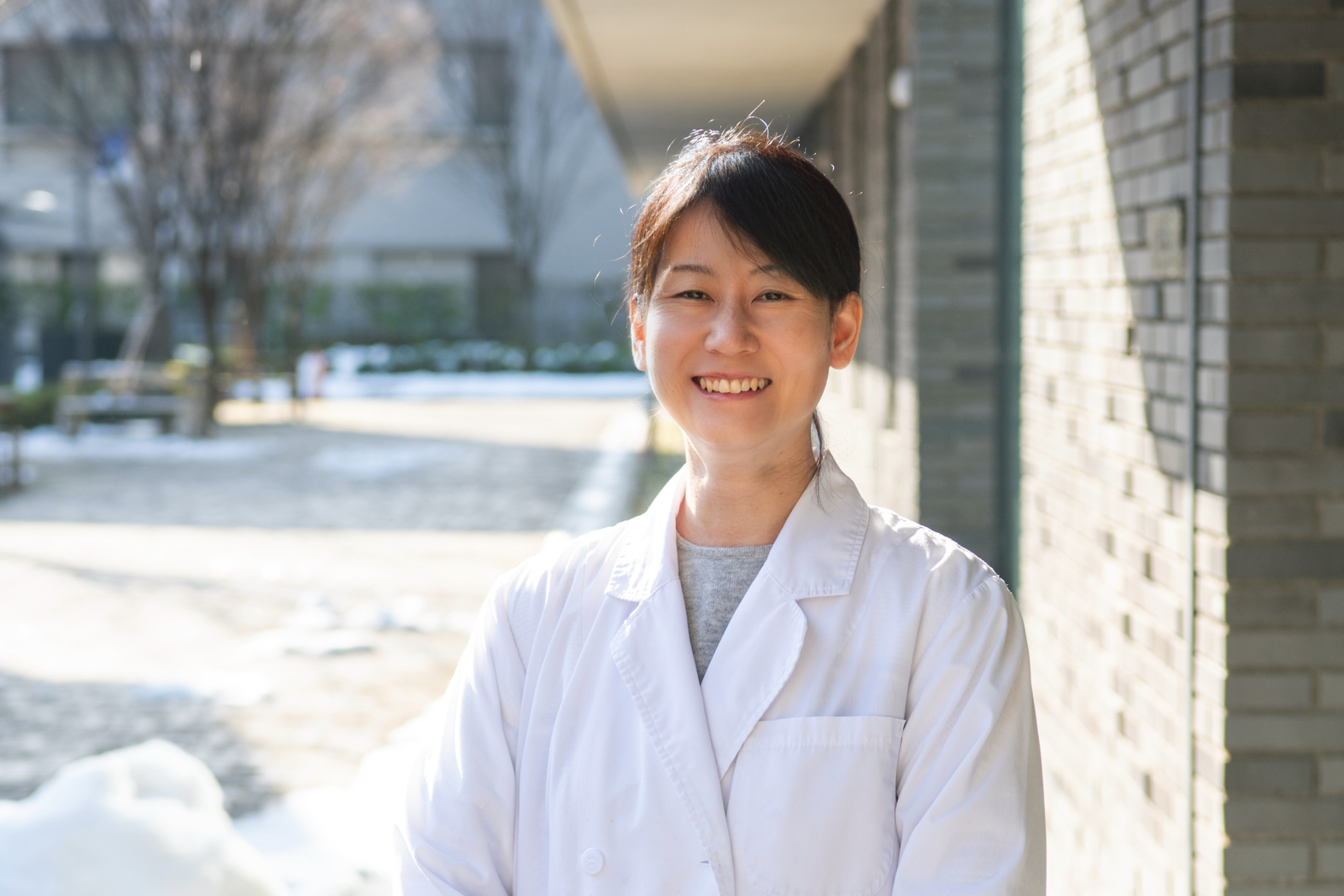
客員研究員 藤田 明子
代謝生物学・生化学を専門としています。アメリカ・テキサス州立大学の生化学教室に留学し、腸上皮における糖鎖研究で経験を積みました。現在は、脳の高次機能と代謝についての研究を学生さんと共に進めています。
a_fujita@cc.kyoto-su.ac.jp
M2 中谷 敢
シアル酸転移酵素St3Gal4を欠損したマウスモデルを用いて、脳と腸の相関性についての研究を行っています。加えて、側頭葉てんかんモデルマウスを対象に、尿や糞便中に含まれる揮発性有機化合物(VOC)を分析し、腸内細菌との関連性を調べています。 趣味:私の趣味は自動車の運転です。特に、山道を走るのが好きで、週末にはよく郊外にドライブに出かけます。

M2 森井 渉羽
うつ不安症モデルマウスの脳の神経の変化について研究しています。このマウスは「ST3Gal4」を持っていません。そこで私は、ST3Gal4の機能が神経回路の形成に与える影響を解明するために、 ST3Gal4を通常に発現する野生型マウスと、ST3Gal4を欠損したうつ不安症マウスの脳のGABA作動性ニューロンの違いを比較しました。その結果、うつ不安症マウスでは、視床前核という脳の領域で特定のGABA作動性ニューロンが消失していることを見つけました。このことから、視床前核で発現するST3Gal4が、GABA作動性ニューロンが働くための環境を作っているという仮説を立て、現在、神経トレーサーという技術を用いて、視床前核におけるGABA作動性ニューロンの可視化を進めています。

M1 八島 智樹
うつ不安モデル動物における視床前核ニューロンの機能について研究しています。
星薬科大の田村先生(電気生理学)に教わりながら、AAVウイルスを使って視床前核や乳頭体に蛍光タンパク質導入しています。マイクロダイアリシスの実験系を立ち上げ、理科研の1分子酵素活性測定法を利用したTNAPの局所的活性化メカニズムに研究も着手しています。毎日新しい発見があり、研究活動の面白さが分かってきました。京都市で教員をされている今年卒業された先輩のように、自分も子供たちに科学の面白さを伝えていきたいです。百億パーセント熱血教師になれるだけん!

M1 山本 裕大
加藤研とは??
-成長の機会を見つける場所-
そして、社会における自分の役割を見出す機会…
長い人生の中で、研究室に所属できる時間はほんの一瞬かもしれません。けれど、その限られた時間は、まるで旅の途中で立ち寄るオアシスのように、個性豊かな仲間たちが集い、互いに刺激し合う特別な場所です。ここでは、未知の知識との出会いや予想もしなかった発見が日常のように起こり、自分自身の新たな一面に何度も出会うことができます。そんな研究室での時間は、単なる「学び」ではなく、人生を彩る大切な「体験」になるはずです。これからその扉を開くあなたを、私たちは心から歓迎します。

B4 今井 陽香
「脳と云う我々に最も身近でありながら未知の多い領域に惹かれてこの研究室を選びました。何か一つ意味あるものを研究室に残して卒業してゆきたいというのが現在の私のヴィジョンです。趣味は読書と映画鑑賞で、好きな映画監督はティムバートンです。」 好きな音楽は:ガブリエルフォーレのシシリエンヌです。

B4 奥村 愛花
神経可塑性に関わるシアル酸転移酵素ST3GAL4の機能に着目し、糖タンパク質のシアル酸修飾による構造制御機構が神経活動に及ぼす影響について、実験動物および培養細胞を用いて研究を行っております。私は、1級の実験動物技術者で、動物実験はもちろんの事、細胞や生化学実験も得意です。

B4 片川 日菜
私たちの研究室ではモデルマウスを用いて、うつや精神疾患に関わる研究に取り組んでいます。その中でも私はフェネチルアミンという物質に着目し、免疫染色によって脳の分布をみることで、正常なマウスと精神疾患を持ったマウスでは脳でどのような違いがあるのかを明らかにしようとしています。

B4 加舎 美穂
私たちの研究室では、「感情のゆらぎ」がどのように脳内で生まれ、心の不調につながっていくのかを、モデル動物を使って探っています。特に、うつや不安といった情動に関わる精神状態と、神経伝達物質の“代謝”とのつながりに注目しています。 例えば、脳内で働く酵素のわずかな変化が、神経の働き方を変え、薬の効き方や気分の変化にも影響を与えることがあるのです。私たちは、そうした「見えない化学の動き」が心にどう影響するのかを、分子レベルで明らかにしようとしています。

B4 野呂 明音
私たちの研究室では、 神経代謝生物学を中心とした研究をおこなっています。この研究室では、神経精神疾患の発症メカニズムなどの解明を目指し、分子生物学、細胞生物学、神経解剖学など多岐に渡る手法を駆使しています。
研究テーマには、てんかんやうつ・不安障害などの疾患モデルマウスを用いた解析が含まれ、疾患の予防や治療法の開発に向けた取り組みが進められています。

B4 増尾 美有
自発運動が代謝、筋力・骨格筋量にどのように影響を与えるかについて行動実験を行っています。老化に従って筋力が衰える疾患であるサルコペニアに自発運動が良い影響を与えるかを調べることを目標としています。

客員研究員 岡卓也
サルコペニアの尿中バイオマーカーの研究をしています。サルコペニアは、筋肉が減って力が弱くなる病気で、「健康寿命を縮める静かな引き金」として世界中で注目されています。腸内細菌と肝臓の代謝機能に着目し、発症メカニズムの謎に迫ると共に、臨床上有用な検査技術を社会実装できるよう加藤研のメンバーと協力して 研究しています。
toka@cc.kyoto-su.ac.jp
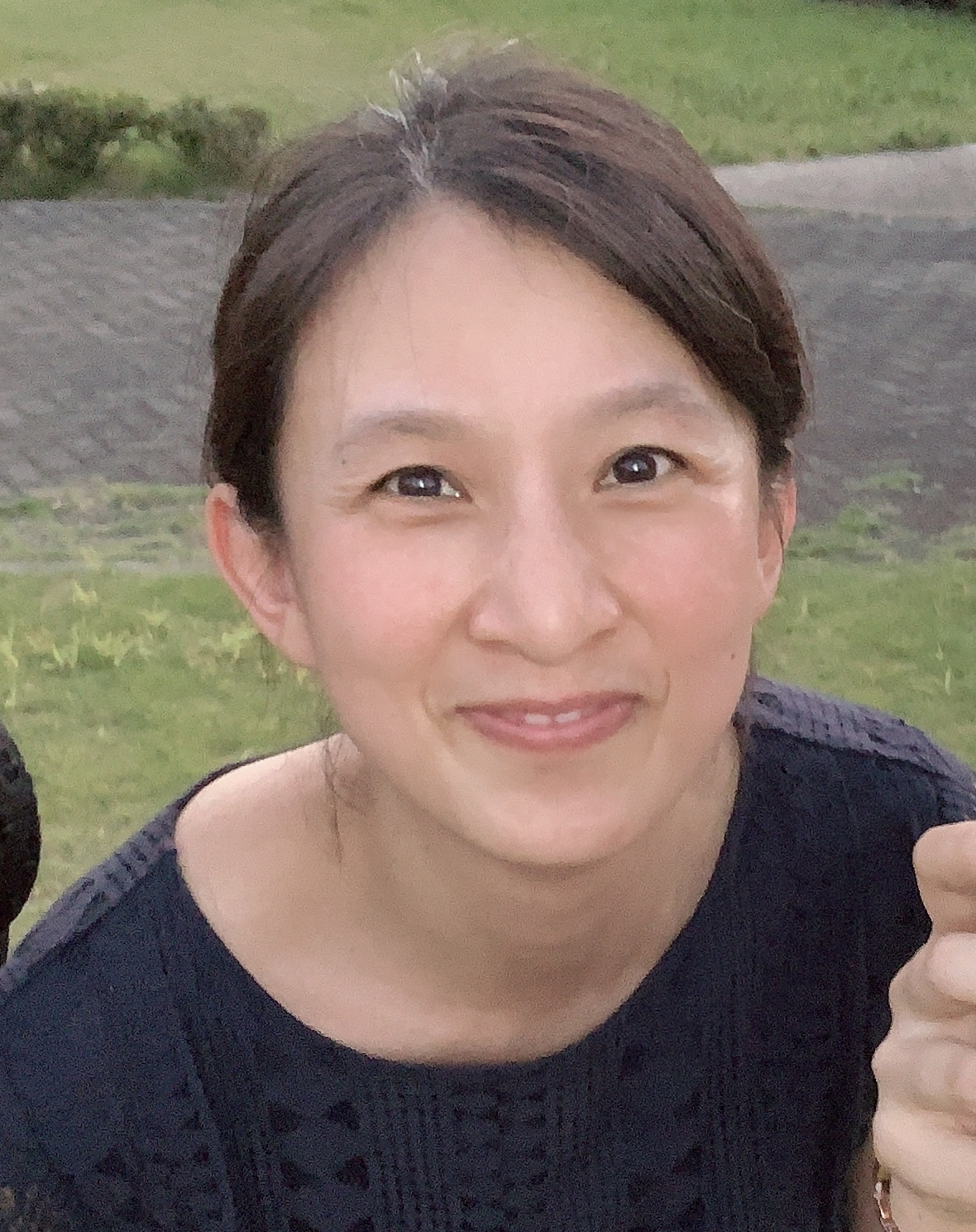
客員研究員 シリポーン タングスツザイ