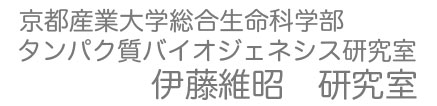【2014. 4. 1】
京都産業大学総合生命科学部・シニアリサーチフェローに就任しました(伊藤)。
【2014. 3. 31】
京都産業大学を退職いたしました(伊藤)。
【2014. 3. 24-25】
2013年度国立遺伝学研究所研究会「単細胞システムの細胞構築・運動・増殖機構の研究」(三島・遺伝研)にて、「MifM研究から見えてきた翻訳伸長アレストの多様性」という演題で口頭発表(招待講演)を行いました(千葉)。
【2014. 3. 18, 20】
4回生の卒論発表会および、伊藤研最終研究セミナーを行いました。その後、送別会を行いました。
【2014. 3. 6】
京産大グローバルサイエンスコースセミナーにおいて、「MifM induces multisite ribosome stalling in monitoring membrane protein biogenesis」という演題でポスター発表を行いました(千葉)。
【2014. 3. 1】
分子遺伝学シンポジウム2014〜新しい生命像を導いた大腸菌遺伝学の系譜〜(京大)において、「翻訳再訪(伊藤)」および、「熱ショック転写因子(シグマ32)の新しい制御回路:SRP-SecY経路によるシグマ32の内膜への移行(由良)」という演題で、それぞれ口頭発表を行いました。
【2014. 2. 18】
東海大学名誉教授の猪子英俊博士にお越しいただき、「ゲノム時代の個人差対応医療におけるHLAの重要性とHALタイピング法の進展」という演題で生命科学セミナーをしていただきました。大変興味深いお話をありがとうございました。
【2014. 2. 7】
M2の斎藤君、中森君の修士論文発表会が行われました。
【2014. 1. 17】
伊藤先生の最終講義「まだまだ奥深いセントラルドグマ」が京産大図書館ホールで開催されました。多数のご参加大変ありがとうございました。 また、準備や進行等を取り仕切って下さいました、佐藤先生、瀬尾先生、事務の方々にも感謝申し上げます。
【2013. 12. 25】
論文"Conformational variation of the translocon enhancing chaperone SecDF."が、Journal of Structural and Functional Genomics誌に掲載されました(伊藤)。筑波大学、奈良先端大学院大学、京大ウイルス研、東大、(株)日本電子との共同研究です。
【2013. 12. 18】
論文 "Heat Shock Transcription Factor σ32 Co-opts the Signal Recognition Particle to Regulate Protein Homeostasis in E. coli." が、PLoS Biology誌に掲載されました(由良・伊藤)。京大秋山研、UCSF Gross研、Walter研との共同研究です。由良先生自らの発見を発展させてまとめ上げた研究で、熱ショック転写因子であるσ32が細胞膜に局在化し、そのことがその活性制御に重要であることを示したものです。
【2013. 12. 16】
千葉大学の相馬亜希子博士をお招きし、生命科学セミナーにて、「逆転および高度分断化 tRNA遺伝子の解析」という演題で講演をしていただきました(世話人・千葉)。セントラルドグマという生物学の中心問題にも、まだまだ多くの謎が残されているようで、大変興味深く感じました。ありがとうございました。
【2013. 12. 5】
博士研究員・茶谷悠平さんの第85回日本遺伝学会年会での発表「大腸菌翻訳途上鎖の網羅的解析」が、BP (Best Papers) 賞として表彰されました。
【2013. 10. 21】
東海大学の堀内嵩博士をお招きし、生命科学セミナー「遺伝子増幅(gene amplification)の話」という演題で、講演をしていただきました。 大変興味深いお話をありがとうございました。
【2013. 9. 30】
奈良先端大学の森浩禎教授をお招きし、生命科学セミナー「細胞内全生理機能ネットワーク解明に向けて」という演題で、講演をしていただきました。壮大な計画をやり遂げる実行力に改めて感銘と刺激を受けました。ありがとうございました。
【2013. 9. 19-21】
日本遺伝学会第85回大会(慶應義塾大・日吉キャンパス)に参加し、「大腸菌翻訳途上鎖の網羅的解析」という演題で、口頭発表をしてきました(茶谷)。
【2013. 9. 7-9】
グラム陽性菌ゲノム機能会議(筑波)にて、 “翻訳アレストを介した枯草菌MifMによる蛋白質膜組込因子YidCの制御”という演題で口頭発表をしてきました(千葉)。世話人の中村幸治先生、中村顕先生には、大変お世話になりました。ありがとうございました。
【2013. 7. 9-12】
Ribosomes Conference 2013 (Napa, USA) にて、それぞれ "Profiling Polypeptidyl-tRNAs to Reveal Real Pictures of Translation Elongation(伊藤)"、"MifM induces multisite ribosome stalling in monitoring membrane protein biogenesis(千葉)"、"ArfA (YhdL) / RF2 and ArfB (yaeJ)-mediated alternative ribosome rescue systems in Escherichia coli(茶谷)" という表題で、ポスター発表をしました。非常にハイレベルな学会で、良い刺激を受けました。また、共通の研究目的をもつ海外の研究者と直接討論することができて大変有意義でした(千葉)。
【2013. 8. 7-9】
第7回細菌学若手コロッセウムにて、 "枯草菌MifMは、ユニークな翻訳アレス トを介して蛋白質膜組込因子の発現量を調節する(千葉)"、"合成途上鎖の解析による翻訳伸長過程の全容解明に向けて(茶谷)" という表題で、口頭発表をしました。広島大学の鹿山さんをはじめ、世話人の方々、学生さんには大変お世話になりました。ありがとうございました。
【2013. 6. 20-21】
第10回21世紀大腸菌研究会(伊豆・修善寺)に参加してきました(伊藤・千葉・由良・茶谷)。特別講演「大腸菌の熱ショック応答:シャペロンによるフィードバック制御の主要な段階は転写因子sigma 32のSRP-SecYに依存する内膜への移行である」(由良)および、口頭発表「枯草菌MifMによるユニークな翻訳アレストと蛋白質膜組込因子の制御」(千葉)、「合成途上鎖の解析による翻訳伸長過程の全容解明に向けて」(茶谷)を行いました。オーガナイザーの学習院大・菱田先生、立教大・関根先生には大変お世話になりました。ありがとうございました。若い世代の方々が新しいサイエンスに果敢にトライしている姿に刺激を受けました(千葉)。
【2013. 6. 2】
Annual Review of Biochemistry誌に総説 "Arrest Peptides: Cis-Acting Modulators of Translation" が掲載されました(伊藤・千葉)。私たちが発見したSecMやMifMをはじめ、翻訳の途上で自らの合成を一時停止させるユニークなポリペプチド鎖が、その性質を利用して様々な細胞機能の調節に貢献していることが分かってきました。今回は、そのような性質を持つ因子(Ribosome Arrest Peptide: RAP)を出来る限り全て網羅し、メカニズム上の共通点と多様な作用様式を、全体像を俯瞰しながらレビューしています。
【2013.5.19-22】
ソウルのKorea Institute for Advanced Studyで行われたBiophysical Society Meeting "Memebrane Protein Fodling"に参加し、"Regulation of membrane protein translocation and integration systems by ribosome stalling"という演題で口頭発表をしました(伊藤)。普段聴けない理論計算シミュレーションの話も多く勉強になりました。
【2013. 4. 12】
4年間にわたり伊藤研を支えてくれた実験補助員・日比野君の送別会を行いました。常にプロ意識を貫いて仕事をしてくれたことにとても感謝しています。
【2013. 3. 28-29】
第2回 Ribosome meetingに参加しました(伊藤、千葉、茶谷)。「枯草菌MifMによるユニークな翻訳アレスト様式を利用した蛋白質膜組込のモニタリング」という表題で口頭発表を行いました(千葉)。活発な質疑応答が印象的な会でした。オーガナイザーの東京農工大・高橋先生には大変お世話になりました。ありがとうございました。
【2013.3.7】
昨年夏にがんばってまとめたAnnual Review of Biochemistryの総説 "ARREST PEPTIDES: CIS-ACTING MODULATORS OF TRANSLATION" の細かい調整と最終的な校正が終わりました(伊藤、千葉)。今年の初夏に刊行される予定です。この新たな分野の現状をまとめる機会を提供して下さったAnnual Review誌の編集者に感謝します。
【2013. 2. 28】
吉田研と合同で、応用特別研究の研究発表会を行いました。その後、打ち上げも行いました。今学期の4年生は最後に向けてだんだん乗りが出てきて、がんばりました。加々爪さん、珎道君、馬屋原君の前途をお祝いします。
【2013. 1. 21】
ストックホルム大学のGunnar von Heijne博士をお招きし、バイオフォーラムにて、「Translocon-mediated assembly of membrane proteins: Energies and forces」という表題でご講演をしていただきました。博士の一連の研究は、一見地味に見える研究を徹底すると凄い成果となることを実感させるものです。また、個別にディスカッションもしていただきました。大変ありがとうございました。
【2013. 1.10, 11, 17, 18】
生命システム実習を担当しました。今年は予備実験に念を入れたので、概ねどの班でも電気泳動がうまくいき、ストレス誘導タンパク質が観察できた点が昨年より進歩しました。
【2012. 12. 17】
甲南大学の杉山直己先生をお招きし、バイオフォーラムで、「脱二重らせんの発想から生まれる新しい機能性核酸の発見」という演題でご講演をしていただき、また、ディスカッションをしていただきました。刺激に満ちたお話をいろいろと聞かせていただきました。大変ありがとうございました。
【2012.10.24】
秋田市で行われた、『独創的発想に富む科学者育成プログラム「出る杭を伸ばすヘリックスプロジェクト」採択事業 七人の侍による記念講演会』にて「翻訳のスピード制御について」という講演を行いました(伊藤)。
【2012. 9. 29-30】
吉田研と一緒に松の浦セミナーハウスにて合宿をしました。吉田研の皆様、ご一緒させていただきましてありがとうございました。
【2012. 8. 30-9. 1】
グラム陽性菌ゲノム機能会議(焼津)に参加し、「枯草菌膜組込モニターMifMのユニークな翻訳アレスト機構」という演題で口頭発表をさせていただきました(千葉)。
【2012. 8. 22】
先日アクセプトされた茶谷博士の論文 "ArfA recruits RF2 to rescue stalled ribosomes by peptidyl-tRNA hydrolysis in Escherichia coli" がon line上で閲覧可能となり、さらに、Molecular Microbiology誌のMicro Commentaryでフィーチャーされました(茶谷、伊藤)。論文掲載サイトはこちら。紹介記事はこちら。
【2012. 8. 22】
MifMのマルチサイトアレスト論文の日本語紹介記事が新着論文レビューのサイトにて掲載されました(千葉、伊藤)。記事はこちら。
【2012. 8. 8-9】
京都産業大学総合生命科学部の研究交流会に参加し、口頭発表(伊藤)およびポスター発表(千葉)を行いました。
【2012. 8. 2】
先日アクセプトされたMifMのマルチサイトアレスト論文が、Molelular Cell誌のオンライン版として閲覧可能となり(掲載ページはこちら)、また、京産大のHPでも紹介していただきました(日本語紹介記事はこちら)(千葉、伊藤)。
【2012. 7. 26】
Molecular Microbiology誌に論文 "ArfA recruits RF2 to rescue stalled ribosomes by peptidyl-tRNA hydrolysis in Escherichia coli" がアクセプトされました(茶谷、伊藤)。岡山大学・阿保達彦先生の元で、博士研究員・茶谷氏が主体となって行った仕事です。
【2012. 7. 26】
ドイツ、ハイデルベルグ大学にて 「Studying cellular nascent polypeptides」という演題でセミナー講演を行いました(伊藤)
【2012. 7. 23-25】
SFB594: 3rd International Symposium "Molecular Machines in Protein Folding and Translocation" (ドイツ、ミュンヘン)にて、「Analysis of cellular polypeptidyl-tRNAs」という演題で口頭発表しました(伊藤)。
【2012. 7. 15-20】
GRC (Gordon Research Conference) "Microbial Stress Response" (米国マサチューセッツ州、マウントホリオーク大学) にて、 「SRP-dependent targeting of sigma 32 to the membrane is required for feedback control of heat shock response in E. coli」という演題で, ポスター発表をしました(由良)。会議の主要テーマが、個々の細胞のストレスから、細胞間のストレス、宿主細胞との間のストレス応答へと移行しつつある現状が、特に印象的でした。
【2012. 6. 21-22】
第9回21世紀大腸菌研究会(長浜)に3名が参加し、それぞれ、「翻訳アレストの解除に関わるSecM部位の同定(中森)」、「大腸菌で見出された新規リボソーム解放機構とその生理学的意義(茶谷)」、「Nascentome:合成途上鎖の解析(伊藤)」という演題で口頭発表をしました。会を運営されました京都大学 秋山芳展先生、森博幸先生、ならびに秋山研の皆様に厚くお礼申し上げます。「今回、初めての口頭発表で大変緊張しましたが、多くの方々に研究の内容を知っていただけたこと、また多くのコメントをいただけた事に感謝しています。懇談会では多くの同年代の院生とも交流する事ができ、よい刺激となりました(中森)。」
「会にて交流、ご意見いただきました皆様、楽しい一時をありがとうございました(茶谷)。」
「大腸菌などのモデル原核生物の研究に学問の基礎を支える役割を見いだし、研究のおもしろさを分かち合っている若い研究者が健在であることに意を強くし、この様な分野が存続できる社会が続くことを改めて願いました(伊藤)。」
【2012. 6. 20-22】
第12回蛋白質科学会年会(名古屋)にて、「合成途上鎖の働きと運命」という演題で口頭発表をしました(千葉)。聴きに来て下さった方々、また、 シンポジウムの企画にご尽力下さり、発表の機会をくださいました世話人の稲葉謙次さん、中戸川仁さんに心より感謝申し上げます。ほかの演者の方々との懇親会も楽しかったです。
【2012. 6. 20】
Molecular Cell誌に論文 "Multi-Site Ribosomal Stalling: A Unique Mode of Regulatory Nascent Chain Action Revealed for MifM" がアクセプトされました(千葉、伊藤)。京産大に来てから立ち上げたin vitroの系とそれを利用した解析が、理想的な形で実を結びました。この論文で重要な役割を果たした実験技術に関して有用なアドバイスをくださり、さらに、その遂行に必要な泳動装置その他もろもろを貸して下さいました京産大・嶋本研の中山さんには本当にお世話になりました。
【2012. 5. 29-31】
CECAM (Centre Européen de Calcul Atomique et Moléculaire) Workshop "Ribosome-associated protein folding: Translation, auxiliary factors, and translocation" (スイス、ローザンヌ)にて、「Analysis of nascentome, cellular polypeptidyl-tRNAs」という演題で口頭発表をしました(伊藤)。これは翻訳と共役した(翻訳途上での)タンパク質フォールディングの諸問題に焦点をあてた、おそらく最初の会議かと思われます。レマン湖越しにアルプスを眺望するキャンパスで密度の高い討論が行われました。細胞における合成途上鎖を検出するアプローチについて活発な議論をいただき、 新たな知人も得ることができ、参加してよかったと思います。
【2012. 4. 17】
吉田研と合同で上賀茂神社でお花見をしました。
【2012. 4. 1】
茶谷悠平博士が学振特別研究員(PD)として、当研究室に加わりました。
【2012. 3. 17】
京都産業大学新聞に当研究室の研究を紹介する記事が掲載されました。
【2012. 3. 15-16】
第一回Ribosome meeting(広島)にて、口頭発表「翻訳途上鎖MifMによるタンパク質膜組込のモニタリング(千葉)」、「Nascentome:合成途上鎖の解析(伊藤)」をさせていただきました。世話人の水田先生および水田研のメンバーの皆様の心のこもった運営に心より感謝申し上げます。
【2012. 3. 8】
奈良先端科学技術大学から、柳谷耕太博士、門倉広博士をお招きし、研究討論をしていただきました。また、生命科学セミナーにおいて、「小胞体膜上で起こるスプライシングの巧妙な仕組み(柳谷耕太博士)」および「哺乳動物細胞小胞体内におけるジスルフィド結合形成を解析する為の新規アッ セイ系の作製(門倉広博士)」という演題で講演をしていただきました。
【2012. 3. 5】
岡山大学から阿保達彦先生をお招きし、研究討論をしていただきました。また、生命科学セミナーにおいて「大腸菌ArfA, ArfBによる終止コドン非依存的翻訳終結」という演題で講演をしていただきました。
【2012. 3. 2】
4回生の応用特別研究の最終発表会を行いました。その後、送別会を行いました。
【2012. 2. 29】
九州大学グローバルCOEプログラム理医連携特別講演会にて、「合成途上鎖のバイオロジー」という口頭発表をしました(伊藤)
【2012. 2. 22】
生命科学セミナーにおいて由良隆先生に「大腸菌熱ショック応答の制御機構:細胞が蛋白質の恒常性維持(品質管理)に関わる基本ストラテジー 」という演題で講演をしていただきました。
【2012. 1. 20】
京都新聞にnascentome論文の紹介記事が掲載されました(伊藤)。
【2012. 1. 12-13, 19-20】
当研究室担当の初めての学生実習として、大腸菌ストレス応答とバクテリオファージ誘発の実験を2年生にしてもらいました。電気泳動のパターンがきれいに出なかった以外は大過なく終わりましたが、学生さんによく理解してもらうための工夫の必要性も浮かび上がりました。
【2011. 12. 20-22】
第37回生体エネルギー研究会において、「翻訳途上鎖のダイナミズムによる翻訳伸長の制御とそれを利用した蛋白質局在化モニタリング機構」という演題で口頭発表を行いました(千葉)。
【2011. 12. 19】
ドイツ・ミュンヘン大学からRoland Beckmann博士とDaniel Wilson博士をお招きし、研究討論をしていただきました。また、生命科学セミナーにおいて「Cryo-EM analysis of co-translational events(Roland Beckmann博士)」および「Man against Microbe: Antibiotic inhibition of ribosome function(Daniel Wilson博士)」という演題で講演をしていただきました。
【2011. 12. 13-16】
第34回日本分子生物学会年会〈横浜)において、シンポジウム「Regulatory systems mediated by programmed ribosomal stalling 」を企画し、北海道大学 内藤哲先生とともにオーガナイザーを務めました(伊藤)。同シンポジウムにおいて、口頭発表「In vitro study of translation arrest of MifM, a regulatory nascent chain that monitors membrane protein biogenesis in Bacillus subtilis 」を行いました(千葉)。このシンポジウムは、翻訳伸長アレスト現象による細胞機能制御システムについて、細菌、植物、哺乳動物の研究を鳥瞰するものとなりました。お越しいただいた方々と講演をしてくださった内外の先生に心より感謝いたします。
【2011. 12. 12】
米国イリノイ大学からAlexander Mankin博士をお招きし、研究討論をしていただきました。また、生命科学セミナーにおいて「Encounters of the nascent peptide and macrolide antibiotics in the exit tunnel of the ribosome」という演題で講演をしていただきました。
【2011. 12. 5】
「ナッセントーム」の論文がPLoS ONE に掲載されました(伊藤、千葉、中森)。
【論文情報】
Ito K , Chadani Y , Nakamori K , Chiba S , Akiyama Y and Abo, Y. "Nascentome Analysis Uncovers Futile Protein Synthesis in Escherichia coli"(ナッセントーム解析が明らかにした大腸菌の空回りタンパク質合成)
これは、伊藤が自ら実験したデータを発表する久しぶりの論文です。細胞内におけるタンパク質の合成途上鎖を、完成したタンパク質と区別して検出する方法を世界で初めて開発しました。そして、合成途上鎖の全体像を“ナッセントーム(nascentome)”と呼ぶことを提案しました。さらに、岡山大学の阿保達彦博士と茶谷悠平さんのリボソーム救援機構の研究と結びつけ、タンパク質合成の過程が厳密な品質管理をうけている様子を明らかにしました。
詳しい内容はこちらをご覧下さい。
【2011. 11. 21-23】
特定領域研究「タンパク質の社会」の班会議(別府)に参加し、口頭(伊藤)およびポスター(由良、千葉)にて研究報告をしてきました。
【2011. 10. 26】
吉田研、伊藤研合同の3年生歓迎会が行われました。今年は、馬屋原 聡、加々爪 尚香、珎道 啓志の「立派な名前の3名」が私達の仲間に加わりました。
【2011. 9. 26 - 30】
中国蘇州で行われた、2011 Cold Spring Harbor Asia Conference "Protein Homeostasis in Health and Disease" に出席し口頭発表 "Vsualization of cellular polypeptidyl-tRNAs uncovers futile protein synthesis in E. coli" (伊藤)、ポスター発表 "Modularity and species-specificity of translation arrest motifs in translocation monitor proteins" (千葉)を行いました。永田研、吉田研の人たちと共に京産大からの出席者が多い会議となりました。
【2011. 9. 7】
国際微生物学会議(International Union of Microbiological Societies 2011 Congress、札幌コンベンションセンター) に出席し,シンポジウム「Bacterial Protein Transport 」において講演 「Structure, function and regulation of bacterial Sec machinery」を行いました(伊藤)。
【2011. 8. 25 - 26】
グラム陽性菌ゲノム機能会議(福山)にて、「タンパク質膜組込をモニターする枯草菌翻訳アレスト因子MifMのin vitro解析」という表題で口頭発表をさせていただきました(千葉)。
【2011. 8. 2】
Proc. Natl. Acad. Sci. USA誌に論文 "Post-liberation cleavage of signal peptides is catalyzed by the site-2 protease (S2P) in bacteria."が受理され、電子版に掲載されました(伊藤、千葉)。京大ウイルス研・秋山芳展研究室に在籍していたときにお手伝いさせていただいた仕事です。
分泌タンパク質は細胞の外に運ばれる「荷札」となるシグナル配列を持って生まれますが、シグナル配列は膜を通過すると、荷札のようにタンパク質本体から切り離されます。今回、バクテリアにおいて、本体から切り離されたシグナルペプチドをさらに切断して処理する酵素が同定されました。
【2011. 7. 23】
京都産業大学新聞の取材を受けました。
【2011. 7. 8-10】
William Wickner教授記念集会(Dartmouth Medical School、米国ニューハ ンプシャー州)に参加して研究発表し、交流に参加しました(伊藤)。 Wickner博士は伊藤の最初の留学先の先生です。
【2011. 6. 21】
米国Brigham Young大学からAllen Buskirk博士を招き、熱心な研究討論をしていただきました。生命科学セミナーとして講演「Identification of peptide sequences that inhibit their own translation」をしていただきました。大腸菌遺伝学を巧みに利用して、リボソームが翻訳を苦手とするアミノ酸配列を新たに創り出すという研究で、翻訳やゲノム配列のあり方などに示唆深いお話でした。セミナーを聞きに来て下さった方々、また、セミナー後もつきあって下さった方々、 ありがとうございました。
【2011. 5. 11】
Nature誌にタンパク質の分泌を助ける因子SecDFの構造と機能に関する論文が電子版として公表されました(伊藤)。
タイトル:Structure and function of a membrane component SecDF that enhances protein export(蛋白質の膜透過を促進する膜蛋白質SecDFの構造と 機能)
著者:塚崎智也*、森博幸*、越前友香、石谷隆一郎、深井周也、田中剛史、Perederina Anna、 Vassylyev Dmitry G.、河野俊之、Maturana Andrés D.、 伊藤維昭**、濡木理**(*同等貢献、**責任著者)
この仕事は伊藤が京都大学に在籍していた頃、当時の大学院生(現東大助教)塚崎智也さんと助手(現准教授)森博幸さんが開始し、東京大学の濡木理教授その他の共同研究者とともに7年がかりで取り組み、やっと実を結んだものです。忍耐強く最後までやり遂げたツッキーさん、生理機能の追求で支えリードした森さん、構造解析と生物物理学測定をオーガナイズして率いた濡木先生に心から御礼申し上げます。この膜蛋白質はSecYトランスロコンと共同でタンパク質の膜を越えた輸送を助けています。今回の構造からプロトン駆動力を利用した構造変化がその働きに重要であることが示唆されました。
【2011. 4. 29-5. 1】
Jon Beckwith教授記念集会(Harvard Medical School)にて基調講演 "Controlling epigenetic connectivity in proteins" および研究発表 "Visualizing a dynamic nascentome, polypeptidyl-tRNAs of the cell"を行いました(伊藤)。Beckwith先生は、転写開始部位 promoter の概念(命名も?)を最初に提唱した人です。このような、Jacob & Monodのオペロン説を発展させた古典的な仕事の後で、タンパク質分泌機構、膜蛋白質の配向決定、ジスルフィド結合形成機構・レドックスバイオロジー、細胞分裂などの重要な細胞の仕組みを寒天培地と大腸菌コロニー 観察だけで(?)解き明かしてしまうという「フォワードジェネティックス」 の名手です。政治活動については http://en.wikipedia.org/wiki/Jon_Beckwith 参照。今回関係者が集まって、 Jonの軌跡を振り返り、交流を深めました。基調講演は、Susan Gottesman, Jeffrey Miller, Tom Silhavy, Tom Rapoport, Richard Lewontinと言ったそうそうたる演者の一部で緊張もしましたが、何とかJonさんに喜んでもらえました。練習に立ち会っていただいた由良先生、千葉さん、中森君ありがとうございました。
【2011. 4. 12】
先日PNAS誌に受理された論文"Recruitment of a species-specific translational arrest module to monitor different cellular processes" が「From the cover」として表紙にハイライトされ、コメント記事"Picky nascent peptides do not talk to foreign ribosomes"で紹介されました(千葉・伊藤)。
【2011. 4. 12】
新しい4年生の応用特別研究が始動しました。既に存在感一杯の中森健太君に加えて、斉藤隆康君、崎山雄介君、三好恭子さんが15323実験室の仲間に加わりました。よろしくお願いします。
【2011. 4. 1】
今年度は由良隆先生(京都大学名誉教授)が「客員研究員」として研究室に来られることになりました。 由良先生は1950年代に米国の分子生物学の誕生の現場で学位を取られた、日本の分子遺伝学の元祖のような先生です。分子シャペロン研究の元祖とも言えるかも知れません。というのは、大腸菌で熱ショック応答を発見され、そのメカニズム追求を続けて来られたからです。HSP研究所所長を退職されてから、アメリカと日本を往復しつつ数年間、そして京都に戻って研究を続けておられます。実際に実験をされる予定です。由良先生の隣で実験できるなんて、若い人にとって得難い経験ですね。
【2011. 3. 24】
マックスプランク植物育種研究所の中村友揮博士が訪問。「高等植物における膜脂質の多様な機能」という演題でセミナーをして下さいました。中村さん、興味深いご講演ありがとうございました。また、セミナーに参加して活発に討論して下さった皆様にも感謝申し上げます。
【2011. 3. 19】
4回生の卒業式が行われました。みなさんこれからもがんばって下さい。いつでも遊びに来いよ〜。
【2011. 3. 10】
京都産業大学総合生命科学部開設記念シンポジウムにて講演「タンパク質誕生の初期における出来事」を行いました(伊藤)。
【2011. 3. 1】
4回生の研究最終報告会を行いました。見に来て下さった吉田研の方々に感謝申し上げます。その後、4回生の追いコン。盛り上がりましたね〜。卒業生の将来が充実したものになりますよう、スタッフ・後輩一同、心より応援しています。
【2011. 2. 4】
Science誌に解説記事(Perspective) "A Translational Pause to Localize" が掲載されました(伊藤)。これは、合成途上鎖による翻訳伸長停止が高等生物における重要な生体反応(小胞体ストレス応答)に重要な役割を果たしているとの奈良先端科学技術大学院・河野研究室の論文("Translational Pausing Ensures Membrane Targeting and Cytoplasmic Splicing of XBP1u mRNA")を紹介し、この問題の周辺をDavid Ron博士と共に解説したものです。
【2011. 2. 3】
Proc. Natl. Acad. Sci. USA誌に論文 "Recruitment of a species-specific translational arrest module to monitor different cellular processes" が受理されました(千葉・伊藤)。この論文では、翻訳アレストを起こす配列が生物種によって多様化しうること、また、翻訳アレストモチーフが独立のモジュールとして働くことで、共通の分子基盤を利用した多様な「細胞内イベントモニター機構」を生み出しうることなどを報告しています。Pogliano研究室(UCSD)、上田研究室(東大)、秋山研究室(京大)のご協力を得て行われました。心より感謝申し上げます。
【2011. 2. 3】
今年は雪が多いですね。"Photos"のページに雪の日の京産大の風景写真を追加しました。
【2011. 1. 27】
奈良先端科学技術大学院大学バイオサイエンス研究科にてGCOEセミナー講演「Functional significance of nascent polypeptidyl-tRNAs」と研究討論を行いました(伊藤)。
【2010. 12. 15】
Ada Yonath博士が多忙なスケジュールの合間を縫って研究室を緊急来訪し、活発な研究討論をしてくださいました。ノーベル賞受賞研究者に私たちの研究をじっくりと聞いていただき意見やアイディアを交換するという大変貴重な機会となりました。また、特別バイオフォーラムにて “The voyage of nascent proteins through the ribosome” という演題で講演をしていただきました。当研究室で扱っているSecMやMifMなどについても言及しながら、リボソームトンネルのダイナミズムについて、力強く語ってくださいました。(急なバイオフォーラム開催にご尽力下さいました総合生命科学部の瀬尾先生、河邊先生、事務の方々、有り難うございました。講演を活発に盛り上げて下さいましたオーディエンスの方々にも感謝申し上げます。)
【2010. 11. 30】
4年生(+3年生有志)の研究中間報告会を開催しました。
【2011.11.26】
京都産業大学発行のサイエンス&テクノロジー誌に当研究室の研究内容が紹介されました(PDF)。
【2010.11. 24】
Proc. Natl. Acad. Sci. USA誌に論文 "Holin triggering in real time" (米国Kit Pogliano研留学中に行ったRy Young研との共同研究)が受理されました(千葉)。Young研の美しいファージ研究と、Pogliano研得意の顕微鏡技術が融合したハッピーなコラボレーションに参加させていただく幸運に恵まれました。
【2010. 11. 16-18】
特定領域・タンパク質分解の班会議に参加し、研究の進展状況を報告してきました(千葉)。久しぶりの札幌で相変わらず美味なお寿司を堪能してきました。
【2010. 9. 13-16】
International Symposium on Protein Community(奈良)にてイブニングトーク(特別講演)"From SecY to Nascent Chain Biology" をしました(伊藤)
【2010. 9. 2-3】
グラム陽性菌ゲノム会議(南木曽)にて「枯草菌翻訳アレスト因子mifMのin vitro翻訳系による解析」という演題で口頭発表をさせていただきました(千葉)。多くの方からの質問、コメントに心から感謝申し上げます。
【2010. 8. 16】
Tom Rapoport博士が研究室を来訪し熱心に研究討論をしてくださいました。永田研(京産大)、秋山研(京大)からも数人の院生・研究員が討論に参加してくれました。また、"Mechanisms of protein transport across membranes"という演題でセミナー講演をしていただきました。大学夏期休業中にもかかわらず、学内外から多数ご参加下さいまして有り難うございました。
【2010.7. 25-】
FASEB Summer Research Conference "Protein Folding in the Cell" (Vermont, USA)にて講演 "Visualizing dynamic "nascentome" of the cell" をしました(伊藤)。
【2010. 2. 26】
BBRC誌にレビュー"Divergent stalling sequences sense and control cellular physiology" が掲載されました(伊藤、千葉)。リボソームのトンネルと相互作用することで翻訳を停止させる「アレスト因子」の多様性と普遍性について最近の知見を分析・総括しています。
【2010. 4. 1 】■伊藤研始動■
2007年3月に伊藤教授の京大退職以来、3年の充電期間(?)を経て、千葉助教と共に京都産業大学総合生命科学部に新たに研究室を構えることが出来ました。