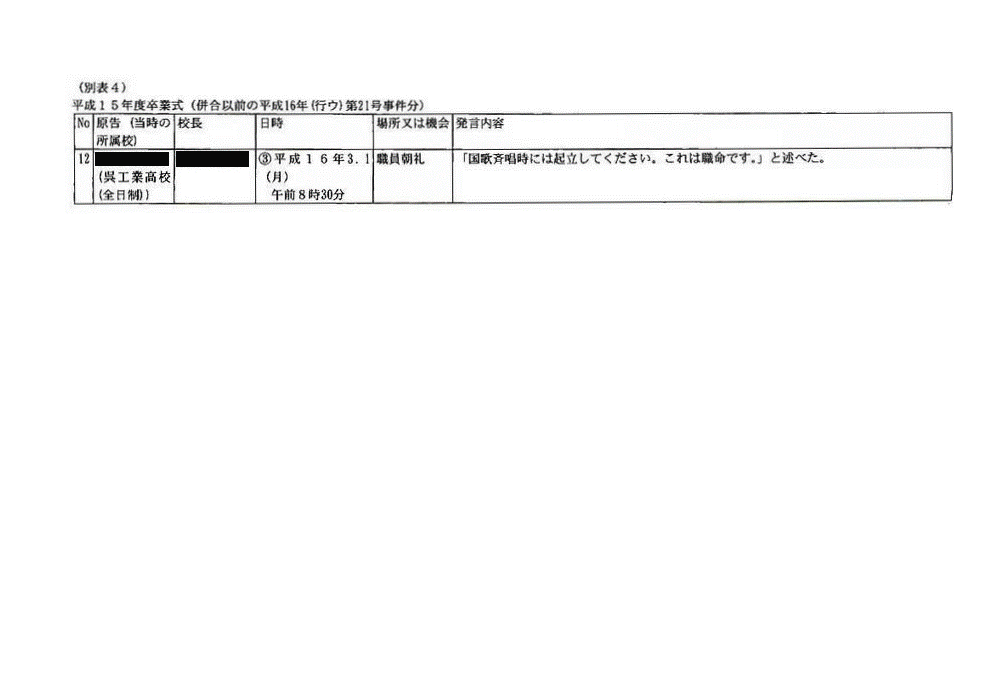戒告処分取消請求事件
広島地方裁判所 平成16年(行ウ)第21号、平成16年(行ウ)第36号
平成21年2月26日 民事第2部 判決
口頭弁論終結日 平成20年8月21日
当事者の表示は別紙当事者目録記載のとおり
■ 主 文
■ 事 実 及び 理 由
1 原告らの請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告らの負担とする。
1(21号事件)
被告が別紙当事者目録記載の番号12の原告に対し平成16年3月30日付けでした戒告処分を取り消す。
2(36号事件)
被告が別紙当事者目録記載の番号1ないし30の原告らに対し平成13年5月11日付けで、同31ないし38の原告らに対し平成14年3月28日付けで、同39ないし40、亡P1及び同45の原告らに対し平成14年5月10日付けでそれぞれした戒告処分をいずれも取り消す。
別表1ないし4原告欄記載の広島県立学校に勤務する原告らが校長から卒業式又は入学式における国歌斉唱の際に起立するように命じる職務命令を受けたにもかかわらず、これに違反して卒業式又は入学式における国歌斉唱の際に起立しなかったとして、いずれも被告から戒告処分(以下「本件各処分」という)をされ、その取消しを求める事案である。
(1) 国旗及び国歌に関する法律
ア 1条1項
国旗は、日章旗とする。
イ 2条1項
国歌は、君が代とする。
(2) 平成18年12月22日法律第120号による改正前の教育基本法(以下「教育基本法」という)10条
ア 1項
教育は、不当な支配に服することなく、国民全体に対し直接に責任を負って行われるべきものである。
イ 2項
教育行政は、この自覚のもとに、教育の目的を遂行するに必要な諸条件の整備確立を目標として行われなければならない。
(3) 平成19年6月27日法律第96号による改正前の学校教育法(以下「学校教育法」という)
ア 小学校に関する規定
(28条3項)
校長は、校務をつかさどり、所属職員を監督する。
イ 高等学校に関する規定
(ア) 43条
高等学校の学科及び教科に関する事項は、前2条の規定に従い、文部科学大臣が、これを定める。
(イ) 50条
a 1項
高等学校には、校長、教頭、教諭及び事務職員を置かなければならない。
b 2項
高等学校には、前項のほか、養護教諭、養護助教諭、実習助手、技術職員その他必要な職員を置くことができる。
(ウ) 51条前段
・・第28条3項・・・の規定は、高等学校に、これを準用する。
ウ 盲学校等に関する規定
(ア) 73条
盲学校、聾(ろう)学校及び養護学校の小学部及び中学部の教科、高等部の学科及び教科又は幼稚部の保育内容は、小学校、中学校、高等学校又は幼稚園に準じて、文部科学大臣が、これを定める。
(イ) 76条
・・・第28条(・・・第51条・・・において準用する場合を含む。)、・・・・第50条・・・の規定は、盲学校、聾(ろう)学校及び養護学校に・・・これを準用する。
(4) 平成19年12月25日文部科学省令第40号による改正前の学校教育法施行規則57条の2
高等学校の教育課程については、この章に定めるもののほか、教育課程の基準として文部科学大臣が別に公示する高等学校学習指導要領によるものとする。
(5) 同規則73条の10
盲学校、聾(ろう)学校及び養護学校の教育課程については、この章に定めるもののほか、教育課程の基準として文部科学大臣が別に公示する盲学校、聾(ろう)学校及び養護学校幼稚部教育要領、盲学校、聾(ろう)学校及び養護学校小学部・中学部学習指導要領及び盲学校、聾(ろう)学校及び養護学校高等部学習指導要領によるものとする。
(6) 学習指導要領
ア 高等学校学習指導要領(平成11年文部省告示第58号)第4章(特別活動)
(ア) 第2のC
学校行事においては、全校若しくは学年又はそれらに準ずる集団を単位として、学校生活に秩序と変化を与え、集団への所属感を深め、学校生活の充実と発展に資する体験的な活動を行うこと。
((1) 儀式的行事)
学校生活に有意義な変化や折り目を付け、厳粛で清新な気分を味わい、新しい生活の展開への動機付けとなるような活動を行うこと。
(イ) 第3の3(以下「国旗国歌条項」という。平成元年文部省告示第26号では第3章第3の3)
入学式や卒業式などにおいては、その意義を踏まえ、国旗を掲揚するとともに、国歌を斉唱するよう指導するものとする。
イ 盲学校、聾(ろう)学校及び養護学校高等部学習指導要領(平成11年文部省告示第62号)第4章(特別活動)
特別活動の目標,内容及び指導計画の作成と内容の取扱いについては,高等学校学習指導要領第4章に示すものに準ずる。
(7) 地方公務員法
ア 29条(懲戒)
(1項)
職員が次の各号の一に該当する場合においては、これに対し懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる。
(ア) 1号
この法律若しくは第57条に規定する特例を定めた法律又はこれに基く条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程に違反した場合
(イ) 2号
職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合
(ウ) 3号
全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合
イ 32条(法令等及び上司の職務上の命令に従う義務)
職員は、その職務を遂行するに当って、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
ウ 33条(信用失墜行為の禁止)
職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
[1](1) 被告教育長は、平成4年2月28日、
「君が代については、歌詞が主権在民という憲法になじまないという見解もあり、身分差別につながるおそれもあり、国民の十分なコンセンサスが得られていない状況もある」とする内容の文書を作成し、被告は同年3月5日、この文書及び「文理解釈」と題する書面を各市町村教育委員会に送付した(甲78の(3)及び(4)、111、135並びに210の(1)及び(2))。
「その教育内容については校長を含む全教職員が創造するものであり、何人も介入してはならないという基本認識にたつ」
[2](2) 平成10年度入学式において、広島県内の公立小学校628校のうち国旗掲揚がされなかったものは4校、国歌斉唱がされなかったものは400校、公立中学校254校のうち国旗掲揚がされなかったものは2校、国歌斉唱がされなかったものは163校、公立高等学校(全課程)及び盲学校、聾(ろう)学校及び養護学校154校のうち国旗掲揚がされなかったものはなく、国歌斉唱がされなかったものは128校であった。
[3] 国歌斉唱が実施されなかった割合について、全国で小学校はワースト2位、中学校はワースト3位、高等学校(全日制)はワースト4位であるとされていた(以上、乙35)。
[4](3) 文部省は、平成10年4月27日及び28日、被告の所掌事務について、(a)学校における教育課程の編成及び実施状況等、(b)学校の管理運営の状況等及び(c)その他これに関連する事項について現地調査をした。
[5] 文部省は、被告に対し、同年5月20日、国旗国歌条項に基づく卒業式及び入学式の国旗掲揚・国歌斉唱等について、適正に実施するよう是正指導をした(以上、乙7、8及び35)。
[6](4) 被告教育長は、各市町村教育委員会に対し、同年12月17日及び平成11年2月23日、各学校において、国旗国歌条項に基づく卒業式及び入学式における国旗掲揚・国歌斉唱について適正に実施することを指導するように通知し、各県立学校長に対し、これを適正に実施するように指導した(甲211の(1)及び(2)、212、乙5、6並びに35)。また、同日付けで各県立学校長に対し、口頭で、卒業式及び入学式における国旗及び国歌の取扱いを適正に行うことを命じる職務命令をした(乙7、8及び35)。
[7] 被告は、平成10年度卒業式において、国歌斉唱を適正に行わなかったとして、平成11年3月23日県立学校長17名に対し、同年4月26日同3名に対し、それぞれ戒告処分をし、同年3月23日から平成12年3月31日までの間に、県立学校長合計5名及び市町立小学校長合計131名に対し文書訓告、市町村立中学校長合計83名及び市立小学校長1名に対し厳重注意をした(乙35)。
[8](5) 国旗及び国歌に関する法律は平成11年8月13日施行された。
[9](6) 被告教育長は、各市町村教育委員会教育長に対し、平成11年10月1日、上記(4)と同様の通知をした(甲214、乙1及び35)。
[10] また、被告教育長は、平成11年12月25日に開催された平成11年度第2回県立学校長会議において、学校における国旗・国歌の問題は、学習指導要領に基づく適正な取扱いをし、上記(1)の文書を始めとした上記(3)の文部省による是正指導以前にあった様々な事柄は、現在においては意味を持たないと明言し、これは翌26日の朝刊で報道された(乙3の(1)ないし(3)及び35)。また、同日の臨時広島県市町村教育委員会教育長会議でも同様の発言をし、これは翌27日の朝日新聞により報道された(乙3の(4)及び35)。
[11] 被告は、卒業式及び入学式において、国歌斉唱の指導を実施しなかったなどとして、平成12年3月31日市立小中学校長6名に対し、同年5月12日同小学校長4名に対し、同年7月14日府中市立小中学校長16名に対し、それぞれ戒告処分をした(乙35)。
[12](7) 被告は、平成12年12月26日、各県立学校長に対し、「卒業式及び入学式における国旗及び国歌に係る指導について」と題する広島県教育委員会教育部長通知を発し、次の点等について指導した(乙7、8及び35)。
ア 式次第に「国歌斉唱」を位置付け、式の進行中において、国歌が斉唱できるようにすること。[13](8) 原告らはいずれも本件各処分に先立ち、原告らが所属する学校の校長から国歌斉唱時に起立するように職務命令を受けたにもかかわらず起立しなかったとして文書訓告をされていた。
イ 儀式的行事の意義を踏まえ、国歌斉唱を厳粛かつ清新な雰囲気の中で実施すること。そのため、国歌斉唱に際しては、教職員は起立するとともに、児童生徒が起立して斉唱するよう指導すること。
[14](9) 原告番号1ないし15、17、20、22ないし28及び30は教諭、同16は養護教諭、同18、同19、同21及び同29は実習助手として、別表1原告欄記載の広島県立学校に勤務していた。
[15] これら原告は、平成13年度入学式において、国歌斉唱時に起立せず、被告から平成13年5月11日付けで戒告処分をされた。その処分理由は、当該原告らが所属する学校の校長から国歌斉唱時に起立するように職務命令を受けたにもかかわらず起立せず、これが地方公務員法32条及び33条に違反し、同法29条1ないし3号に該当するものであり、当該原告らには従前にも同様の行為があったというものであった。
[16](10) 被告は、平成14年2月19日、各県立学校長に対し、「平成13年度卒業式及び平成14年度入学式の適正な実施及び実施状況に関する報告について」と題する広島県教育委員会教育長通知を発し、平成13年度卒業式及び平成14年度入学式について、平成12年12月26日付け通知のとおり、適正に実施すること並びに卒業式及び入学式の実施に当たっては国歌斉唱時に起立するよう教職員に対して職務命令を明確に発することを指導した(乙13及び35)。
[17](11) 原告番号31ないし38は教諭として、別表2原告欄記載の広島県立学校に勤務し、平成13年度卒業式において、国歌斉唱時に起立せず、被告から平成14年3月28日付で戒告処分をされた。その処分理由は、上記(9)と同様に、当該原告らが所属する学校の校長から国歌斉唱時に起立するように職務命令を受けたにもかかわらず起立せず、これが地方公務員法32条及び33条に違反し、同法29条1ないし3号に該当するものであり、当該原告らには従前にも同様の行為があったというものであった。
[18](12) 原告番号39ないし40及び原告番号45は教諭として、亡P1(原告番号41P2、同42P3、同43P4及び同44P5が訴訟承継)は実習助手として、別表3原告欄記載の広島県立学校に勤務し、平成14年度入学式において、国歌斉唱時に起立せず、被告から平成14年5月10日付けで戒告処分をされた。その処分理由は上記(9)と同様に、当該原告らが所属する学校の校長から国歌斉唱時に起立するように職務命令を受けたにもかかわらず起立せず、これが地方公務員法32条及び33条に違反し、同法29条1ないし3号に該当するものであり、当該原告らには従前にも同様の行為があったというものであった。
[19](13) 被告は、各県立学校長に対し、平成15年2月4日及び平成16年2月9日、上記(10)と同様の指導をした(乙14、15及び35)。
[20](14) 原告番号12は平成15年度卒業式において、国歌斉唱時に起立せず、被告から平成16年3月30日付けで戒告処分をされた。その処分理由は上記(9)と同様に、校長から国歌斉唱時に起立するよう職務命令を受けていたにもかかわらず起立せず、これが地方公務員法32条及び33条に違反し、同法29条1ないし3号に該当するものであり、当該原告には従前にも同様の行為があったというものであった(甲1及び2)。
[21](15) 原告番号12は、上記(14)の処分について同年5月25日付けで広島県人事委員会に対し、審査請求をし、同年6月14日審査請求を却下された(甲3)。
[22] そこで、原告番号12は同年6月29日上記処分の取消しを求める本件訴え(平成16年(行ウ)第21号事件)を提起した。
[23](16) 原告番号1ないし45は、上記(9)、(11)及び(12)の各処分について地方公務員法49条の3所定の期間内に広島県人事委員会に対し、審査請求をして受理されたものの、裁決をされなかったことから、平成16年12月27日上記各処分の取消しを求める本件訴え(同第36号事件)を提起した。
(1) 原告らは卒業式及び入学式における国歌斉唱時に起立するように命ずる職務命令を受けたか
(2) 国旗国歌条項には法的効力があるか
(3) 上記(1)の各職務命令は適法であるか
(4) 被告による県立学校長らに対する一連の指導等が教育基本法10条1項の規定する「不当な支配」に当たるか
(5) 卒業式及び入学式において、生徒らに対し、国歌斉唱を指導することが生徒らの思想良心の自由を侵害し、憲法19条及び児童の権利に関する条約14条に違反するか
(6) 上記(1)の各職務命令は原告らの思想良心の自由を侵害し、憲法19条に違反するか
(7) 被告が原告らに対し本件各処分をするに当たり裁量権の逸脱又は濫用があったか
(被告の主張)
[24] 原告らは、別表1ないし4記載のとおり、平成13年度入学式及び卒業式、平成14年度入学式並びに平成15年度卒業式において、その当時原告らの上司であった校長らから、卒業式及び入学式における国歌斉唱の際には起立するように命じる内容の職務命令を受けた。
(原告らの主張)
[25] 原告らはいずれも上司であった校長らから適式な上記職務命令を受けたことはない。
(被告の主張)
[26]ア 学習指導要領は各学校の教育課程の基準として、その全体として法規としての性質を有する。
[27]イ 国旗国歌条項は卒業式及び入学式などにおいて国歌を斉唱するよう指導するものとするとし、作為義務を具体的に規定しており、卒業式及び入学式において、国旗を掲揚しないこと及び国歌を斉唱しないことは許されない。
(原告らの主張)
[28]ア 学習指導要領には全面的な法的拘束力があるわけではなく、その徹底を目的としてされた上記(1)の各職務命令は無効である。
[29] 学習指導要領は、教員の創意工夫や地方の実情に即した教育活動を保障するものでなければならない。そうであるにもかかわらず、学習指導要領には、細かいことまで立入りすぎ、法的拘束力を持たせることが適当でないものや、もともと法的拘束力を持たせる趣旨とは思えないものが含まれており、それらについては法的拘束力はない。
[30] 国旗国歌条項は、国旗掲揚と国歌斉唱を「指導するものとする」と記載し、「しなければならない」といった義務づけ規定の文言を採用していないから、国旗掲揚及び国歌斉唱を義務づけてはいない。また、国旗をどこに掲揚するとか、誰がそのように指導するかなどについて何も定めていないから、指導的助言的基準にすぎない。
[31]イ 学習指導要領は教育における法律主義に違反するものであり、指導的助言的基準にすぎないと解すべきであり、少なくとも国歌斉唱を義務付けるかのようにみえる部分は法規範性を有しない。また、国旗国歌条項が教職員が自ら斉唱し、生徒に君が代を斉唱するように指導するという趣旨であれば、一方的な理論ないし観念を生徒に教え込むことを強制することとなるから、その内容も国家の教育内容に対する決定権の範囲を逸脱しており違法である。
(被告の主張)
[32] 上記(1)の各職務命令は適法である。
[33]ア 原告らの上司であった校長らは学習指導要領等に基づき、卒業式及び入学式において国歌斉唱を実施する義務があり、自らの責任と判断に基づいて上記(1)の各職務命令をした。
[34]イ 卒業式及び入学式は学校における教育課程の一部として実施されるものであるから、学校に勤務する職員は、その式次第に従い、運営に協力する義務がある。
[35] 校長は卒業式及び入学式の式次第について、その裁量の範囲において決定する権限を有するから、その実施のために、各教職員に対して、職務命令を発することもできる。
[36] したがって、校長が、卒業式及び入学式において、国歌を起立して斉唱するという式次第を前提として、国歌斉唱の際には起立するよう求める職務命令は原告らの職務に関連するものである。
[37] 学校が主催する式において、教職員が定められた式次第に従わないと、式に参列する来賓や保護者に対して不信感を抱かせ、式の円滑な進行を妨げるおそれは否定できないから、校長が、卒業式及び入学式に出席する教職員に対し、式次第に従って、起立すべきことを命じる必要性がある。また、国歌斉唱は、国歌を尊重する態度を育てるという教育目的のために行われるものであることからすれば、生徒に対して範を示すという観点から、教職員である原告らに対し、国歌斉唱の際に起立するよう命じることには合理性もある。
(原告らの主張)
[38]ア 校長らは、各学校の状況やその状況の下で期待できる教育効果について検討することなく、被告の不当な支配に従って、原告らに対し、職務命令をしたから、各職務命令はいずれも教育基本法10条1項に違反する無効なものである。
[39]イ 職務命令はおよそ何らかの職務に関連していれば良いというものではなく、当該職務命令の内容が被命令者の遂行すべき本来の職務において、必要かつ合理的なものでなければならない。
[40] 原告ら教職員がその思想及び信条に基づいて国歌斉唱時に着席している行為自体は、特段、式の円滑な進行に対する妨げとなることはないから、被告が何としてでも全教職員を起立させたいという目的を達成するという施策の押しつけに他ならない。このような職務命令は必要性及び合理性を欠いており、違法である。
(被告の主張)
[41] 被告による県立学校長らに対する一連の指導通知等は教育基本法10条の規定する「不当な支配」に当たらない。
[42]ア 教育基本法10条は、国の教育統制権能を前提としつつ、教育行政の目標を教育の目的の遂行に必要な諸条件の整備確立に置き、その整備確立のための措置を講ずるに当たっては、教育の自主性尊重の見地から、これに対する「不当な支配」となることのないようにすべき旨の限定を付したところにその意味がある。したがって,教育に対する行政権力の不当、不要の介入は排除されるべきであるとしても、許容される目的のために必要かつ合理的と認められるそれは、たとえ教育の内容及び方法に関するものであっても、必ずしも同条の禁止するところではない。
[43]イ 県教育委員会は、県立学校を所管する行政機関として、その管理権に基づき、学校の教育課程の編成について基準を設定し、一般的な指示を与え、指導、助言を行うとともに、特に必要な場合には具体的な命令を発することもできる。
[44] 被告は、文部省からの是正指導に従い、県立学校や市町村教育委員会等に対し、学校管理運営の適正化等について指導通知を発し、実態調査を行ったところ、適正に行われていなかった。
[45] そこで、国旗国歌条項の趣旨を徹底する必要があり、かつ重要な行事において国歌を斉唱し、その際には起立するということが国内外を問わず広く一般的に認められた儀礼であることから、各県立学校長に対し、国旗国歌条項に沿った指導をするように指導した。
[46] このように被告による一連の指導はいずれも学習指導要領の趣旨に沿ったものであり、その内容も、地方の実情に即した教育の実現への関わりを期待された被告の判断に基づき、入学式等を厳粛かつ清新なものとするための方策として必要かつ合理的な範囲を超えたものとはいえない。また、入学式の挙行に当たり、各学校の自主的な判断に委ねられている場面も相当程度残されている。
(原告らの主張)
[47] 被告による卒業式及び入学式における国旗掲揚及び国歌斉唱に関する一連の指導等は教育基本法10条1項の規定する「不当な支配」に当たり、これに基づく、上記(1)の各職務命令は違法である。
[48] 教育委員会は、学校及び教師に対して、教育指導又は助言を超えて教育内容に関し命令監督をすることはできず、学校及び教師の教育課程編成権等の教育内容決定の権限を尊重しなければならない。
[49] 被告は、広島県内の校長らに卒業式及び入学式において国歌斉唱を実施するように強制し、これを実施しない校長を懲戒処分に処し、人事異動において、同年度の卒業式において、国歌斉唱を実施した校長は栄転させ、実施しなかった校長を左遷するという報復人事をした。さらに、被告は、各校長らに対し、入学式や卒業式での国歌斉唱時に生徒児童らに大きな声で歌わせるよう教育することを求め、教職員らに国歌斉唱時に起立して斉唱することを求めた。
[50] こうした被告の一連の指導等は、教育の自主性や教育に関する地方自治の原則に違反する。
(被告の主張)
[51]ア 本件では原告らが職務命令に従わなかったことが地方公務員法29条の規定する懲戒事由に当たるかどうかが争点であり、生徒の内心の自由は本件と関連性がない。
[52] 教員が起立して国歌を斉唱することと、生徒が起立して斉唱することとは必ずしも結びつくものでもなく、また、原告らが起立して斉唱することによって、生徒が君が代を起立して斉唱すべきものと考えるに至るとしても、それは次のような正当な教育目的に対し、相当な範囲の指導が行われた結果である。
[53]イ(ア) 君が代の「君」は、日本国憲法下において、日本国及び日本国民統合の象徴であり、その地位が主権の存する日本国民の総意に基づく天皇のことを指しており、君が代とは、日本国民の総意に基づき、天皇を日本国及び日本国民統合の象徴とする我が国のことであり、君が代の歌詞も、そうした我が国の末永い繁栄と平和を祈念したものと解することが適当である。
[54] そして、「日の丸」や「君が代」が平和主義や象徴天皇制を採用する戦後の現行憲法下においても既に半世紀有余にわたり我が国の国民の間で国旗及び国歌として定着したことから、国旗及び国歌に関する法律が制定された。
[55](イ) 学校における国旗国歌の指導は、上記(ア)の国旗国歌の意義を理解させ、これを尊重する態度を育てるとともに、諸外国の国旗と国歌も同様に尊重する態度を育てるために行われる。
[56] 具体的には、学習指導要領に基づき、社会科で国旗国歌の意義を理解させ、諸外国の国旗国歌を含めそれらを尊重する態度を育成すること、音楽の授業では国歌君が代を指導すること、入学式や卒業式などでは国旗を掲揚し国歌を斉唱するよう指導することとされている。
[57] これらは、あくまでも教育指導上の課題として指導を進めていくことを意味するものであり、憲法及び教育基本法に基づき、人格の完成を目指し、平和的な国家及び社会の形成者としての国民を育成することを目的として行っている。
[58] 教育は、個人がその人格を形成、発展させるという目的のもと、その過程を助けるために行われるものであるから、個人の内心に対する働きかけを教育から一切排除することは、教育の本質と相容れない。
[59] 人格の形成、発展を助けるという教育の本質からすれば、正当とされる教育目的に応じ、合理的な範囲の指導を行う限りにおいては、それが内心に対する働きかけを伴うものであっても、生徒の思想良心を不当に侵害するものではない。
[60] 卒業式及び入学式における国歌斉唱も教育活動の一環として、集団的に行われるものであって、国家と個人の関係のあり方について特定の考えを指導するものではなく、他の教育課程において国家と個人の関係のあり方についての様々な考え方などを生徒に教えることも禁止されていない。したがって、卒業式及び入学式において君が代の斉唱を実施し、これを指導することは、国を愛する心や日本人としての自覚及び国歌を尊重する態度を育てるという目的に対する指導としての合理的範囲を逸脱するものとはいえない。
[61](ウ) 国旗国歌の指導に当たって、生徒に対し、心理的な強制力が働く方法で指導等が行われることはない。卒業式及び入学式などの特別活動についてはいわゆる五段階評価等による評定の対象にならないし、単に国歌を歌わなかったり、起立しなかったりしたというようなことが、そのまま指導要録等に記載されることには通常ならない。
[62] したがって、卒業式及び入学式において国歌斉唱を実施し、指導することが、生徒の思想良心の自由を不当に侵害することはない。
[63](エ) 君が代の斉唱時に起立しない理由は様々であり、その中には、思想、良心に基づいて君が代を歌えないという以外の理由を有するものも当然存在し得るから、君が代斉唱時に起立しないことによって、起立しない者の思想が推知されるとはいえないから、生徒の沈黙の自由を侵害することもない。
[64] したがって、学習指導要領に基づく国歌に関する指導は、憲法19条及び児童の権利に関する条約14条には違反しないから、原告らがこれに従ったからといって憲法尊重擁護義務に違反することにはならない。
(原告らの主張)
[65]ア 原告らは憲法99条の規定する憲法尊重擁護義務を負っており、生徒らの内心の自由に対する侵害を防止する義務がある。
[66] 生徒らの中には国旗国歌について自己の意見を持ち、君が代を斉唱したくないと考えている者や、自発的な意見を持っていない者がいるから、卒業式及び入学式において国旗国歌について指導することは、次のとおり、生徒に対し、一方的な観念を植え付ける教育をして人権を侵害することとなる。
[67] 原告らが卒業式及び入学式における国歌斉唱の際に起立しなかったのは、生徒の思想良心の自由に対する侵害を防止するためであり、抵抗権の行使とも評価されるべきであるから、非違行為に当たらない。
[68]イ(ア) 君が代は天皇制を讃えるための歌であり、大日本帝国が他国を侵略するに当たり、超国家主義の思想を徹底させる必要から学校教育を通じて普及させられた歴史がある。
[69] 憲法19条は天皇制の権威を否定することを目的の一つとして規定されたものであり、君が代は戦前の天皇制をよみがえらせるものとして、現行憲法下では排斥される必要があり、憲法は君が代を忌み嫌う考え方を尊重することこそ予定している。
[70] 国旗国歌法にしても、国旗及び国歌を規定したにとどまり、これらに対する尊重義務を規定したわけではなく、意思決定は個々の国民に委ねている。
[71](イ) 児童や生徒が歴史を知れば君が代を歌うことが侵略戦争や天皇制の賛美につながることに思い至り、君が代を歌うことを拒否することとなるのであり、それにもかかわらず君が代を歌うことを強制することは、憲法19条により絶対的自由として掲げられている内心の自由、思想信条の自由を侵害し、児童の権利に関する条約14条にも違反する。
[72] 国旗国歌に関する指導の趣旨は、生徒らの愛国心を涵養することにあり、これは生徒らに特定の信条を植え付け、強制することになるから生徒らの思想信条を侵害する。国旗国歌を教育課題とするのであれば、生徒らがこの問題に対する自発的な信条を形成する余地があるようにし、すでに自発的な信条を形成している生徒に対してはその信条に対する干渉とならないように配慮しなければならない。君が代斉唱時に教職員らが一律に起立するような状況において生徒が自発的に起立しないことを決定することは極めて困難である。原告らが起立しないのはこのような生徒の人権の侵害を回避する目的をも有する。
(被告の主張)
[73] 上記(1)の各職務命令には、以下のとおり、その目的及び内容において必要性及び合理性があり、原告らの思想及び良心の自由を制約したり、その制約が許されないものであったりすることにはならないから憲法19条に違反しない。
[74]ア 原告らが侵害されたと主張する思想良心は、君が代に対する嫌悪感や不快感であり、そもそも様々な意見がある君が代についての一つの見解を採ることによるものである面が大きく、各原告それぞれの生い立ちや体験から直接に生じるものではないから、思想の核心部分ではない。
[75] 原告らは高教組の組合員であり、高教組による「司法闘争」の手段として、高教組の運動方針や考え方を、鸚鵡返しに主張しているにすぎず、実際に「公的機関が、参加者にその意思に反してでも一律に行動すべく強制することに対する否定的評価」を有しているわけではない。また、公務員であるとはいっても組織の一員である以上、組織の方針に反するこのような「信念」についてまで、組織が保障する必要はないのであって、こうした否定的評価は憲法19条で保障されてはいない。
[76]イ 上記(1)の各職務命令それ自体は単に外部的行為を要求するにすぎないものであり、前記のとおり、生徒らに対し国歌を尊重する態度を育てるという教育目的のために行われたものである。
[77] 君が代を歌えないという考えは、君が代は天皇を賛美する歌であるという、君が代についての様々な解釈の一つを前提とするものであり、原告らの主張する人間観及び世界観と必ずしも直接に結びつくものではない。
[78] また、上記(1)の各職務命令は、原告らに対して、例えば、「君が代」は国民主権及び平等主義に反し天皇という特定個人を賛美するものであるという原告らの考えは誤りである旨の発言を強制するなど、直接的に原告らの歴史観ないし世界観又は信条を否定する行為を命じて、原告らの内心における精神的活動を否定したり、原告らの思想、信条に反する特定の精神的活動を強制したりするものではないし、原告らが主張するような君が代に関する特定の解釈を前提として、それに対する敬意を求めるものでもない。
[79] しかも、卒業式等の儀式の場で行われる式典の進行上行われる出席者全員による起立及び斉唱であるから、原告らの主張する歴史観ないし世界観又は信条と切り離して、不起立という行為には及ばないという選択をすることも可能である。
[80] したがって、一般的には、卒業式等の国歌斉唱時に不起立行為に出ることは、原告らの歴史観ないし世界観又は信条と不可分に結びつくものではない。
[81]ウ 全国の公立高等学校では、卒業式等における国歌斉唱は従来から広く実施されているから、客観的にみて、卒業式等の国歌斉唱の際に起立するという行為は、卒業式等の出席者にとって通常想定され、かつ、期待されるものであり、一般的には、これを行う教職員等が特定の思想を有するということを外部に表明するような行為でもない。
[82] とりわけ、校長の職務命令に従ってこのような行為が行われる場合には、これを特定の思想を有することの表明とみることはできない。
[83]エ 「君が代」斉唱時に起立しない理由は様々であり、「君が代」斉唱時に起立しないことによって、必ずしも起立しない者の思想や信条が推知されるとはいえない。
[84] 本件では、儀式的場面における国歌斉唱の際の通常の行為として、起立の指示がされたものであり、教職員の思想や信仰の内容を推知する目的でされたものでもない。
[85] したがって、上記(1)の各職務命令は、原告らの沈黙の自由を侵害するものでもない。
[86]オ 憲法15条2項は、すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではないと定めており、地方公務員も、地方公共団体の住民全体の奉仕者としての地位を有する。
[87] このような地方公務員の地位の特殊性や職務の公共性から、地方公務員法30条は、地方公務員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、かつ、職務の遂行に当たっては全力を挙げてこれに専念しなければならない旨規定し、同法32条は、地方公務員がその職務を遂行するに当たって、法令等に従い、かつ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない旨規定している。
[88] 原告らは、いずれも広島県立学校の教職員で、法令等や上司の職務上の命令に従わなければならない立場にあり、校長が学習指導要領に基づき、法令の定めるところに従い所属教職員に対して本来行うべき職務を命じることは、当該職員の思想、良心の自由を侵すことにはならない。
[89] 国旗及び国歌に関する法律は、日の丸を国旗とし、君が代を国歌とする旨明確に定め、また、学校教育法43条に基づき定められた高等学校学習指導要領は
「入学式や卒業式などにおいては、その意義を踏まえ、国旗を掲揚するとともに、国歌を斉唱するよう指導するものとする。」と定めているところ、卒業式等に参列した教職員等が、国歌斉唱時に国旗に向かって起立して、国歌を斉唱するということは、これらの規定の趣旨にかなうものである。
[90] また、儀式的行事における国歌斉唱は、我が国に限らず、起立して行うことが通例であり、教員が、国歌斉唱時に起立する行為は、儀式的行事における通常の振る舞いを示すとともに、卒業式及び入学式にふさわしい雰囲気を形成するものとして必要な行為である。しかも、上記のとおり卒業式や入学式等の集団で行われる儀式においては、出席者に対して一律の行為を求めること自体に合理性があり、卒業式等における国歌斉唱は全国的には従前から広く実施されていた。
(原告らの主張)
[91] 上記(1)の各職務命令は原告らの思想良心の自由を侵害し、憲法19条に違反するから無効である。
[92]ア 原告らは、上記(5)(原告らの主張)イ(ア)の歴史観及び思想に加え、天皇制が民主主義の論理と相容れないものであり、基本的人権の保障にとっての妨害要素であり、日章旗・君が代は皇国史観又は身分差別につながるという思想を有する。
[93] また、原告らは、公的機関が、参加者にその意思に反してでも一律に行動すべく強制することに対する否定的評価及びこのような行動に自分は参加してはならないという信念ないし信条を有する。
[94] これらの原告らの思想は社会通念上一般に想定されず、およそ容認され得ないような特異なものではないから、憲法19条により保障される。
[95]イ 卒業式及び入学式における国歌斉唱の際に起立することは、身体的動作により、君が代に対する敬意及び尊重を表現するものである。
[96] これは原告らの思想信条とは相容れず、原告らの良心の内容を破壊する外部的行為を強いるものである。
[97]ウ 原告らは起立しないことにより、他から自己の君が代に対する内心の意思を推知され、沈黙の自由を侵害される。
(原告の主張)
[98] 本件各処分には次のとおり裁量権の逸脱濫用があるから違法無効である。
[99]ア 学校の教職員には、一般の労働者や公務員以上の特別な身分保障がされるべきである。
[100](ア) 改正前の教育基本法6条2項は、「法律の定める学校の教員は、全体の奉仕者であって、自己の使命を自覚し、その職責の遂行に努めなければならない。このためには、教員の身分は尊重され、その処遇の適正が期せられなければならない。」と規定する。この趣旨は、学校教職員の労働条件や身分保障について、子どもの教育を受ける権利の保障に関する教育条件の整備に関するものであるから、一般の労働者や公務員に対する身分保障以上でなければならないという趣旨である。
[101](イ) ILO、ユネスコによる「教員の地位」に関する勧告によると、教職における雇用の安定及び身分の保障は教員の利益とともに教育の利益にとって必須なものであり、教員の労働条件は、効果的な学習を最も良く促進し、かつ教員がその専門的任務に専念できるようなものとすることが確認されている。
[102](ウ) 教師の仕事は専門職であるから、(a)教師による学校教育活動の自主性の保障、(b)学校教師の自主研修の責務と権利、(c)学校教師の専門資格を公証する教育免許状、(d)学校教師の特別な身分保障が必要である。
[103]イ 本件各処分は、上記身分保障及び次の各点を考慮していないから裁量権の逸脱濫用がある。
[104](ア) 行政機関が、教職員の教育活動の具体的内容について偏向教育などにより違法であると認定し、それを理由に不利益処分をすることは、教育基本法10条1項の「不当な支配」に当たり、教職員の教育権を侵害する。
[105] また、上記特別の身分保障の観点からも、具体的教育活動が失当であることを理由として、直ちに不利益処分をすることは許されない。
[106](イ) 学校の教職員にとっては生徒や保護者との人間的信頼が重要であり、生徒の人間的成長発達を人間活動によって指導しなければならないから、人間的主体性が必要である。
[107] したがって、教育人事における行政機関の裁量権は、一般労働者や公務員よりも、教職員に対しては、思想信条面に関してより制限的でなければならない。
[108](ウ) 上記のとおり、原告らは自らと子供たちの思想と良心を守るためにあえて起立しなかったものである。
[109](エ) 原告らは本件各処分によりいずれも3か月の昇給延伸となり、現行の給与制度の下では、例えば原告番号1のP6の場合には定年退職時までに得ることのできる給与及び退職金の額が少なくとも50万円以上減額されるという重大な不利益を被る。
(被告の主張)
[110] 本件各処分には裁量権の逸脱又は濫用はない。
[111]ア 教員には特別の身分保障はなく、その懲戒処分についても特別の法的な制限はない。
[112](ア) 大学以外の学校における教育公務員の具体的身分保障について明記した規定は存在しないし、原告の主張する教育条理解釈は明文の規定を無視し、行政実例や判例に照らして全く成り立ち得ない考え方である。
[113](イ) ILO及びユネスコによる「教員の地位に関する勧告」についても、そもそも法的拘束力を有する条約ではなく、各国の努力して到達すべき目標を示した勧告にすぎない。
[114]イ 原告らの行為は地方公務員法32条及び同法33条に違反し、同法29条各号所定の懲戒事由に該当するものであり、本件各処分は以下のとおり適切である。
[115](ア) 原告らは上記(1)の各職務命令に違反した。
[116](イ) 生徒に範を示すのみならず、生徒とともに起立して斉唱すること自体が教育活動である。
[117] また、不起立行為が結果的に参列者の目に入らなかったとしても、その場の状況によっては式の円滑な進行の妨げとなり、参列者に対して不信感を抱かせるおそれがある。
[118](ウ) 原告らは本件各処分を受ける以前から、同様の職務命令に違反し、被告から文書訓告の措置を受けていた。
[119](エ) 本件各処分は地方公務員法上の処分として最も軽い戒告処分である。
[120] 原告らの上司であった校長らが、原告らに対し、別表1ないし4記載の日時場所において、少なくとも「発言内容」欄記載の発言をしたことについては、当事者間に争いがない。
[121] これらの発言のうち原告番号1、5ないし11、24、27、34、36、37、39及び45並びに平成15年度卒業式における原告番号12については、いずれも職務命令であることが明示され、国歌斉唱時に起立するように指示されている。したがって、これらの原告らについては、各校長らから上記日時場所において、君が代斉唱の際に起立するように命じる職務命令をされたことを認めることができる。
[122] そのほかの原告らについて検討すると、前記各校長らの発言内容はいずれも国歌斉唱時において起立することを求めるものであることのほか、前提事実のとおり、原告らの上司であった各校長らは被告から教職員らに対し国歌斉唱の際には起立すべきことについて、あらかじめ職務命令をするように指導されていたから、各校長において上記各発言は職務命令としてされたというべきであり、他方、原告らにおいても、いずれも国歌斉唱の際に起立するように命じる職務命令に違反したとして訓告処分を受けたことがあったことは前提事実のとおりであるから、上記各発言が職務命令としてされたことを当然認識していたものと推認すべきである。
[123] したがって、原告ら全員についていずれも別表1ないし3記載の日時場所において、卒業式又は入学式における君が代斉唱の際には起立するように命じる職務命令を受けたというべきである。
[124] 原告らはこれら職務命令が適式になされたものではないと主張するところ、そもそもどのような要件を欠くと主張するものか全く不明である。地方公務員法は職務命令を発する手続的な要件について何ら規定しておらず、口頭によることも可能であり、上記各職務命令は適式になされたものであるというほかない。
(1) 学習指導要領の法的効力
[125]ア 憲法上、国は国政の一部として適切な教育政策を樹立して実施する権能を有し、国会は国の立法機関として教育の内容及び方法について法律により直接に又は行政機関に授権して必要かつ合理的な規制を施す権限を有し、このような規制を施すことが子どもの利益のため又は子どもの成長に対する社会公共の利益のために要請される場合もあり得る。
[126] もとより、民主主義的政治過程を通じてされる立法行政による意思決定はさまざまな政治的要因によって左右されるものであるのに対し、教育は本来人間の内面的価値に関する文化的な営みとして党派的な政治的観念や利害によって支配されるべきではない。
[127] したがって、教育内容に対する国家的介入はできるだけ抑制的であることが要請されるし、個人の基本的自由を認めその人格の独立を国政上尊重すべきものとしている憲法の下においては、子どもが自由かつ独立の人格として成長することを妨げるような国家的介入、例えば、誤った知識や一方的な観念を子どもに植えつけるような内容の教育を施すことを強制するようなことは、憲法26条・13条により禁じられる。
[128]イ 行政機関が教育について許容される目的のために、必要かつ合理的な範囲内において、教育内容及び方法に関する基準の設定等をすることは、必ずしも教育基本法10条の禁止するところではなく、その限度で教育内容に関係のあるいわゆる内的事項に関するものであっても立法による委任が可能であると解される。学習指導要領自体が教育における法律主義に違反するという原告らの主張には理由がない。
[129] しかしながら,上記基準は教育における機会均等の確保と全国的な一定の水準の維持という限られた目的のために必要かつ合理的と認められる大綱的基準にとどめられるべきものであり、学習指導要領の個別の条項が上記大綱的基準を逸脱し、また、内容的にも教師に対して一方的な一定の理論や観念を生徒に教え込むことを強制するようなものであれば、教育基本法10条1項の不当な支配に該当するものとして、法規としての性質が否定されることもあり得る。
[130] 文部科学大臣は、学校教育法43条の規定する高等学校の教科に関する事項を定める権限に基づき、高等学校における教育の内容及び方法につき、同法73条の規定する養護学校の教科に関する事項を定める権限に基づき、養護学校における教育内容及び方法につき、それぞれ教育の機会均等の確保等の目的のために必要かつ合理的な基準を設定することができる。そして、同規則57条の2、73条の10は、高等学校及び養護学校高等部の教育課程については、教育課程の基準として、それぞれ学習指導要領によるものとすると規定する。
[131] したがって、そのために定められた学習指導要領は、上記限度において法規としての性質を有する。
[132] 盲学校等については高等学校学習指導要領が準用されているから、以下、一括して高等学校学習指導要領を前提として検討する。
(2) 国旗国歌条項の法的効力
[133]ア 日本国憲法は、天皇について、日本国及び日本国民統合の象徴であり、その地位が主権の存する日本国民の総意に基づくものとして規定し、その存在を認めるところであり、国民主権及び法の下の平等に違反するものであるということはできない。
[134]イ 学校行事は、学習指導要領の第4章(特別活動)において、ホームルーム活動、生徒会活動等に関する条項と共に規定され、
「学校行事においては、全校若しくは学年又はそれらに準ずる集団を単位として、学校生活に秩序と変化を与え、集団への所属感を深め、学校生活の充実と発展に資する体験的な活動を行うこと」を目標とし、そのうち儀式的行事については
「学校生活に有意義な変化や折り目を付け、厳粛で清新な気分を味わい、新しい生活の展開への動機付けとなるような活動を行うこと」とされている。
[135]ウ 乙1によれば、国旗国歌条項は、国際化の進展に伴い、日本人としての自覚を養い、国を愛する心を育てるとともに、生徒が将来国際社会において尊敬され信頼される日本人として成長していくためには、生徒に国歌に対して正しい認識を持たせ、それらを尊重する態度を育てることが重要なことであること、入学式・卒業式は学校生活に有意義な変化や折り目を付け厳粛かつ清新な雰囲気の中で新しい生活への動機付けを行い、学校・社会・国家などの集団への所属感を深める上でよい機会となることから、このような意義を踏まえた上で、これらの式典において国旗を掲揚し、国歌を斉唱するように指導する趣旨等で設けられたものであることが認められる。さらに、国際社会においては、その歴史的沿革を問わず、自国のものであれ、他国のものであれ、国旗ないし国歌に対して敬意を表するべきであるとする共通の認識が存在していることも周知の事実である。この意味において、国旗国歌条項は、実際にその目的を達成するために相当なものであるかどうかについての議論はありうるものの、明日の日本を担うべき高校生に対する教育指導方針としては必要かつ合理的な内容のものでないとはいえない。また、これは生徒らに対し、法的及び社会的な規範を身につけさせるための指導であると評価することもできる。
[136] このように、国旗国歌条項は、人格の完成を目指し平和的な国家及び社会の形成者としての国民を育成することに資するものであり、教育の内容及び方法に関するものであるとはいえ、その内容は許容される目的のために法令に適合した必要かつ合理的なものでないとはいえず、教育における機会均等の確保と全国的な一定の教育水準の維持という観点から全国一律に定める必要性がある。
[137] さらに、国旗国歌条項は、そこで規定されている内容以上に国歌斉唱の具体的方法等について何ら指示するものではなく、教師による創造的かつ弾力的な教育の余地や地方ごとの特殊性を反映した個別化の余地を残している。また、国歌等に対して敬意を表する態度を育てることは、国歌の歌詞について特定の解釈を基にその内容に対して賛意を表明させることを求めるものでないことはもとより、教職員に対して国歌について一方的な一定の理論を生徒に教え込むことを強制するものではない。そして、教師が国歌をめぐる歴史的背景や国歌の歌詞に関して様々な見解があることを教えることについても、特定の見解に著しく偏るようなものでないかぎり禁止するものではない。
[138] 以上によれば、国旗国歌条項は大綱的基準として、内容的にも一方的な一定の理論や理念を生徒に教え込むことを教師に強制するものともいえないから、憲法及び教育基本法に反するものではなく、さらに教育における機会均等の確保と全国的な一定の水準の維持という目的のために必要かつ合理的な基準を設定したものとして、法的効力を有するというべきである。
[139] もっとも、国旗国歌条項が「・・・ものとする」という表現を採ったことから、法令用語の通常の用語例に照らして、これを原則ないし方針とするにとどめるものであることが明らかである。
ア 職務命令の適法要件
[140] 職務命令が適法有効であるためには、職務上の上司とその部下職員という関係を前提に、部下職員の職務に関連するものであって、法令に違反するものでないこと、その目的や内容に合理性があることを要すると解される。
[141]イ 学校教育法28条3項によると、校長は、校務をつかさどり所属職員を監督する権限を有しており、教育課程、学級及び授業等の時間割を編成し、各教員に校務を分掌させることができる。また、広島県立特別支援学校学則7条1項も、各学科の教育課程及び授業時間数は、学習指導要領等の基準により、校長が定めると規定する。
[142] したがって、卒業式及び入学式における国歌斉唱は、校務をつかさどり所属職員を監督する権限を有する校長が上記のとおり法的効力のある学習指導要領に基づきその権限と責任に基づいて行う校務である。したがって、校長が国歌斉唱の実施に当たり各教職員に対してする職務命令は許容される目的のためにされる職務に関連するものである。なお、被告による県立学校長らに対する一連の指導等が教育基本法10条1項の規定する不当な支配に当たらないことは後述のとおりである。
[143] 次に、国歌斉唱は国歌に敬意を表する態度を育てるという教育目的のために行われるものであることからすれば、生徒に対して範を示すという観点から、教職員である原告らに対して国歌斉唱の際に起立するよう命じることは方法として穏当であり、合理的である。ちなみに、上記事実関係及び被告の主張はともかく、本件において問題とされる職務命令は国歌斉唱時における起立をいうものであり、その斉唱までを命ずるものではない。
[144] したがって、上記1の各職務命令は適法である。
ア 教育基本法10条の規定する「不当な支配」の意義
[145] 前述のとおり、憲法上、国は適切な教育政策を樹立・実施する権能を有し、国会は国の立法機関として、教育の内容及び方法について法律により直接に又は行政機関に授権して必要かつ合理的な規制を施す権限を有し、このような規制を施すことが子どもの利益のため又は子どもの成長に対する社会公共の利益のために要請される場合もありうる。
[146] 教育基本法10条は、国の教育統制権能を前提としつつ、教育行政の目標を教育の目的の遂行に必要な諸条件の整備確立に置き、その整備確立のための措置を講ずるにあたっては、教育の自主性尊重の見地からこれに対する「不当な支配」となることのないようにすべき旨の限定を付したものと解される。
[147] したがって、教育に対する行政権力の介入は許容される目的のために必要かつ合理的と認められる限り、教育の内容及び方法に関するものであっても、不当な支配には当たらないというべきである。
イ 被告による県立学校長らに対する一連の指導等が「不当な支配」に当たるか
[148] 前提事実のとおり、被告は、各校長に対し、学習指導要領の徹底を標榜して、職務命令・指導・通知等によって国旗国歌条項に基づく卒業式等における国歌斉唱等を適正に実施するよう指導し、これに従わない校長に対しては懲戒処分等をもって臨み、また教職員に対しては明確に職務命令を発するよう指示するなどしてその方針を実現しようとした。したがって、このような状況下において、校長の発した職務命令は学習指導要領及び学校教育法を根拠として自らの責任と判断において被告とは独立にしたものであるということはできない。
[149] ところで、上記指導から上記1の各職務命令に至る全体としてみたときに、被告による一連の指導等は「不当な支配」に当たらないというべきである。
[150] すなわち、被告は、県立学校を所管する行政機関として、その管理権に基づき、学校の教育課程の編成について基準を設定し、一般的な指示を与え、指導・助言を行うとともに、特に必要な場合には具体的な命令を発することもできる。
[151] 広島県内の極めて多数の県立学校において国旗国歌の指導が行われていなかったことは前提事実のとおりである。このような状況において、被告は、文部省からの是正指導を契機として、各校長に対し、国旗国歌条項に基づく一連の指導をしたというのであって、これら一連の指導自体はいずれも学習指導要領の趣旨に沿ったものであり、必要かつ合理的な範囲を逸脱しているとはいえないし、その具体的な指示内容も学習指導要領の趣旨に沿ったものであって、不必要不合理であるということはできない。
[152]ア 上記1の各職務命令は教職員らに対し向けられたものであり、生徒らに対し直接向けられたものではないから、生徒らの思想良心の自由を直接侵害するものではない。ここではまず、国歌斉唱を指導することそのものが生徒の思想良心の自由を侵害するかどうかが問題となる。
[153] 教育基本法1条が「教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない」と規定するように、教育は人格を形成し発展させるという目的のために行われるべきものである。このように、教育はその性質上生徒の内心に対する働きかけを伴うことが予定されており、これが憲法19条に違反して許されないとすると、社会科学の分野に関する事柄や生活指導をすることは不可能であり、およそ公教育が成り立たない。したがって、正当とされる教育目的についての合理的な範囲における指導は、それが内心に対する働きかけを伴うものであっても、憲法19条に違反するものではないと解される。
[154] 上記2のとおり、学習指導要領に基づく国歌に関する指導は憲法及び教育基本法の目的にも沿う正当な教育目的によるものである。また、卒業式等において君が代の斉唱を実施することは、生徒らに対する直接強制を伴うようなものではない限り、諸外国の国旗や国歌と同様にこれに対する敬意を表する態度を育てるという正当な目的に対する指導として、社会通念上合理的範囲を逸脱するものではない。
[155] 上記3のとおり、上記1の各職務命令に基づく生徒らに対する指導内容は、教職員に対し国歌斉唱時に起立することを命じ、これにより生徒らに対し、率先して国歌に対する敬意を表する態度を示すことにより、間接的に生徒らに働きかけるというものであり、生徒らに対する直接強制を伴うものではなく、方法としても穏当なものであって、合理的範囲を逸脱する指導であるとは到底いえない。
[156]イ 生徒らに対し君が代斉唱時に起立するように指導することは生徒らの沈黙の自由を侵害するものではなく、その理由は後述の教職員における場合と同様である。
[157] したがって、上記1の各職務命令に基づく生徒らに対する国歌斉唱の指導は、生徒の内心に対する働きかけを伴うものであるとはいえ、生徒の思想良心の自由を不当に侵害するものではなく、憲法19条に違反するとはいえない。
ア 原告らの主張についての検討
[158] 原告らは、(a)国歌「君が代」が天皇制を讃えるための歌であり、大日本帝国が他国を侵略するにあたり超国家主義の思想を徹底させる必要から学校教育を通じて普及させられたものであるという歴史観、(b)憲法19条は天皇制の権威を否定することを目的として規定されたものであり、君が代は皇国史観又は身分差別につながるものとして現行憲法下では排斥される必要があり、憲法は君が代を忌み嫌う考え方を尊重することこそ予定しており、天皇制は民主主義の論理と一貫していない又は基本的人権の保障にとっての妨げになるという思想を有すると主張する。また、原告らは、(c)公的機関が参加者にその意思に反してでも一律に行動すべく強制することに対する否定的評価及びこのような行動に自分は参加してはならないという信条を有するとも主張する。
[159] まず、(a)及び(b)は君が代に関する原告らの歴史観及びこれに由来する原告らの思想を述べるものである。そして、卒業式等の儀式において国歌斉唱の際に起立することは、社会的儀礼としての意味があるとともに、国歌に敬意を表する態度を示す外部的行為である。したがって、学校の儀式的行事において国歌斉唱の際に起立しないということが原告にとって上記歴史観及び思想に基づく一つの選択であるとはいうことはできる。しかしながら、国会による民主主義的な政治過程を通じて成立した国旗及び国歌に関する法律により国歌は君が代であると定められ、国旗国歌条項に基づく指導が必要かつ合理的なものであることも上記2のとおりであるから、これらのことを前提とすれば、君が代に関する歴史観や思想はさておいて、卒業式等の儀式的行事における国歌斉唱の際に起立する限度で敬意を示すという選択をすることも一般的に十分ありうることであり、これを拒否するということが原告らの主張する歴史観及び思想と論理必然なものとして、不可分に結びつくものであるとはいえない。すなわち、後述のとおり、一般に国歌斉唱に際して起立するということは当該国歌に対して敬意を表するという限度で行為者の態度ないし意思を表明するものであるにとどまり、当該国歌の内容ないしはその特定の解釈に賛同することを意味するわけではない。
[160] したがって、上記1の各職務命令は原告らの歴史観ないし世界観という内心の核心部分を直接否定する外部的行為を強制するものではないというべきである。
[161] 次に、(c)公的機関が参加者にその意思に反してでも一律に行動すべく強制することに対する否定的評価及び信条について検討すると、原告らはいずれも地方公務員の地位にあり、その職務として儀式的行事に参加し、しかも国歌斉唱の際に起立することが原告らの内心の核心的部分に反する外部的行為に当たらないことは後述のとおりであって、そのような場合に地方公務員である原告らにおいてその主張するようなおよそ内心に反する義務を強制されない自由が一般に認められるならば法治国家は成り立たなくなるから、そのような信条に基づき義務を否定することが憲法19条による保障の対象となるとは解することができない。
イ 上記1の各職務命令の客観的な性質・効果
[162] 上記1の各職務命令がされた当時、全国の公立学校における卒業式や入学式において、国歌斉唱が従来から広く実施されており、その際に出席者が起立していたことは公知の事実であり、客観的にみて、卒業式及び入学式の国歌斉唱の際に起立するという行為は教職員を含む卒業式等の出席者にとって通常想定されかつ期待される社会的儀礼であったというべきである。そして、教職員らがその職務として卒業式等に参加していることは客観的に明らかであるから、国歌斉唱の際に一斉に起立するという儀礼的行為をすることについて他の参加者から原告ら個人に関わる私的な表現行為とみられることは通常ありえないのであって、ひいてはこのような儀礼的行為にとどまるものについて職務命令を発したからといって、そのことによって原告らの内心の自由を侵害する性質を有するとはいえない。
[163] すなわち、上記1の各職務命令は単に国歌斉唱の際に起立することを命じたものであって、原告らに対し、例えば、「君が代」は国民主権・平等主義に反し、天皇という特定個人又は国家神道の象徴を賛美するものであるという原告らの考えは誤りである旨の発言を強制するなど、直接的に原告らの歴史観ないし世界観又は信条を否定する行為を命じて原告らの内心における精神的活動を否定したり、原告らの思想信条に反する特定の精神的活動を強制したりするものではない。また、原告らが主張するような君が代に関する特定の解釈を前提としてそれに対する敬意を求めるものでもなく、これを行う教職員等が特定の思想を有するということを告白させる行為であるとも評価することはできない。
[164] したがって、客観的な性質・効果に照らしても、上記1の各職務命令は原告らの内心の核心部分を直接否定するようなものではない。
ウ 原告らの地位・職務との関係
[165] 憲法15条2項は、すべて公務員は全体の奉仕者であって一部の奉仕者ではないと規定し、地方公務員も地方公共団体の住民全体の奉仕者としての地位を有する。このような地方公務員の地位の特殊性や職務の公共性から、地方公務員法30条は、地方公務員は全体の奉仕者として公共の利益のために勤務しかつ職務の遂行に当たっては全力を挙げてこれに専念しなければならない旨規定し、同法32条は、地方公務員がその職務を遂行するに当たって、法令等に従いかつ上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない旨規定する。
[166] 原告らはいずれも広島県立学校の教職員であったものであり、法令等や上司の職務上の命令に従わなければならない立場にあって、上司である各校長から学校行事である卒業式及び入学式に関して上記1の各職務命令を受けた。
[167] 他方、国旗及び国歌に関する法律は君が代を国歌とする旨明確に定め、平成19年6月27日法律第96号による改正前の学校教育法18条2号及び36条は、義務教育の目標の一つとして、郷土及び国家の現状と伝統について正しい理解に導き、進んで国際協調の精神を養うことを目標としてその達成に努めなければならないことを規定し、同法42条は高等学校における教育については、高等学校における教育の目標として、中学校における教育の成果をさらに発展拡充させて国家及び社会の有為な形成者として必要な資質を養うことと規定する。国旗国歌条項はこれらの規定を受けたものと解される。
[168] そして、卒業式等に参列した教職員等が国歌斉唱時に起立し、生徒に率先して国歌に対する敬意を示すことは、生徒らに対する上記指導に有益な行為であり、これらの規定の趣旨にかなうものである。また、儀式的行事における国歌斉唱は我が国に限らず起立して行うことが通例であり、教員が国歌斉唱時に起立する行為は儀式的行事における通常の振る舞いを示すとともに、卒業式及び入学式にふさわしい雰囲気を形成するためにも必要な行為であるし、集団で行われる儀式である卒業式等においては、無秩序となり学校行事の意義を損ねることを防ぐ必要もあるから、出席者に対して整然とした行動を求めること自体にも合理性がある。かえって、原告ら教職員が卒業式等の式典において国歌斉唱の際に起立することを拒否することを容認しては儀式の進行ひいては学校の運営に当たって秩序を維持することができなくなる可能性がある。
[169] そうすると、原告らの職務上の地位等に照らしても、卒業式及び入学式等の行事に出席し、国歌斉唱の際に起立することは必要かつ合理的なことであり、上記1の各職務命令は不必要かつ不合理に原告らの信念に反する行為を強制するものではない。
エ 原告らの沈黙の自由
[170] 国歌斉唱時に起立するという行為の意味するところは上記のとおりであって、起立をしたからといって、そのことによって国歌の意味するところに賛同することになるわけではない。また、上記1の各職務命令は原告らの思想や信仰の内容を推知する目的でされたものでないことについては当事者間で争いがない。
[171] したがって、上記1の各職務命令が原告らの沈黙の自由を侵害するものと評価することもできない。
[172]オ 以上によれば、上記1の各職務命令は憲法19条の保障する思想及び良心の自由の制約には当たらないと解される。
[173](1) 前記のとおり地方公務員法29条1項は、同条所定の懲戒事由があるときには処分行政庁が戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができると規定するほか、懲戒処分をすべきであるかどうか、また懲戒処分をする場合にいかなる処分を選択すべきかなどについて具体的基準を定めていない。
[174] そもそも、地方公務員に対する懲戒処分は、全体の奉仕者として公正中立な立場において職務に専念すべき地方公務員の職務の適正さを保持し、組織の規律を保つため、非行に対して課する行政監督権の作用である。したがって、懲戒権者は、懲戒事由に該当すると認められる行為の原因、動機、性質、態様、結果及び影響等のほか、当該公務員の上記行為の前後における態度、懲戒処分等の処分歴、選択する処分が他の公務員及び社会に与える影響等、諸般の事情を総合的に考慮して、懲戒処分をすべきかどうか、また、懲戒処分をする場合にいかなる処分を選択すべきか決定すべきものである。
[175] これら地方公務員法の規定及び懲戒処分の趣旨等に照らせば、当該公務員に対し懲戒処分をすべきかどうか及びいかなる処分を選択すべきかどうかについては、地方公務員法各条の定める限度で、平素から庁内の事情に通暁し、職員の指揮監督に当たる懲戒権者の裁量に任されているというべきである。
[176] なお、原告らは教育公務員については教育条理上他の公務員よりも特別の身分保障がされるべきであり、教育公務員に対する懲戒処分の裁量の幅は小さいなどと主張する。しかしながら、原告らも認めるとおり、大学の教員を除いた一般の教育公務員について特別の身分保障を定める法律は存在せず、他の公務員とは異なる特別の身分保障があるとする実定法上の根拠は全くない。そして、全体の奉仕者である公務員について実定法上の根拠もないのに条理を理由として特別の身分保障を図ることは許されないというべきであって、原告らの主張は単に独自の意見を述べるものにすぎず、採用することはできない。
[177](2) 行政事件訴訟法30条は、行政庁の裁量処分については、裁量権の範囲をこえ又はその濫用があった場合に限り、裁判所は、その処分を取り消すことができると規定する。
[178] 上記1ないし6からすると、原告らは上記1の各職務命令に従う義務を負っていたと認められるところ、これに違反したものであるから、服務規程違反として地方公務員法32条に違反する。
[179] また、教職員である原告らが卒業式及び入学式の運営責任者である校長の職務命令に従わないことは、学習指導要領に基づく指導を妨げることとなるし,他の参加者に対してその影響を及ぼすことになれば、式典の円滑な進行が妨げられることは明らかである。また、生徒や式典の参列者に対し、原告らを含む学校教職員らの服務態度に対する信頼を失わせる行為であって、地方公務員法33条にも違反する。
[180] そうすると、原告らが上記1の各職務命令に従わなかったのは地方公務員法29条1項1ないし3号の懲戒事由に該当すると評価される。
[181] そして、前提事実のとおり、原告らは本件各処分以前にも上記1の各職務命令と同旨の職務命令に従わず文書訓告の措置を採られたことがあり、重ねて上記1の各職務命令に違反したのであるから、懲戒処分によらなければ原告らの服務規程違反を是正することができないと判断した被告の判断が不合理なものであったとは必ずしもいうことができない。また、戒告処分は地方公務員法上予定されている懲戒処分のうちでは最も軽いものである。
[182] 以上によれば、原告らが負担する不利益を考慮しても、本件各処分について、被告に裁量権の範囲をこえ又はその濫用があったとは認めることができない。
[183]8 原告らは他にもるる主張するものの、いずれも本件との関連性がないか又は認めるに足りる証拠がない。
[184] 以上によれば、原告らの本件各請求にはいずれも理由がないから棄却することとし、主文のとおり判決をする。
裁判長裁判官 橋本良成 裁判官 佐々木亘 裁判官 西田昌吾
原告
1 36号事件原告 P6
2 同 P7
3 同 P8
4 同 P9
5 同 P10
6 同 P11
7 同 P12
8 同 P13
9 同 P14
10 同 P15
11 同 P16
12 両事件原告 P17
13 36号事件原告 P18
14 同 P19
15 同 P20
16 同 P21
17 同 P22
18 同 P23
19 同 P24
20 同 P25
21 同 P26
22 同 P27
23 同 P28
24 同 P29
25 同 P30
26 同 P31
27 同 P32
28 同 P33
29 同 P34
30 同 P35
31 同 P36
32 同 P37
33 同 P38
34 同 P39
35 同 P40
36 同 P41
37 同 P42
38 同 P43
39 同 P44
40 同 P45
41 亡P1訴訟承継人36号事件原告 P2
42 同 P3
43 同 P4
44 同 P5
上記2名法定代理人親権者母 P2
45 36号事件原告 P46
原告ら訴訟代理人弁護士 外山佳昌 増田義憲 山田延廣 藤井裕
原告ら訴訟復代理人弁護士 寺本佳代
被告兼処分行政庁 広島県教育委員会
同代表者委員長 D1
同訴訟代理人弁護士 水中誠三
同両事件指定代理人 D2 外5名
同21号事件指定代理人 D3 外1名
(別表1)
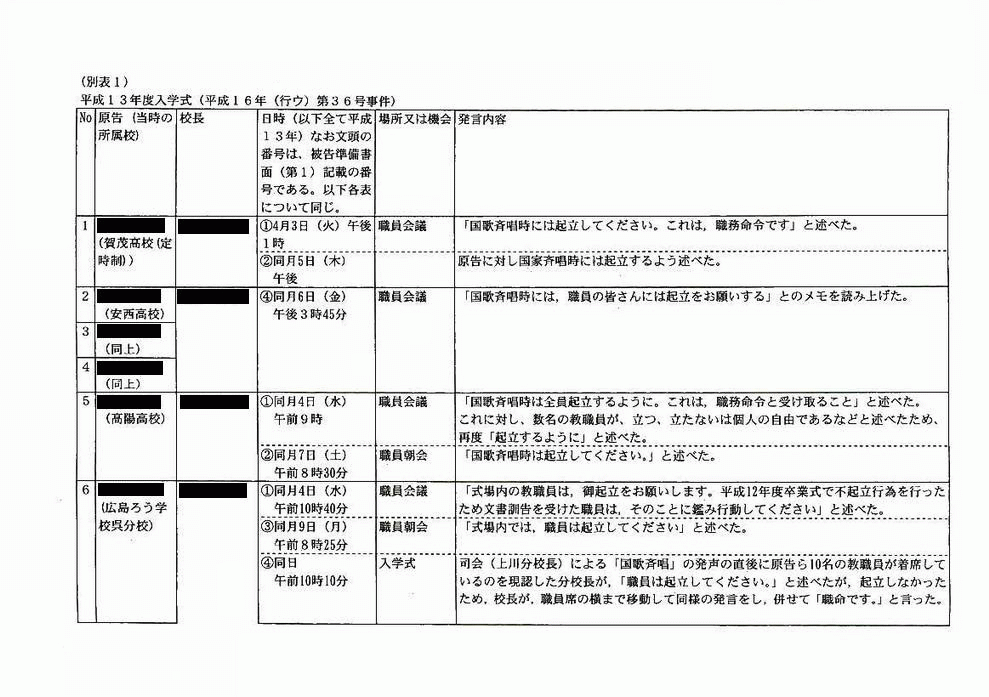
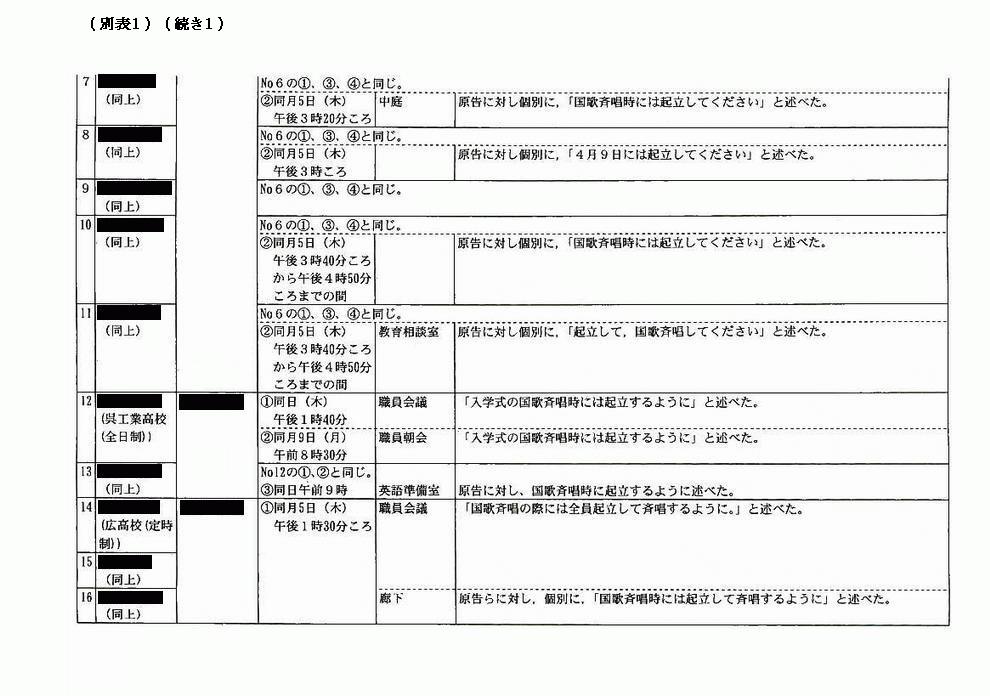
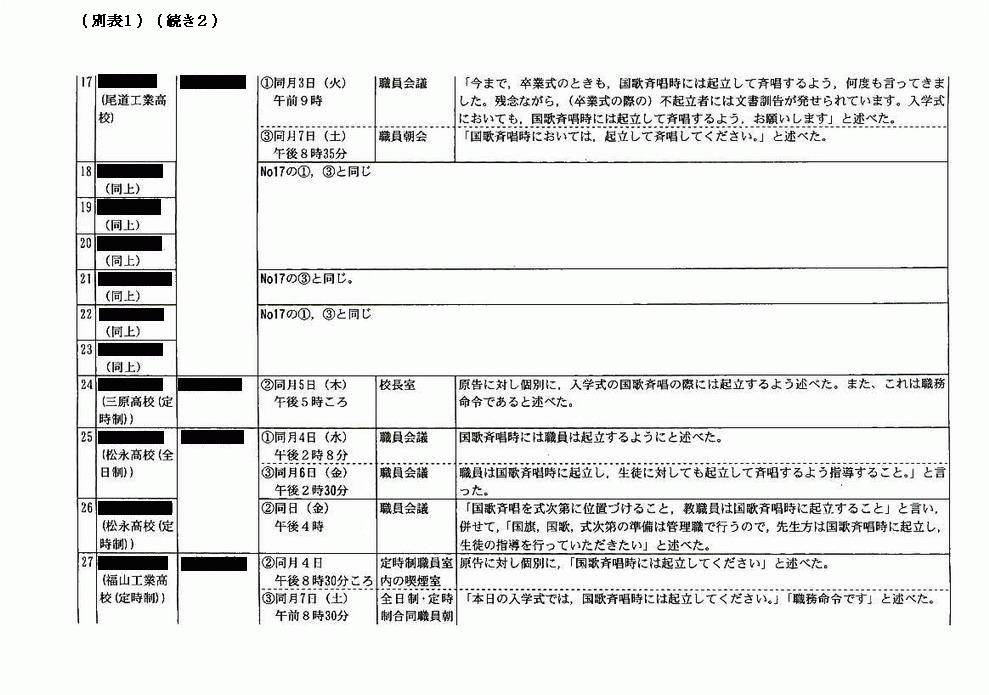
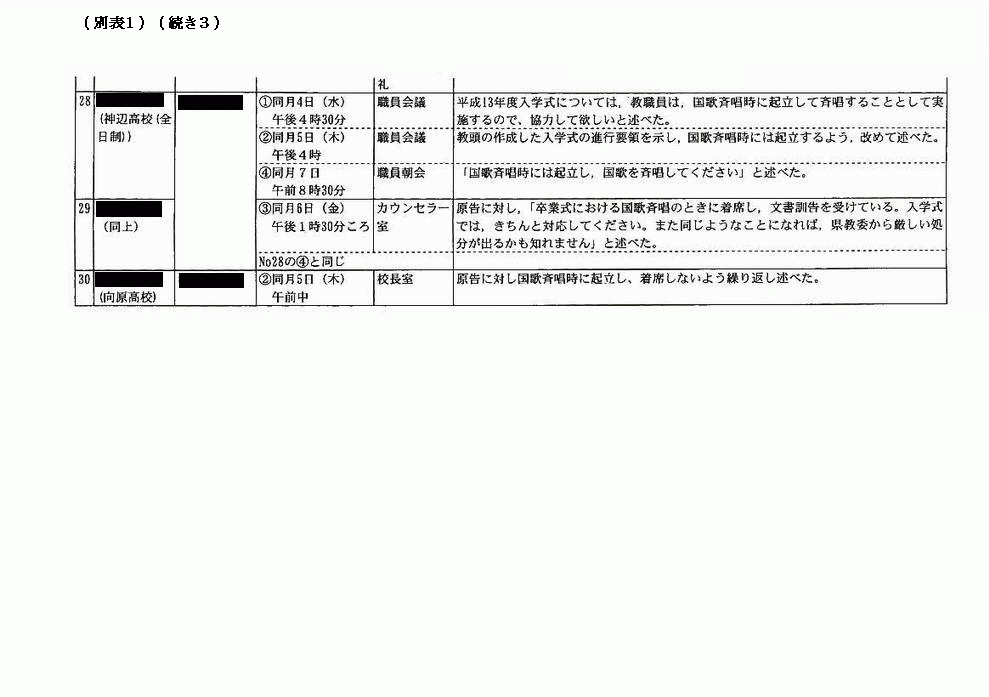 (別表2)
(別表2)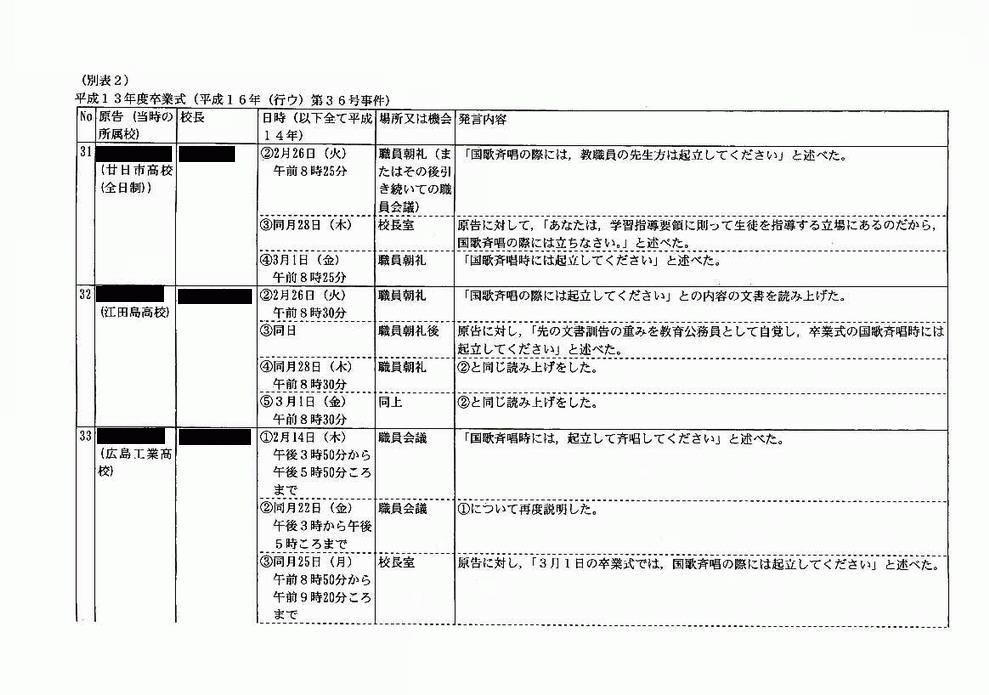
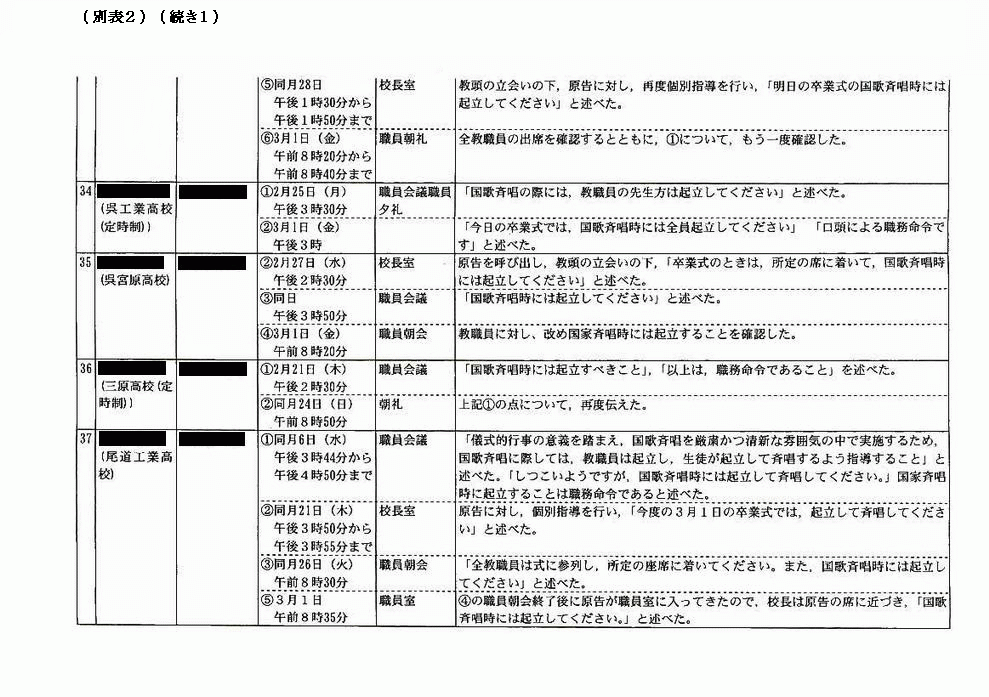
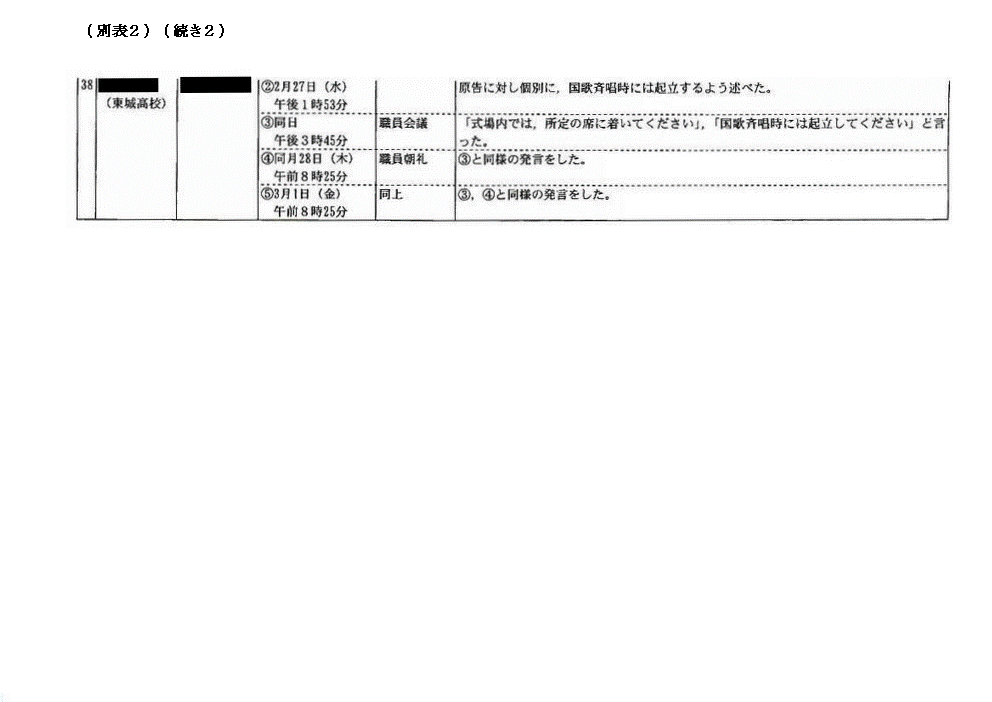 (別表3)
(別表3)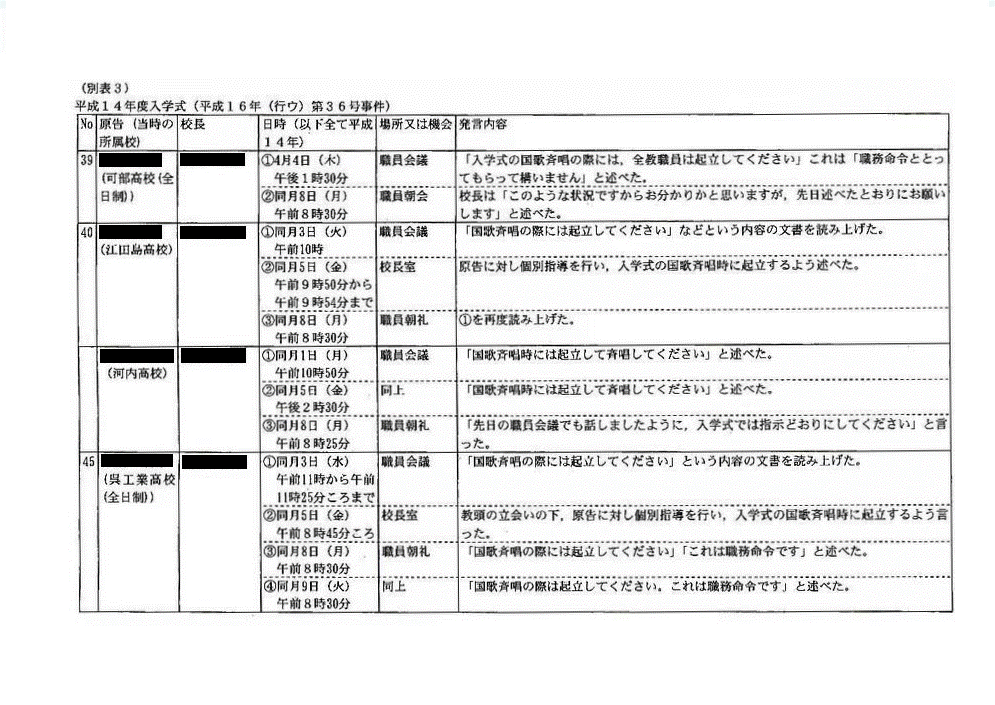 (別表4)
(別表4)