|
Home>
わたしの研究>
福祉資本主義│
環境経営史│
モダンダンス│
写真のアメリカ経営史
|
「安全第一」の経営史
生活様式としての「安全第一」
| ||
| 研究の経緯 | ||
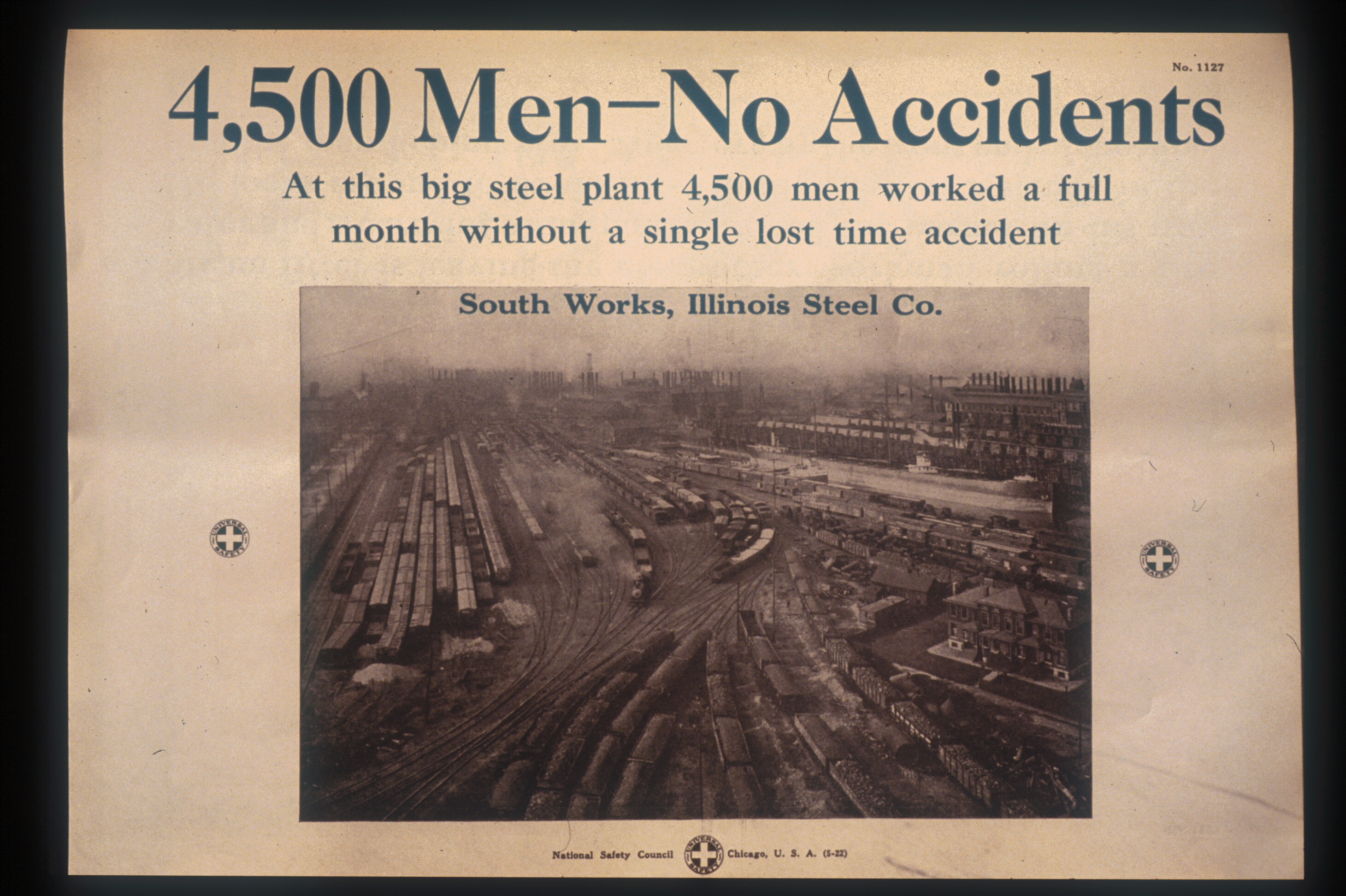
National Safety Council, poster
|
||
|
米国の安全運動(safety movement)のおおきな特徴のひとつは、この運動が「工場内ばかりか、路上、学校のなか、さらには家庭内へも入り込む」ようになり、社会運動の様相を呈することになったことである。わけても労働者家庭の婦人と子どもたちが重点的な保安教育の対象としてセイフティ・マン(安全管理者は当時このように呼ばれた)によって意識されていた。安全運動の指導者チャールズ・プライス(Charles W. Price)は、1919年12月1日付の『全国安全新聞』に筆を執り、「安全第一」の教えを人々の生活様式のなかに組み入れることの大切さを説いている。コミュニティや家庭の中で安全を心掛ける習慣を身につけることが、ゆくゆくは職場での安全な作業慣行の確立に結びつくという。この主張は、イリノイ製鋼(Illinois Steel Co.)やインタナショナル・ハーヴェスター社(International Harvester Co.)など、シカゴ地域の大手企業における実際経験に基づくものであった。シカゴのセイフティ・マンたちは、「安全第一」を家庭に持ち込むべく、地元の小学校やカソリック教会、YMCA(Young Men's Chiristian Association)や訪問看護婦協会など、企業外部の協力者を積極的に開拓した。なかでもシカゴ訪問看護婦協会(Visiting Nurse Association of Chicago)は企業の安全活動にきわめて協力的であり、南・東欧系の移民労働者とその家族に対して産業看護婦(industrial nurses)を派遣する新しいサーヴィスを組織している。
前稿の関連箇所をここで復唱しておく。「この時代の福利厚生活動を考察する際に、どうしても視野に入れておかなければならないことは、企業の福利をさまざまな非営利団体が外部から支えていたことである。19世紀末葉からの企業規模の飛躍的な拡大と移民の大量流入は、労働者福祉を専門に取り扱う非営利組織の活動をおおいに刺激し、企業もまた自己の福利活動をそのような専門家組織に依存する方向を辿り相互に密接な協力関係を築くこととなった。いうなれば私的福祉の営利部門(企業)と非営利部門との分業に基づく相互補完関係が進展したのである。「安全教育をいかに家庭へ持ち込むか」に苦慮していたセイフティ・マンも、「訪問看護婦」という企業外部の専門家をみいだし、このような私的福祉の部門間協力によって従来手薄となりがちであった産業衛生の領域に活動を組織することができた。」
引用文献
上野継義「革新主義期アメリカにおける安全運動と移民労働者──セイフティ・マンによる『安全の福音』伝道」『アメリカ研究』第31号(1997年3月): 19-40. 引用は23頁から。
|
||
| 学会報告 |
|
|
| Archives |
|
|
| 関連サイト | ||
Home> わたしの研究> 福祉資本主義│ 環境経営史│ モダンダンス│ 写真の経営史 |