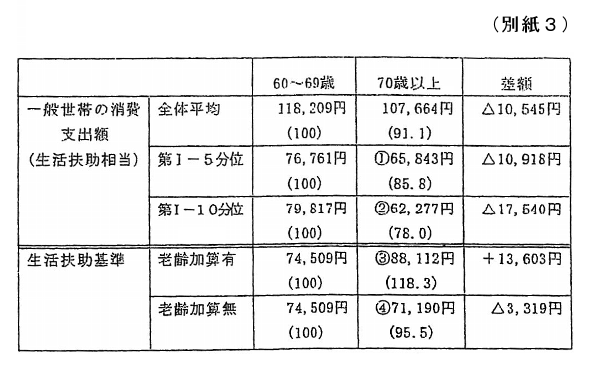各生活保護変更決定取消請求控訴事件
東京高等裁判所 平成20年(行コ)第265号
平成22年5月27日 第19民事部 判決
口頭弁論終結の日 平成22年2月9日
A事件控訴人 X1
B事件控訴人 X2
C事件控訴人 X3
D事件控訴人 X4
E事件控訴人 X5
F事件控訴人 X6
G事件控訴人 X7
H事件控訴人 A
I事件控訴人 X8
J事件控訴人 X9
K事件控訴人 X10
L事件控訴人 X11
上記12名訴訟代理人弁護士 新井章 田見高秀 渕上隆 西岡弘之 望月浩一郎 黒岩哲彦 小寺貴夫 吉村清人 水田敦士 佐藤誠一 佃俊彦 田島浩 鳥海準 柳沢尚武 坂本雅弥 中川勝之 牧戸美佳 北村将郎 高橋力 田所良平 林治 竹下義樹 吉田雄大 舟木浩 阪田健夫 西野大輔 大沢理尋 吉田維一 平田かおり 小川威亜 高木佳世子 田篭亮博
同訴訟復代理人弁護士 我妻正規 瀬川嘉章 今西雄介 縄田浩孝 松川邦之 堺啓輔 朝本孝一
| A事件被控訴人 東京都足立区 | 同代表者区長 近藤弥生 | 同処分行政庁 足立区北部福祉事務所長 |
| B・C事件被控訴人 東京都墨田区 | 同代表者区長 山崎昇 | 同処分行政庁 墨田区福祉事務所長 |
| D事件被控訴人 東京都大田区 | 同代表者区長 松原忠義 | 同処分行政庁 大田区福祉事務所長 |
| E事件被控訴人 東京都豊島区 | 同代表者区長 高野之夫 | 同処分行政庁 豊島区福祉事務所長 |
| F事件被控訴人 東京都新宿区 | 同代表者区長 中山弘子 | 同処分行政庁 新宿区福祉事務所長 |
| G・H事件被控訴人 青梅市 | 同代表者市長 竹内俊夫 | 同処分行政庁 青梅市福祉事務所長 |
| I事件被控訴人 調布市 | 同代表者市長 長友貴樹 | 同処分行政庁 調布市福祉事務所長 |
| J事件被控訴人 町田市 | 同代表者市長 石阪丈一 | 同処分行政庁 町田市福祉事務所長 |
| K事件被控訴人 東京都品川区 | 同代表者区長 濱野健 | 同処分行政庁 品川区福祉事務所長 |
| L事件被控訴人 東京都台東区 | 同代表者区長 吉住弘 | 同処分行政庁 台東区福祉事務所長 |
上記10名指定代理人 渡邊未来子 坂本隆一 吉澤敏雄 益子浩志 矢島千鶴
被控訴人足立区指定代理人 嶋靖記 三島圭太 遠藤立栄
被控訴人墨田区指定代理人 浮田康宏 後藤洋 國友誠 酒井敏春 福谷光広
被控訴人大田区指定代理人 池一彦 鎌田勝浩 鑓田明美
被控訴人豊島区指定代理人 鈴木正明 内田吉彦
被控訴人新宿区指定代理人 上原隆夫 佐賀聡
被控訴人青梅市指定代理人 横手良夫 増田博司
被控訴人調布市指定代理人 関口浩秀 石川広生 保田俊夫 福山武志 塚本栄 長谷部隆
被控訴人町田市指定代理人 秋山一弘 本多孝治
被控訴人品川区指定代理人 安藤尚之 岡田常也 朽木剛 赤坂樹彦
被控訴人台東区指定代理人 岡田和平 内田円 菊地武司 近藤裕二 福田健一
■ 主 文
■ 事 実 及び 理 由
1 原判決のうちH事件控訴人Aに関する部分を取り消す。
2 本件訴訟のうちH事件控訴人Aに関する部分は,平成21年12月7日,同控訴人の死亡により終了した。
3 その余の控訴人らの控訴をいずれも棄却する。
4 控訴費用は控訴人ら(H事件控訴人Aを除く。)の負担とする。
(1) 原判決を取り消す。
(2) A事件
足立区北部福祉事務所長がA事件控訴人X1に対して平成18年3月24日付けでした生活保護法25条2項による保護変更決定を取り消す。
(3) B事件
墨田区福祉事務所長がB事件控訴人X2に対して平成18年3月22日付けでした生活保護法25条2項による保護変更決定を取り消す。
(4) C事件
墨田区福祉事務所長がC事件控訴人X3に対して平成18年3月22日付けでした生活保護法25条2項による保護変更決定を取り消す。
(5) D事件
大田区福祉事務所長がD事件控訴人X4に対して平成18年3月28日付けでした生活保護法25条2項による保護変更決定を取り消す。
(6) E事件
豊島区福祉事務所長がE事件控訴人X5に対して平成18年3月10日付けでした生活保護法25条2項による保護変更決定を取り消す。
(7) F事件
新宿区福祉事務所長がF事件控訴人X6に対して平成18年3月28日付けでした生活保護法25条2項による保護変更決定を取り消す。
(8) G事件
青梅市福祉事務所長がG事件控訴人X7に対して平成18年3月20日付けでした生活保護法25条2項による保護変更決定を取り消す。
(9) H事件
青梅市福祉事務所長がH事件控訴人Aに対して平成18年3月13日付けでした生活保護法25条2項による保護変更決定を取り消す。
(10) I事件
調布市福祉事務所長がI事件控訴人X8に対して平成18年4月1日付けでした生活保護法25条2項による保護変更決定を取り消す。
(11) J事件
町田市福祉事務所長がJ事件控訴人X9に対して平成18年3月13日付けでした生活保護法25条2項による保護変更決定を取り消す。
(12) K事件
品川区福祉事務所長がK事件控訴人X10に対して平成18年3月13日付けでした生活保護法25条2項による保護変更決定を取り消す。
(13) L事件
台東区福祉事務所長がL事件控訴人X11に対して平成18年3月20日付けでした生活保護法25条2項による保護変更決定を取り消す。
主文同旨
[1] 厚生労働大臣の定める生活保護基準(以下「保護基準」という。)は,70歳以上の被保護者(以下では,「生活保護受給者」ともいう。)に対する加算(老齢加算)を定めていたが,平成16年度から保護基準が改定され,段階的な減額を経て,平成18年度から老齢加算が廃止されたため,控訴人らの住所地を所管する福祉事務所長は,生活保護法(以下「法」ともいう。)25条2項に基づき,控訴人らの同年度の老齢加算を3760円から0円に減額する旨の保護変更決定(以下「本件各決定」という。)をした。
[2] 本件は,控訴人らが被控訴人ら(本件各決定をした福祉事務所長を設置する区市)に対し,本件各決定は,保護の不利益変更禁止を定めた生活保護法56条及び生存権を定めた憲法25条に違反する違憲・違法なものであるなどと主張して,その取消しを求めた事案である。
[3] 原判決は,本件各決定は,いずれも適法であり,その取消しを求める控訴人らの請求は,いずれも理由がないとしてこれを棄却したため,控訴人らが原判決を不服として控訴した。
[4] なお,H事件控訴人Aは,原判決後の平成21年12月7日に死亡した。
[5]2 関係する生活保護法の定め及び前提事実は,原判決の「事実及び理由」欄の「第2 事案の概要」の1及び2(原判決3頁12行目から10頁16行目まで)に記載のとおりであるから,これを引用する。ただし,原判決9頁9行目,13行目及び16行目並びに10頁2行目及び4行目の各「3670円」をいずれも「3760円」と改める。
[6] 本件の争点は、(1)厚生労働大臣が保護基準を改定して老齢加算を廃止したこと,及びこれに基づいて各福祉事務所長が給付を減額した本件各決定を行ったことが,法56条に違反するか否か,(2)本件各決定が,「要保護者の年齢,性別,健康状態等その個人又は所帯の実際の必要の相違を考慮」せず,控訴人らの「健康で文化的な最低限度の生活」「健康で文化的な生活水準」の水準を切り下げ,これを下回る生活を強いるものであり,憲法25条,法1条,3条,9条,「経済的,社会的及び文化的権利に関する国際規約」(以下「社会権規約」という。)に違反するか否かであり,この点に関する当事者の主張は,以下のとおりである。
[7]ア 憲法25条があくまで国民の権利として生存権を保障していることからすれば,これを単なる政治的宣言(プログラム規定)であると解するのは相当でなく,少なくとも生存権はこれを具体化する立法を要請し,当該立法に具体化される抽象的権利であって,立法化された内容が具体的な権利内容として保障されると解すべきである。
[8] 憲法25条1項にいう「健康で文化的な最低限度の生活」という概念は,「一ヶ月当たり金何円で営む生活」という形で憲法上,一義的に定まるということは言えなくても,マーケットバスケット方式を初めとする理論生計費算定方式によって,その金額を具体的に算定することが可能なものであり,一定の幅を持った概念としては,憲法25条1項の解釈としても定まるものであって,生活保護法に基づく給付額が,この一定の幅からも逸脱して低いということになる場合には,生活保護法8条に違反するだけではなく,憲法25条に違反するということになるのである。そして,一定の幅があるといっても,理論的に我が国における現在の最低生活費を算出しようとする以上は,そこにそれほど大きな差異が生じるとは考えにくいのである。
[9]イ 生活保護法は,同法1条及び3条に示された同法の目的を制度の現実において達成するためには,最低生活の需要を満たすに十分なものとなる保護基準を明確に定めることが何よりも重要であり,保護基準をどう定めるかは制度の性格を決定する重大な問題であるという観点から,厚生労働大臣が保護の基準を定立する権限を有する根拠規定として,法8条を設けている。
[10] 法8条は2項からなり,1項は,「保護は,厚生労働大臣の定める基準により測定した要保護者の需要を基とし,そのうち,その者の金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度において行うものとする。」と,2項は,「前項の基準は,要保護者の年齢別,性別,世帯構成別,所在地域別その他保護の種類に応じて必要な事情を考慮した最低限度の生活の需要を満たすに十分なものであって,且つ,これをこえないものでなければならない。」と規定する。
[11] これは,厚生労働大臣に対して,最低生活の基礎となるべき生活資料を確定し,合理的な理論生計費算定方法を用いて,「要保護者の年齢別,性別,世帯構成別,所在地域別その他保護の種類に応じて必要な事情を考慮した」理論生計費を算定し,これに基づいて保護基準を定立すべきことを要請する規定である。最高裁昭和42年5月24日大法廷判決(民集21巻5号1043頁。以下「朝日訴訟最高裁判決」という。)の傍論(憲法25条,生活保護法8条の法解釈)における田中二郎少数意見も,
「生活保護法8条2項には,『前項の基準は,要保護者の年齢別,性別,世帯構成別,所在地域別その他保護の種類に応じて必要な事情を考慮した最低限度の生活の需要を満たすに十分なものであって,且つ,これをこえないものでなければならない。』と規定されているから,厚生大臣は,保護基準を設定するに当たり,合理的な理論生計費算定方法を採用するなど,右の要請に応ずるように努めなければならないし,また,理論生計費算定方式を採用するに当たっては,その基礎となるべき生活資料を確定しなければならない」と述べているところである。
[12] したがって,上記の要請に反する保護基準の設定,改定は,法8条に違反するものである。
ウ 厚生労働大臣による保護基準の改定と法56条の適用の有無
[13](ア) 法56条は,「被保護者は,正当な理由がなければ,既に決定された保護を,不利益に変更されることがない。」と定めているところ,この規定は,被保護者について既に決定された保護を不利益に変更する場合一般について,「正当な理由」が存在することを要求しているものである。生存権の保障の充実拡充の時期・程度について立法府・行政府に一定の裁量があるとしても,特定の施策がいったん実現した後に,これを廃止したり削減したりすることは,憲法25条に定められた人権が具体化し現実化されたものを制限することにほかならないから,合理的な理由,正当な理由がなければ許されるべきではないのであって,法56条の規定は,生活保護の実施機関が被保護者に対して保護変更決定をする場合のみならず,厚生労働大臣が保護基準を被保護者の不利益に改定する場合にも適用されると解すべきである。そのことは,法の規定の文言・趣旨に照らしても明らかである。
[14](イ) 仮に,法56条が,保護の実施機関と被保護者の間における関係について定めた規定であり,保護基準の改定について,法56条が直接的に適用されないとしても,同条が被保護者に対して,正当な理由がなければ,既に決定された保護を不利益に変更されることがないという地位を保障した以上,実施機関は,改定後も被保護者の最低限度の生活の需要が満たされていることの立証の責任を負うべきであり,結局のところ,その保護のよって立つべき基準が,当該需要を満たすものとして定立されたことの立証の責任を負うべきものであって,法56条は保護基準の定立行為についても間接的に適用(準用)されるべきである。
[15] すなわち,厚生労働大臣が保護基準を被保護者に不利益に改定することによって,保護実施機関が既に決定された保護を不利益に変更する場合には,保護の実施機関は,厚生労働大臣の定める保護基準に従っているというだけでは足りず,厚生労働大臣の行った保護基準の不利益変更自体に「正当な理由」があることをも立証しなければならないものである。
[16](ウ) たとえ保護基準の定立行為に法56条の適用・準用がないとしても,生活保護の被保護者は最低限度ぎりぎりの生活を送っているものであるから,これを不利益に変更する場合には,より慎重な態度で臨む必要があるという法56条の法意は,保護基準の定立行為における裁量権行使に当たって最も重視すべき要素であって,正当な理由,合理的な理由がなければ不利益変更を許さないというのは憲法上の要請でもあるから,これらを欠いた保護基準の不利益変更は裁量権の範囲を逸脱したものになるというべきである。
エ 保護基準の不利益変更における裁量権の範囲の逸脱又は濫用の有無の判断基準
[17](ア) 法56条の「正当な理由」の判断についての厚生労働大臣の裁量権と,法8条2項に基づく厚生労働大臣の保護基準の設定に関する裁量権は,以下のとおり,質的に異なるものであり,保護基準の不利益変更の適法性については,厚生労働大臣の裁量権に対する一般的な制約とは質的に異なる厳格な基準によって判断されなければならない。
[18] 保護基準の設定は,法8条2項の「要保護者の年齢別,性別,世帯構成別,所在地域別その他保護の種類に応じて必要な事情を考慮した最低限度の生活の需要を満たすに十分なものであって,且つ,これをこえない」との要件を満たすことを要するが,この要件自体が多分に価値的・抽象的な文言で表現されていて,解釈者側に解釈の余地を与えないほど一義的に明白な概念とはいえないから,保護基準の設定権限を与えられた厚生労働大臣が,具体的にいかなる内容・程度の生活を以て「健康で文化的な最低限度の生活」と解するか,そして,そのような生活を実現するのにどれ程の金員・物品・サービスを必要とするかを判断する際には,その判断の専門技術性から一定の裁量の余地が認められることは否定できない。これに対し,法56条は,「被保護者は,正当な理由がなければ,既に決定された保護を,不利益に変更されることがない。」と定めているところ,この「正当な理由」も確かに一義的に明白とはいえない概念ではあるが,その性質は規範的なものであって,不利益変更の理由が「正当な理由」に当たるか否かについては基本的に司法審査が及ぶべきものである。ただ,保護基準設定における専門技術性は,保護基準の改定についても存するから,裁量性を否定することまではできないだけである。
[19](イ) そして,上記のとおり,保護基準が,「要保護者の年齢別,性別,世帯構成別,所在地域別その他保護の種類に応じて必要な事情を考慮した最低限度の生活の需要を満たすに十分なものであって,且つ,これをこえない」(法8条2項)ものである以上,保護基準の不利益変更は,原則として許されないはずである。したがって,法56条にいう「正当な理由」があるといえるためには,(a)保護基準の切り下げを必要とするやむにやまれぬ事情があり(少なくとも,もともと定められていた保護基準自体が,最低限度の生活の需要を超える不当なものであることが判明した場合,社会経済情勢の変化によって最低限度の生活の需要が減った場合でなければならない。),(b)仮にそのような必要性が認められる場合にあっても切り下げが必要最小限度のものでなければならないというべきである。
[20] 上記(a),(b)の要件は,生活保護受給権の人権としての性格からも導くことができる。すなわち,憲法及び生活保護法の規定自体によって導かれる「健康で文化的な最低限度の生活」を営む権利は抽象的なものにすぎないとしても,厚生労働大臣が「要保護者の年齢別,性別,世帯構成別,所在地域別その他の保護の種類に応じて必要な事情を考慮して」定めた保護基準に基づいて生活保護を受給する権利は,憲法及び生活保護法によって導かれる「健康で文化的な最低限度の生活」を営む権利が具体化したものにほかならず,まさに生存権という人権が実体化したものであるから,その不利益変更は,具体的な人権の制限にほかならない。したがって,そこで要求される「正当な理由」は,個々の被保護者の生存に不可欠な権利の制約であるから,自由権の制約原理と同様に,(a)保護基準の切り下げを必要とするやむにやまれぬ事情と,(b)切り下げが必要最小限度のものであることの双方の要件を備えることが必要である(生存権の自由権的効果)。
[21](ウ) 加えて,最低限度の生活の需要を満たすに「十分なものであって,且つ,これをこえない」という最低限度ぎりぎりのところで定められた保護基準を不利益変更するということの性格からして,不利益変更後の保護基準によって法の要求する生活水準を満たすことが可能であるか否かの検証を経ていることが不可欠の要請というべきである。
[22] 本件に即していえば,老齢加算を含めた保護基準は,法8条2項に基づき,高齢の要保護者の特別の需要を考慮し,かつ,最低限度の生活の需要を満たすに「十分なものであって,且つ,これをこえない」という最低限度ぎりぎりのところで定められたものであることからすれば,老齢加算の減額・廃止について,法56条のいう「正当な理由」が認められるためには,(a)高齢者に老齢加算が想定していた特別需要が存在しないこと(高齢者とそれ以外の年齢層との支出費目ごとの比較を行い,高齢者の特別需要の存否について検証を行った上で,老齢加算創設時に認められた高齢者の特別需要が消滅したこと,あるいは,老齢加算創設時に認められた高齢者の特別需要は存続しているが,基準生活費が増額となったことにより,特別需要が基準生活費のみによりまかなえるようになり,基準生活費以外に加算を設ける必要がなくなったことのいずれかが確認されること),(b)老齢加算を除いた生活扶助基準で高齢者の生活の需要を満たすことが可能であることが,被保護者の生活実態に係る調査を踏まえて裏付けられていることが必要である。
[23](エ) 上記ウの(ウ)の考え方を採用するとしても,厚生労働大臣の裁量権の範囲の逸脱又は濫用の有無を判断する上で,法56条にいう「正当な理由」の存否を基礎付ける事情がそのまま重要な考慮要素になり得ると解すべきところ,法56条にいう「正当な理由」の存否を基礎付ける事情があるといえるためには,(a)保護基準の切り下げを必要とするやむにやまれぬ事情があり,かつ,(b)切り下げが必要最小限度のものであるという2つの要件が満たされなければならない。
[24](オ)a 生活扶助基準は,基準生活費と加算とに大別されるところ,基準生活費を構成する第1類費(個人的経費)及び第2類費(世帯共通的経費)については,標準生計費方式(昭和21年~22年),マーケット・バスケット方式(昭和23年~35年),エンゲル方式(昭和36年~39年),格差縮小方式(昭和40年~58年)を経て,現在では水準均衡方式(昭和59年~)がその改訂方式として採用されている。水準均衡方式では,昭和59年以来,相対的に一般国民の消費水準の60%台のところで生活保護世帯の消費水準を維持することが原則とされ,毎年,民間最終消費支出の伸びを基礎として改定率が設定されて生活扶助額が改定されてきた。そして,毎年の改定では,標準世帯(33歳男,29歳女,4歳子)の消費実態の第1類費と第2類費の構成割合を参考として,第1類費については年齢別の栄養所要量を参考とした指数で,第2類費については世帯人員別の消費支出を参考とした指数で,それぞれ展開されることとなっている。
[25] このように,基準生活費は,栄養所要量と世帯人員数によってその額が決定されるため,何らかのハンディキャップにより発生する需要,本件で対象となる高齢者についていうならば,加齢に伴う心身の状況の変化に対応するために必要な需要については全く配慮されていないのである。そして,基準生活費だけでは法8条2項にいう「その他保護の種類に応じて必要な事情を考慮」したことにはならないことから,それとは別途設けられたのが加算である。それと同時に法8条2項は,保護基準は「これ」(=「最低限度の生活の需要を満たすに十分なもの」)「をこえないものでなければならない」としていることから,加算を付加することによって「最低限度」の水準を超えてはならないのであり,加算は基準生活費と合わせて「最低限度」の水準を成すという関係にあるのである。
[26]b 以上のような,生活保護制度上の「加算」の位置付けに鑑みれば,基準生活費と加算とで,その減額・廃止等にあたって法56条で要求される正当性の程度,あるいは,厚生労働大臣に認められる裁量権の範囲に違いを設ける原判決の「二重の基準」論には,何ら根拠はないことは明らかであり,原判決は,生活保護法の解釈を誤ったものであるというべきである。したがって,本件老齢加算減額・廃止措置が適法であるためには,「本体ともいうべき基準生活費」の減額の場合と同程度以上の「正当な理由」が必要なのであり,これを欠く場合は法56条に反し違法である。
[27]ア 法56条は,保護の実施機関と被保護者との関係を規律し,「既に決定された保護」の保護の実施機関による変更が,法,更には,法8条により保護のよりどころと規定される厚生労働大臣が定めた保護基準の定める要件を充足したものでなければならないとの趣旨で設けられた規定であり,その「既に決定された保護」とは,法24条1項の規定により保護の決定通知書に記載されたすべての事項,すなわち,保護の種類,程度及び方法のすべてを含むものである。そして,同条にいう「正当な理由」とは,当該保護の改定が法や保護基準の定める保護の変更や停止又は廃止の要件に該当することをいうと解すべきである。
[28] 以上のように法56条は,被保護者の既得権の保護について規定したものであるといえるが,それは個別具体的な保護決定の変更は法や保護基準に適合していることが必要であるとの意味においてであって,適合対象である法そのものというべき保護基準の改定にまでそのような趣旨が及ぶものではないというべきである。
[29]イ また,厚生労働大臣が保護基準を定立する際の指針としては,確固とした成文の規定(法3条,8条2項)があり,しかも,これらの規定は,第1章「基本原理」及び第2章「保護の原則」の章に位置し,法全体の解釈に係る指針ともいうべきものである。他方,法56条は,第8章「被保護者の権利及び義務」という既に保護の決定を受けた個々の被保護者(法6条1項の「被保護者」の定義参照)を念頭に置いた章の中に置かれているのである。
[30] 以上からすると,保護基準の定立行為について,全く異なる趣旨から設けられた他章の条文を適用することは,合理性が認められないばかりか,法3条や8条2項には規定されていない条件を付け加えることになってしまい,本来の法の趣旨を正解しないものというべきである。
[31]ウ 本件各決定は既に決定された控訴人らに対する保護費を減額(変更)するものであり,そうである以上,法56条の不利益変更に当たり,同条の適用はある。
[32] なお,保護の実施機関である被控訴人らは,厚生労働大臣が定めた保護基準に拘束されるから,その改定に伴い保護の変更決定を行った場合,保護基準が改定された事実を主張・立証すれば,不利益変更を行う「正当な理由」の根拠としては十分であって,「正当な理由」のあることを争う当事者である控訴人らが,保護基準の改定に厚生労働大臣の裁量権の範囲の逸脱・濫用があることを主張・立証すべきである。
[33]ア 老齢加算は,昭和35年4月より,前年度に開始された老齢福祉年金を収入認定する代わりに,老齢福祉年金と同額を加算するものとして設けられたが,その後老齢福祉年金の額が大幅に増額・改善されて基礎的生活需要に対応するという性格が強められたため,老齢福祉年金の額とは切り離されて,昭和51年1月からは,別途生活扶助基準改定率により,昭和59年4月からは,基準生活費1類相当の消費者物価指数の伸び率により改定されている。
[34]イ 老齢加算額については,中央社会福祉審議会生活保護専門分科会の昭和55年12月の「生活保護専門分科会審議状況の中間的とりまとめ」において,
「老齢……の特別需要を算定するに当たって,福祉年金の趣旨・給付額・家計調査等から得られる消費実態,外国の加算制度の実態等を勘案して定めたものであり,その妥当性の根拠は現在も変わっていない。」「現在利用可能な資料を用いて特別需要額を推計してみると,現行の加算額は金額的にもそれぞれの特別需要にほぼ見合うものと考えられる。」との見解が示されている。
[35] また,中央社会福祉審議会の昭和58年12月23日付け「生活扶助基準及び加算のあり方について(意見具申)」において,低所得世帯の家計に関する各種の資料を基にして,加算対象世帯と一般世帯との消費構造を比較検討した結果,
「老齢……の特別需要としては,……おおむね現行の加算額で充たされているとの所見を得た。」とされている(乙7)。
[36] これらは,老齢加算の妥当性を裏付けていたものである。
ウ 老齢加算減額・廃止の考え方
(ア) 老齢加算額の検証
[37]a 「社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する法律」(平成12年法律第111号)の法案審議時の付帯決議(衆議院及び参議院),平成15年の社会保障審議会意見及び財政制度等審議会(以下「財政審」という。)建議において,社会福祉基礎構造改革を踏まえた今後の社会福祉の状況変化や規制緩和,地方分権の進展,介護保険の施行状況等を踏まえつつ,生活保護制度についても見直しの必要が指摘されていた。これを受けて,厚生労働省では,平成15年8月,生活保護制度全般について議論するため,厚生労働大臣の諮問に応じて社会保障に関する重要事項の調査審議を行う社会保障審議会の福祉部会内に,生活保護制度の在り方に関する専門委員会(以下「専門委員会」という。)を設置した。専門委員会では,老齢加算について,以下のような検証を行った。
[38]b 老齢加算は原則70歳以上の者に算定されるものであることから,平成11年の総務省全国消費実態調査結果を特別集計し,高齢者単身世帯の消費支出を所得階層別に集計して,単身無職の「60歳~69歳」と「70歳以上」の生活扶助相当消費支出額(消費支出額の全体から,生活保護制度において,生活扶助以外の扶助に該当するもの(家賃・地代,教育費,医療診療代等),生活保護制度において,基本的に是認されない支出に該当するもの(自動車関連経費),被保護世帯は免除されているもの(NHK受信料)及び最低生活費の範疇になじまないもの(家事使用人給料,仕送り金)を除外したもの)を比較(以下「比較(a)」という。)した資料により検討が行われた。
[39] その状況をみると,全世帯平均で60歳~69歳では11万8209円に対し70歳以上は10万7664円,第I-5分位(調査対象者を年間収入額順に並べ,対象者数を5等分した場合に年間収入額の最も低いグループのこと。対象者数を10等分した場合の年間収入額の最も低いグループは第I-10分位となる。つまり第I-10分位と第II-10分位を合わせたものが,第I-5分位となる。)で60歳から69歳までは7万6761円に対し70歳以上は6万5843円,第I-10分位では60歳から69歳では7万9817円に対し70歳以上は6万2277円となっており,いずれも60歳から69歳までの者より70歳以上の者の生活扶助相当支出額が低い状況となっている(乙9)。
[40]c また,第I-5分位の70歳以上の単身無職の者の生活扶助相当消費支出額と70歳以上の者の老齢加算を除いた生活扶助基準額との比較(以下「比較(b)」という。)をすると,第I-5分位の70歳以上の単身無職の者の生活扶助相当消費支出額が6万584円であるのに対し,70歳以上の者の生活扶助基準額(老齢加算を除く。)(平均)は7万1190円と,生活扶助基準額が高い状況となっている(乙9)。
[41](イ) 専門委員会では,上記(ア)の実態を踏まえて検討を行い,「平成15年中間取りまとめ」において,
「単身無職の一般低所得高齢者世帯の消費支出額について,70歳以上の者と60~69歳の者との間で比較すると,前者の消費支出額の方が少ないことが認められる。したがって,消費支出額全体でみた場合には,70歳以上の高齢者について,現行の老齢加算に相当するだけの特別需要があるとは認められないため,加算そのものについては廃止の方向で見直すべきである。」とし,との提言を行った。
「また,被保護者世帯の生活水準が急に低下することのないよう,激変緩和の措置を講じるべきである。」
[42] 厚生労働省においては,上記提言及び一般低所得高齢者世帯の消費実態を検証した結果,70歳以上の高齢者に老齢加算する特別な消費需要がないと認められること,老齢加算制度の合理性を基礎付けていた事情が現在ではほぼ失われていると解されることを踏まえ,老齢加算を廃止することとする一方,激変緩和の措置に関する提言がされたのを踏まえ,廃止に当たっては3年間をかけて段階的に廃止することとしたものである。
[43](ウ) このように老齢加算の段階的廃止は,一般低所得高齢者世帯の消費実態を検証した結果,70歳以上の高齢者に老齢加算に相当するだけの特別な消費需要がないことが認められたという国民の所得・生活水準の変化に伴う保護基準の改定であり、厚生労働大臣がその裁量の範囲内において実施したものである。
エ 老齢加算段階的廃止の妥当性
(ア) 保護基準の改善の推移
[44] 過去の保護基準の算定方式の推移を見ると,(a)最低生活を営むのに必要な飲食物費,衣食費,家具什器費,光熱費等の個々の需要の一つ一つを積み上げて理論計算するマーケット・バスケット方式,(b)標準的栄養所要量を満たす飲食物費を理論計算し,これと同等程度の飲食物費を支出している世帯のエンゲル係数で割り戻すことによって算定するエンゲル方式,(c)高度経済成長期の国民の生活水準の向上に合わせて保護基準の引き上げを図るため,政府経済見通しにおける民間最終消費支出の伸び率(見通し)に格差縮小分を加味して改定する格差縮小方式を経て,現在は,(d)政府経済見通しにおける民間最終消費支出の伸びに準拠して改定する水準均衡方式によって行われている。
[45] マーケット・バスケット方式から消費支出に準拠する方式へと変遷してきたのは,前者が品目及び数量の選定において恣意的にならざるを得ない側面があり,特に飲食物費を除く国民の消費の多様性に対応できないこと,高度経済成長に伴う国民の生活水準(消費)の向上に対応することが難しかったこと等が主な理由である。
[46] 現在,保護基準によって保護される生活水準を,一般世帯と被保護者世帯の消費支出を比較することによって示すと,一般世帯の消費支出を100としたときの被保護者の消費支出の割合(格差)は,昭和45年度には54.6パーセントであったものが,格差縮小方式により昭和58年度には66.4パーセントとなり,その後,水準均衡方式が採用されてからはおおむね7割弱で推移しており,平成13年度には71.9パーセント,平成14年度には73.0パーセントと,7割を超える水準に達している。
[47] 基準生活費が一般国民の消費実態との比較において十分な水準に達していることは,上記の事実のほか,平成8年から平成12年までの間の第I-10分位の勤労者3人世帯の消費水準に着目して,これと生活扶助基準額とを比較すると,(a)第I-10分位の消費水準よりも生活扶助基準額の方が高いこと,(b)食費,教養娯楽等の減少が顕著な第I・第II-50分位の消費水準よりも生活扶助基準額の方が高いこと,(c)第IIIないし第V-50分位の消費水準と勤労控除額(収入認定において就労に伴う必要経費を控除するものであり,控除額は就労収入によって異なる。平成8年から平成12年までの間の平均控除額は2万0599円である。)を除いた生活扶助基準額とは均衡が図られているが,勤労控除額を含めると生活扶助基準額の方が高いという事実などから明らかである。
(イ) 社会経済情勢の変化
a 賃金,消費者物価の変動
[48] 専門委員会では,昭和58年の中央社会福祉審議会意見具申で保護基準が妥当とされた以降の社会情勢の変化についても着目しており,第6回の委員会においては,当該期間中の生活扶助基準改定率,消費者物価指数,賃金及び基礎年金改定率の推移を比較した資料が提出され,検討が行われている(乙11の12,説明資料1頁)。これによれば,昭和59年度を100とした場合,平成14年度においては,生活扶助基準は135.5パーセントであるのに対し,消費者物価指数(暦年)は116.5パーセント,賃金は131.2パーセントであり,生活扶助基準の改定率が上回つていること,特に平成7年度を100とした場合には,生活扶助基準が104.3パーセントであるのに対し,消費者物価指数は99.9パーセント,賃金は98.7パーセントであり,物価,賃金ともにマイナスとなっていることが分かる。
b 消費構造の変化,エンゲル係数の低下
[49] また,専門委員会は,昭和55年と平成12年の消費支出の構成を10大費目別に検討している。これによると,一般勤労者世帯(全国,平均),一般勤労者世帯(全国,第I-10分位),被保護勤労者世帯(全国,平均)ともに消費支出に占める食料費の割合(エンゲル係数)が低下していることなどが分かる(乙11の6,説明資料9ないし14ページ)。
c 小括
[50] 以上のように,専門委員会は,昭和58年当時との比較を老齢加算廃止の直接の根拠とするものではないが,この間の社会情勢の変化に着目し,各種指標の推移について検討を行っているのである。
(ウ) 一般低所得高齢者世帯の消費実態
[51] 老齢加算額改定の考え方については,上記ウ(ア)で述べたところであるが,以下に補足する。
[52] 専門委員会においては,平成11年の総務省全国消費実態調査結果を特別集計し,高齢単身世帯の消費支出を所得階層別に集計して,「60歳~69歳」と,「70歳以上」の生活扶助相当消費支出額を比較した資料により検討が行われた(乙11の8説明資料10ないし13頁)。これを分かりやすくまとめたのが別紙3の表である。
[53] これによると,一般世帯の生活扶助相当消費支出額は,「全体平均」,「第I-5分位」,「第I-10分位」のいずれにおいても,70歳以上が60歳~69歳よりも1万円以上低いことが分かる。特に,第I-10分位においては,1万7540円の差がある。
[54] 他方,70歳以上の生活扶助基準額は8万8112円であり,60歳~69歳の生活扶助基準額よりも1万3603円高く,一般世帯の生活扶助相当消費支出額と比較すると,第I-5分位(6万5843円)及び第I-10分位(6万2277円)を大きく上回つている(別紙3の表中(3)と(1)及び(2)との比較)。
[55] さらに,老齢加算を除いた場合(7万1190円)でも,第I-5分位及び第I-10分位の生活扶助相当消費支出額よりも高いことが分かる(別紙3の表中(4)と(1)及び(2)との比較)。
[56] 以上のとおり,70歳以上の高齢者について,当時の老齢加算に相当するだけの需要がないことは明らかである。
オ 被保護高齢者世帯の消費実態
[57] 実際に被保護高齢単身世帯の家計消費の実態を,加算有世帯(主に70歳以上)と加算無世帯(主に60歳~69歳)で比較した場合,老齢加算は,必ずしも老齢加算が想定する需要を充たすためには費消されず,貯蓄等に回っていることが分かる(乙11の12,説明資料3及び4ページ)。すなわち,両世帯の貯蓄純増(「預貯金」と「保険掛金」の合計から「預貯金引出」と「保険取金」を差し引いたものである。)を比較してみると,加算無世帯では,実支出以外の支出のうち(a)貯金は8万8211円,(b)保険掛金は14円であり,実収入以外の収入のうち(c)貯金引出は7万8796円,(d)保険取金は22円であるところ,(a)貯金と(c)貯金引出の差額9415円と,(b)保険掛金と(d)保険取金の差額△8円を合わせた貯蓄純増((a)十(b)-(c)-(d))は9407円であり,可処分所得に占める割合(可処分所得に対する貯蓄純増の割合である平均貯蓄率)は8.4パーセントである。
[58] 他方,加算有世帯は,同様に計算すると貯蓄純増は1万4926円,可処分所得(「実収入」から税金,社会保険料などの「非消費支出」を差し引いた額で,いわゆる手取り収入のことである。これにより購買力の強さを測ることができる。)に占める割合(平均貯蓄率)は12.1パーセントとなっており,加算無世帯よりも5519円多い。
[59] また,翌月への繰越金(月末における世帯の手持ち現金残高である。)を見ると,加算無世帯が3万6094円,加算有世帯が4万7071円となっており,その差は1万0977円である。つまり,両世帯については,費消されずに翌月に繰り越される手持ち現金に,1万円以上の差があるということである。これと貯蓄純増の差5519円を合計すると,その差は1万6496円に上る。以上のように,被保護高齢者世帯の消費実態を見ると,老齢加算が,加算が想定する需要を充たすために消費されず,少なからず貯蓄等に回っていることが分かる。
[60]カ 以上のように,数次にわたる基準改定によって保護基準が引き上げられてきたこと,消費者物価の下落などの社会経済情勢の変化並びに一般低所得高齢者世帯及び被保護高齢者世帯の消費実態からみて,70歳以上の高齢者に当時の老齢加算に相当するだけの特別な需要があるとは認められないとする専門委員会の提言は妥当であり,それを受けて行った厚生労働大臣の判断に誤りはなく,裁量権の範囲の逸脱・濫用はない。
[61] 被控訴人らの主張は争う。本件においては,被控訴人らが主張する事情は,そもそも老齢加算の減額・廃止を必要とするやむにやまれぬ事情といえるようなものではない。また,老齢加算の減額・廃止が必要最小限度のものであるという主張・立証もない。
ア 老齢加算が創設され,存続してきた経緯
(ア) 老齢加算は単なる「みあい」加算ではない。
[62] 老齢加算は,昭和35年に創設されたが,これが老齢福祉年金制度が創設された際,老齢福祉年金の収入認定分を保障するため,老齢福祉年金と同額を加算して支給したことから,「みあい」加算と呼ばれてきた。
[63] しかし,老齢加算創設の必要性については,老齢福祉年金制度が創設される以前から,「生活保護本来の立場」から議論されていた。また,老齢加算の創設を担当していた厚生省の担当者(板山賢治)も,養老施設関係者から聞き取りを行い,加齢に伴う心身の状況の変化に対応するために必要な需要(高齢者の特別需要)にはどのようなものがあるかについて調査し,その聞き取りを基に特別需要を積算したところ,その金額は,老齢福祉年金と同じ月額1000円となった。このように,老齢加算は,生活保護本来の立場から創設されたものであり,また,その金額も調査に基づき高齢者の特別需要に見合ったものとされたのである(甲54・2~7頁,甲56)。
(イ) 創設時と比較した老齢加算の現代的意義
[64] 老齢加算の創設時と現代を比較した場合に考慮しなければならないのは,老齢加算の創設時は現代のように核家族化,高齢者の単身化は進んでおらず,高齢者の福祉的課題の多くは,家族によってカバーされていたことである。
[65] 現代においては,核家族化,高齢者の単身化が進んだ結果,高齢者の福祉的課題は,外部化された部分に依存しなければならない。すなわち,高齢者は,近隣や親族との関係を維持しながら安定した生活を送り,家族がカバーできない需要についてはサービスを購入して補う必要があって,高齢者の生活費は増加している。しかし,世帯人員が減少したからといってその分だけ世帯にかかる費用が比例して減少することにはならないのである。そして,高齢者,とりわけ単身高齢者が,基準生活費の設定に関して,不利な立場にある現状においては,老齢加算の意義は創設時より高まりこそすれ,低くなることはないのである。
(ウ) 老齢加算存続の経緯
[66] 老齢加算制度は,昭和51年に老齢福祉年金との関連から解き放たれ,昭和55年及び昭和58年の中央社会福祉協議会に設置された生活保護専門分科会における各検証により,高齢者の特別需要の存在と老齢加算の必要性が確認され(乙6,7),40年以上にわたって存続してきた。政府も,老齢加算の廃止前は,老齢加算が高齢の被保護者が健康で文化的な最低限度の生活水準を維持するために必要な制度であることを認めていたところである。
(エ) 昭和55年及び昭和58年の検証の合理性
[67] 中央社会福祉審議会生活保護専門分科会の「昭和55年中間取りまとめ」は,
被保護世帯の「消費支出の内容を詳細に分析すると,栄養摂取の態様については主食の比率が高いこと等未だ貧困性が強く認められ,さらに,地域社会の成員としてふさわしい生活を営むために不可欠な交通費,教養費,交際費等社会的経費は一般世帯のみならず全国勤労世帯第I-10分位階級等の世帯と比較しても著しいひらきがあることなどを勘案すると被保護世帯の消費支出の水準は今後さらに改善を要するものと認められる。」とした(乙6・3頁)。
[68] 一方,昭和58年意見具申は,
「現在の生活扶助基準は,一般国民の消費実態との均衡上ほぼ妥当な水準に達しているとの所見を得た。」と評価したものの,それは,一般世帯の7割弱の水準に達したということにすぎないのであり,一般世帯の7割弱でもってどのような生活が営めるかについては全く明らかにしていなかった。しかも,昭和58年意見具申は,上記評価に続けて,
「しかしながら,国民の生活水準は今後も向上することが見込まれるので,生活保護世帯及び低所得世帯の生活実態を常時把握しておくことはもちろんのこと,生活扶助基準の妥当性についての検証を定期的に行う必要がある。」として,今後も生活保護(扶助)基準には改善の余地があるとしているのであって(乙7・1~2頁),加算を除いた基準生活費のみによって特別需要も含めた高齢者の生活の需要を賄うことができる程度にまで基準生活費が改善されたという認識とはほど遠いものであった。
[69] したがって,老齢加算を除いた基準生活費のみによって特別需要も含めた高齢者の生活の需要を賄うことができるかについての検証を行うまでもないというのが当時の判断であったということができるのであり,かつ,その判断に不合理な点はない。
(オ) 「70歳以上」区分の創設による基準生活費の抑制と老齢加算の存続
[70] 政府は,その後も
「加算は特定の需要に対応するものであることから,その改訂に当たっては,生活扶助基準本体の場合とは異なった取扱いをする。」との立場をとり続けた。そして,平成元年には,第1類費について「70歳以上」との区分が新たに設けられたが,その理由として,当時の厚生省社会局保護課は,
「一般高齢者世帯の消費実態をみてみると,70歳以上の第1類費相当の消費支出額は69歳以下のそれと比較して低いこと,また,第1類基準設定の基礎となっている公衆衛生審議会の年齢別栄養所要量は,60歳代より70歳代の方が低いことが認められている。したがって,(中略)70歳以上の第1類費基準については,この改訂率を抑制し,年齢階級別に適正な水準の確保を図ったところである。」と説明し,老齢加算については,
「これら三加算(老齢・母子・障害加算)を含めた各種加算については,一般的な日常生活費の向上分以外の特別の需要に対応するものであり,従来から消費者物価動向を勘案し改訂を行ってきたところである。平成元年度においても,消費税導入の影響等も勘案し所要の改訂を行ったものである。」としていた(乙24・5頁)。
[71] このように,政府は,平成元年当時においても,70歳以上の第1類費相当の消費支出額は69歳以下のそれと比較して低いとの認識を持っていたことから,第1類費について,「70歳以上」の年齢区分を新たに設けて第1類費基準については改訂率を抑制して「適正な水準」の確保を図ったが,老齢加算については,「一般的な日常生活費の向上分以外の特別の需要に対応するもの」との認識のもと,その存続を当然の前提として,その改訂に当たっては,生活扶助基準本体の場合とは異なった取り扱いをしたのである。したがって,70歳以上の「生活扶助相当消費支出額」が60歳代のそれと比較して低いこと(比較(a))を根拠とする老齢加算の廃止は,政府のこれまでの対応と矛盾するものである。
イ 特別需要の存否及びその検証手法等の不当性(1)
[72] 高齢者における特別需要の存在が老齢加算が設けられた根拠とされており,老齢加算制度が昭和35年に老齢福祉年金制度の発足を契機として創設され,昭和51年に至って老齢福祉年金制度と切り離され,高齢者の特別需要を満たす基準として純化され,生活保護の特別基準として本来の性格を確立し,これまで生活保護の見直し等が実施された機会にも,高齢者の特別需要の存在とこれを理由とした老齢加算の必要性・妥当性が繰り返し確認されてきているところ,老齢加算廃止の措置に至る検証過程においては,消費支出の総額しか問題とされておらず,消費構造の比較検討,特に,昭和58年意見具申において行われた高齢者とそれ以外の年齢層との支出科目ごとの比較が行われていないため,従前の老齢加算制度の合理性を基礎付けていた事情,特別需要の存否についての検証は全く行われていないに等しい。以下に指摘するとおり,被控訴人らの特別需要の検証方法等は当を得たものではなく,特別需要が消滅したなどとする被控訴人らの主張は裏付けを欠くものである。
[73](ア) 専門委員会で使用された検討資料(平成11年の全国消費実態調査特別集計による消費支出額)(乙11の8)に基づいて,昭和58年意見具申と同様の手法により,60歳以上69歳以下の者と70歳以上の者との間の消費構造を比較検討すると,60歳以上69歳以下の者よりも70歳以上の者の方が高くなっている支出科目の合計額は,全国平均で9804円,第I-5分位で8180円,第I-10分位で1万3435円となっており,むしろ,特別需要が引き続き存在していることが裏付けられている。
[74] また,上記検討資料によれば,高齢者の特別需要の存在及び老齢加算の必要性・妥当性とともに,基準生活費についての妥当性も確認されており,その後も,水準均衡方式に従って改定が行われるなど,その評価に変動を来すべき事情も生じていないことからすれば,基準生活費の改定・引上げがあったとしても,それによって特別需要がカバーされることにはならない。
[75](イ) 老齢加算制度の必要性・合理性を検討するには,高齢者に具体的にどのような「需要」があるのか,その内容はどのようなものであり,その金額をどう考えるのかといった分析が不可欠であり,本件検討手法のような消費「支出」額を単純に比較しただけで,「需要」の有無を結論づけることは明確な誤りである。
[76] 消費支出と需要との間に「一定の相関関係」があることを否定するものではないが,高齢の保護利用世帯においては,需要が潜在化している点も十分に考慮されなければならず,また,単身高齢被保護者の生活に『ゆとり』分があったとしても,そのほとんどは,加齢に伴う特別需要や日常生活維持に備えた未実現の消費支出に過ぎず,こうした未実現の特別需要についても,なんらかの形で把握する必要があるのであって,「消費」支出額のみにより「需要」の有無を判断することには合理性がない。
[77](ウ) 保護基準以下の低所得者であっても実際には保護を受給していない者(いわゆる漏給層)がおり,各種調査の結果によれば,その数は膨大なものと推測され,これらの者を含んだ低所得者層の消費動向を参考にして保護基準を定めた場合には,本来の在るべき水準を下回った保護基準となって不合理な結果をもたらすことになる。
[78] 保護基準を定める場合に参照とされるべきは一般国民の生活水準であって,漏給層を除外せず,消費支出が圧縮されていると考えられる第I-5分位や第I-10分位のような低所得層を参照とするのは適切ではない。
[79](エ) 老齢加算の見直しの過程で,単身高齢者の消費水準を検証するに当たり,60歳以上69歳以下と70歳以上という年齢区分を用いて比較対照を行ったことには合理性がなく,70歳以上の高齢者に係る特別需要の不存在を根拠付けることもできない。
[80] この点,被控訴人らは,70歳以上の者と60歳~69歳の者とを比較する理由について,「老齢加算は原則70歳以上の者に算定されるものであることから」とする。
[81] しかし,もともと,高齢者に特有の生活の需要について考える際に,その対象を70歳以上の高齢者に限定すべき必然性などない。老齢加算の対象者が70歳以上の者となったのは,老齢加算制度の創設が70歳以上の高齢者を対象とする老齢福祉年金発足を契機としたという歴史的経緯に基づくものである。そして,1976(昭和51)年に老齢福祉年金との関連性が断ち切られて以降は,老齢加算の支給対象者を70歳以上の者に限定しなければならない理由はなくなったといえるのである。
[82] そして,実際,1975(昭和50)年9月15日の中央社会福祉審議会の分科会意見書でも,「65歳程度から傾斜的な加算の仕組みを検討すること」との提言が行われ(甲10の1・(参考4)),翌1976(昭和51)年から老齢加算の対象者は「70歳以上の者」の他に,65歳以上の重い障害ある者や68歳以上70歳未満の者であって,病弱等のため日常の起居動作に相当程度の障害がある者にまで拡大されている。このように,「60歳~69歳の者」には,老齢加算制度本来の趣旨からすれば,支給対象となるべき,あるいは,支給対象として検討されるべき者が含まれているのである。
[83] つまり「60歳~69歳の者」と「70歳以上の者」との比較は「同じ特性を持った方同士」の比較(乙11の11 10頁)ということができるのであり,このような両者を比較して高齢者の特別需要の有無・程度と老齢加算の要否を検討する手法には合理性がないのである。
[84] また,前記のとおり,昭和55年「中間的とりまとめ」及び昭和58年「意見具申」,それぞれに至る検討過程においても,60~69歳と70歳以上の者の比較により特別需要の有無及び程度を検証するという手法はとられていない。
[85] 例えば,「老夫婦世帯の収入・支出の内訳」(甲10の2)では,世帯主が「60~644歳」,「65~69歳」,「70歳以上」の各年齢層の世帯を「老夫婦世帯」と位置づけ,これら各世帯と,「一般世帯」との間で消費構造の比較検討を行っている。すなわち,ここでは,世帯主が70歳以上の世帯のみならず,「60~64歳」,「65~69歳」の世帯も高齢者の特別需要の有無及び程度を判断するに当たっての検討対象とされているのである。他方,「高齢単身世帯の生活扶助相当経費のうちの特別需要調べ」(甲11の1)では,「50歳代」,「60歳~64歳」,「65歳~69歳」,「70歳~74歳」,「75歳以上」の5つの年齢層に分けての比較検討が行われており,本件検証手法のように,「70歳以上の者」と「60歳~69歳の者」とに2分して,この2つの年齢層のみの比較検討により,老齢加算の要否を判断するといった粗雑な手法はとられていない。
[86] もっとも,60歳代について,その生活扶助基準が,高齢者に特有な生活の需要を含めて最低限度の生活の需要を満たしているということが検証されているならば,60歳代と70歳以上の比較により老齢加算の必要性の有無を検討することにも一定の合理性が認められる。しかし,そのような検証は全くなされていない。そうである以上,60歳代と70歳以上の比較のみにより,特別需要の有無・程度や老齢加算の必要性について検証することはできないのである。
[87](オ) 被控訴人らは,全国消費実態調査の特別集計から得られた数値を,高齢者の特別需要の不存在や老齢加算廃止の根拠となる基礎資料にしている。
[88] しかし,特別集計の基になったサンプルデータが公表されていないため,その信憑性・信頼性は何ら担保されていないこと,「生活扶助相当消費支出額」を比較する際に消費支出全体の中からどのような支出を控除し,その控除が妥当なものであったかどうかも検証できないこと,「平成11年全国消費実態調査・高齢者世帯結果表の第26表」(甲12)によれば,70歳以上74歳以下の単身無職世帯の月間消費支出額は,65歳以上69歳以下のそれを上回っており,厚生労働省(専門委員会の資料作成に当たった事務局)が「生活扶助相当消費支出額」を算定する過程で控除したであろう,住居費,保健医療費,自動車等関係費,仕送り金を控除して「消費支出の比較」を試みてみても,やはり70歳以上74歳以下の単身無職世帯の支出額が65歳以上69歳以下のそれを上回る結果となるなど,被控訴人らが高齢者の特別需要の不存在の根拠とした60歳以上69歳以下の者と70歳以上の者との比較(比較(a))と齟齬していることからすれば,被控訴人らが根拠とした検証資料は,データそれ自体の信用性に疑問があり、老齢加算廃止の合理的根拠にはなり得ないものである。
[89] また,厚生労働省が基礎データとして使用した平成11年全国消費実態調査の単身世帯に関する調査は,同年10月及び11月の2か月間のみを対象として実施されたものである。
[90] しかし,老齢加算は,生活扶助費の重要な一部として40年以上の間継続的に支給されてきたものであり,これを廃止して,保護受給者に不利益な保護基準の改定を行うのであれば,その検証は慎重に行われねばならないはずである。したがって,仮に,あるデータに基づいて検証を行った結果,高齢者の特別需要の存在が確認できないと判断される場合であっても,それが「一般的・継続的な傾向」のものであるといえるのかが更に問われねばならないのであり,経年変化や将来予測についての調査が不可欠である。したがって,平成11年全国消費実態調査それ自体の信頼性については措くとしても,それのみでは基礎データとして不十分であることは明らかである。
[91](カ) 70歳以上の高齢者については,他の年齢層と比較して,基準生活費のうち第1類費の伸びが著しく抑制されており,別途老齢加算の給付が行われていたからこそ,そのような抑制が可能であったと考えるべきところ,第1類費をそうした水準のままに据え置きながら,老齢加算を廃止することは,いわば二重に減額の負担を負わせることになり,著しく不利益であって合理性を欠いた措置である。
[92](キ) 財政審の建議並びに閣議決定された「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2003(骨太の方針2003)」及び「平成16年度予算編成の基本方針」において,社会保障費を抑制する一環として,老齢加算の廃止に向けた検討が明示され,専門委員会での議論が始まったが,老齢加算廃止の方針はそれ以前から決まっていたのであり,専門委員会での「検討」はその方針を正当化するためのものであって,合理性を検証する上で必要な検討が行われたものとはいい難い。
[93] また,専門委員会の「平成15年中間取りまとめ」では,老齢加算について「廃止の方向で見直すべきである」とされているが,同委員会では反対意見を述べる意見が多く,その意見を正しく集約したものとはいえない。専門委員会での実際の検討の過程では,老齢加算が廃止される場合にも,高齢者世帯の社会生活に必要な費用に配慮して,その代替措置の要否及び内容を含めて議論することが前提とされており,「平成15年中間取りまとめ」においてもこれを踏まえた修文を経ていたものである。
[94] こうした専門委員会の審議の過程等に照らしてみても,老齢加算を廃止したこと,特に代替措置なく廃止を実施したことは,正当な理由を欠き,合理的な根拠を欠くものというべきである。
ウ 特別需要の存否及びその検証手法等の不当性(2)(当審における主張)
[95](ア) 比較(a)及び(b)は,老齢加算の廃止の根拠となり得ないものである。
[96] 被控訴人らは,(a)60歳以上69歳以下の者と70歳以上の単身無職者のそれぞれ全体,第I-5分位及び第I-10分位の「生活扶助相当消費支出額」の比較(比較(a)),(b)70歳以上の単身無職者のうち第I-5分位の者の「生活扶助相当消費支出額」と老齢加算を除いた生活扶助基準額の平均との比較(比較(b))を老齢加算廃止の主要な根拠として主張しているが,以下のとおり,これらは,いずれも高齢加算廃止の根拠となり得ないものである。
a 「平成15年中間取りまとめ」における比較(a)の位置付け
[97] 比較(a)は,「平成15年中間取りまとめ」において,老齢加算を廃止の方向で見直すべき根拠とされている。
[98] しかし,「平成15年中間取りまとめ」は,これまで加算によって対応してきた高齢者の特別需要の存在を当然の前提とするものであり,「平成15年中間取りまとめ」が老齢加算に関して指摘しているのは,「消費支出全体でみた場合には」,特別需要があるとは認められないということにすぎず,また,「現行の老齢加算に相当するだけの」特別需要があるとは認められないとしているにすぎない。すなわち,「平成15年中間取りまとめ」は,老齢加算そのものについて廃止の方向で見直すべきとしているにすぎないのであり,これまで加算の形で支給されてきたものをすべて削減すべきであるとか,削減してもよいとはしていない。したがって,比較(a)は,老齢加算廃止の根拠となり得ない。
b 「平成15年中間取りまとめ」における比較(b)の位置付け
[99](a) 比較(b)については,専門委員会の資料とはされたが,「平成15年中間取りまとめ」では全く言及されていない。
[100](b) 専門委員会は,単身高齢者の生活扶助基準額(老齢加算を除いたもの)が第I-5分位の「生活扶助相当消費支出額」を上回っているからといって,これが老齢加算廃止の根拠となり得ると考えてはいなかった。
[101] むしろ,「平成15年中間取りまとめ」は,単身70歳以上の被保護者の生活扶助基準の妥当性に疑義を呈し,問題点を指摘している。すなわち,「平成15年中間取りまとめ」は,生活扶助基準について,標準3人世帯を基準として具体的な世帯類型別にこれを展開してみると,いくつかの問題点がみられるとして,被保護者世帯の約7割が単身世帯であること,単身世帯における第1類費と第2類費については一般世帯の消費実態からみて,これらを区分する実質的な意味が乏しいことも踏まえ,単身世帯については,一般低所得世帯との均衡を踏まえて別途の生活扶助基準を設定することについて検討することが望ましいと指摘していたものである。
[102](c) このため,「平成15年中間取りまとめ」は,老齢加算そのものについては「廃止の方向で見直すべき」としながら,
「ただし,高齢者世帯の社会生活に必要な費用に配慮して,生活保護基準の体系の中で高齢者世帯の最低生活基準が維持されるよう引き続き検討する必要がある。」として,老齢加算を廃止する場合には,保護基準の体系の見直しが必要である旨を提言しているのである。
[103] したがって,比較(b)を老齢加算廃止の根拠とするのは被控訴人ら独自の見解であり,比較(b)は,老齢加算廃止の根拠とはなり得ない。
[104](イ) 比較(a)及び(b)は,次のとおり不合理,不当なものであり,老齢加算廃止の根拠とはなり得ない。
a 比較(a)が,70歳以上の単身無職者の消費水準が,これと隣接する年齢区分の者(60歳以上69歳以下)のそれと比べて低いと評価することの問題点について
(a) 全国消費実態調査の結果
[105](aa) 別紙1の(1)表,(3)表,(5)表は,平成11年全国消費実態調査高齢者編第26表(甲12)の単身高齢の「無職世帯」の年間収入・消費支出を男女平均・男性・女性の3区分にまとめたものであり(以下の表も,同様の区分をしている。),(2)表,(4)表,(6)表は,平成16年全国消費実態調査高齢者編第27表(甲126)の同様の世帯の年間収入・消費支出をまとめたものである。
[106] また,別紙1の(7)表,(9)表,(11)表は,平成11年全国消費実態調査高齢者編第28表a(甲130の1)の単身高齢の「全世帯」の年間収入・消費支出をまとめたものであり,(8)表,(10)表,(12)表は,平成16年全国消費実態調査高齢者編第29表a(甲131の1)の同様の世帯の年間収入・消費支出をまとめたものである。
[107] さらに,別紙1の(13)表,(15)表,(17)表も,平成11年全国消費実態調査高齢者編第28表b(甲130の2)の単身高齢の「無職世帯」の年間収入・消費支出をまとめたものであり,(14)表,(16)表,(18)表は,平成16年全国消費実態調査高齢者編第29表b(甲131の2)の同様の世帯の年間収入・消費支出をまとめたものである(なお,甲130の2,甲131の2は,甲12,甲126と同年度の全国消費実態調査であるが,集計世帯数が異なっている。)。
[108](bb) 比較(a)は,60歳以上の高齢者の消費支出を60歳以上69歳以下と70歳以上に2区分して,両者を比較することにより,老齢加算廃止の根拠としたが,60歳以上の高齢者の消費支出を全国消費実態調査のとおり,60歳以上64歳以下,65歳以上69歳以下,70歳以上74歳以下及び75歳以上の4区分として,検討すると,別紙1のとおり,70歳を境として,消費支出は減少することはなく,むしろ,70歳以上74歳以下の消費支出が65歳以上69歳以下のそれを上回っているものが,全18表のうち(1)表,(3)表,(4)表,(7)表,(8)表,(9)表,(10)表,(12)表,(13)表,(14)表,(15)表,(16)表の12表もあり,男性についてはすべての表で上回っている。
(b) 比較(a)の統計上の誤謬について
[109] (a)(bb)のとおり,70歳を境として,消費支出が減少することはないのに,70歳以上の単身無職者の消費水準が60歳以上69歳以下のそれと比べて低いとした比較(a)には,次のような統計上の誤謬がある。
[110](aa) 誤謬の第1は,消費支出額が支出の原資となる所得(収入・貯蓄)の金額に制約されることを看過していることである。すなわち,年齢層ごとに所得(収入・貯蓄)が異なる場合,年齢層ごとの消費支出額が異なることは当然であり,消費支出額が異なる原因が年齢の相違にあるということはできないはずであるが,比較(a)は,これを無視している。
[111](bb) 誤謬の第2は,比較(a)が,ある年齢層の消費支出額(所得額)の分布と他の年齢層のこれが等しいか,同視し得ない限り,年齢層間の消費支出額が異なる原因が,年齢の相違にあるということはできないことを看過していることである。すなわち,70歳以上の年齢層が,60歳以上69歳以下の年齢層よりも所得の低い世帯を多く含むのであれば,60歳以上69歳以下の消費支出額が,70歳以上の消費支出額を上回るのは当然であり,実際にも,70歳以上の年齢層は60歳以上69歳以下の年齢層よりも所得の低い世帯を多く含むため,70歳以上の消費支出額が60歳以上69歳以下の消費支出額を下回る結果を招いているにすぎないが,比較(a)は,これを無視している。
[112](cc) 誤謬の第3は,平成11年という単年度の調査によって得られた「全世帯平均,第I-5分位及び第I-10分位において60歳以上69歳以下より70歳以上の者の「生活扶助相当消費支出額」が低い状況となっている」との一統計事実(比較(a))を不変のものとしていることである。別紙1のとおり,年齢層ごとの消費支出額は,それぞれの所得や所得分布の変動に伴って,当然に変動する。また,個人ごとにみても,(a)年齢のステージに沿った需要の相違は当然あるにしても,(b)同じ年齢に達した時代が何時であるかによる相違,(c)生まれ年によって異なる消費の在り方の相違(例えば,団塊の世代とそれ以前の世代の相違)があり,60歳以上69歳以下の消費支出と70歳以上の消費支出に固定的な大小関係があると認めることはできないはずであるが,比較(a)は,これを無視している。
b 比較(a)が統計上の消費支出額と異なる「生活扶助相当消費支出額」を設定して消費水準を比較することの問題点
[113] 厚生労働省は,総務省から,平成11年全国消費実態調査の調査票(個票データ)の提供を受けた上で,これを同調査の公表統計のように収支分類項目表に基づき,単純に集計するのではなく,厚生労働省が「生活扶助相当消費支出額」ではないとする個別の支出を「特別集計」では支出項目として計上することなく,このような集計・非集計の判断のフィルターをくぐった項目の合計額を「消費支出」,「食料」等と区分し,この「消費支出額」を「生活扶助相当消費支出額」と呼称して,年齢層ごとの消費水準を比較している。
[114] しかし,このように比較(a)が比較のものさしとした「生活扶助相当消費支出額」は,次のとおり,恣意的で不合理なものであり,比較(a)は,老齢加算の廃止を正当化する根拠にはなり得ない。
(a) 「教養娯楽」「その他消費支出」の不整合
[115] 別紙2は,平成11年全国消費実態調査26表(甲12)の単身無職世帯(60歳以上64歳以下,65歳以上69歳以下,70歳以上74歳以下及び75歳以上の4区分)を,比較(a)と同様,60歳以上69歳以下と70歳以上の2区分として,年齢・男女別の区分ごとの消費金額に,区分ごとの集計世帯数を乗じ,これを総世帯数数で割って加重平均を算出し,これを厚生労働省が比較(a)及び比較(b)の資料とした特別集計(乙11の8・14枚目)の「生活扶助相当消費支出額」と比較したものである。
[116] 別紙2では,60歳以上69歳以下の「教養娯楽」の加重平均が2万2337円であるのに対し,「生活扶助相当消費支出額」(生活扶助相当)は1万4772円であり,差額が7565円ある。また,「その他の消費支出」の加重平均が4万0756円であるのに対し,「生活扶助相当消費支出額」は,2万4189円であり,差額が1万6567円ある。
[117] この差額が発生した原因として考えられるのは,特別集計では,全国消費実態調査の金額から,一定の消費細目の金額が除外されている場合であるが,この場合,どのような支出をどのような根拠で除外したかを被控訴人らが主張・立証すべきであるのに,これがされていない。もう1つの原因として考えられるのは,全国消費実態調査の集計世帯と,特別集計の基礎とした集計世帯の範囲・数が異なっている場合であるが,集計範囲が異なったものになれば,集計結果の数値は当然異なってしまうことは統計のイロハであるから,特別集計の信頼性はないことになる。
(b) 「食料」の不整合について
[118] 別紙2の60歳以上69歳以下の「食料」の加重平均が3万5272円であるのに対し,「生活扶助相当消費支出額」は3万9180円であり,差額が3908円ある。このように加重平均の消費支出額よりも「生活扶助相当消費支出額」が多くなることは,全国消費実態調査の金額から,一定の消費細目の金額を除外することでは起こり得ず,また,調査票に記載されていない食料費を加算するということは,できないはずであるから,考えられるのは,集計世帯の範囲・数の相違のみである。被控訴人らは,この「食料」の差額が生じた原因を主張・立証すべきであるが,これをしていない。
(c) 「家具・家事用品」の不整合について
[119] 別紙2の「家具・家事用品」の加重平均と「生活扶助相当消費支出額」の差額は,60歳以上69歳以下で350円と僅差であるのに対し,70歳以上では2651円と大きな相違がある。
[120] その原因は,特別集計において,「生活扶助相当消費支出額」を算定する際,「最低生活費の範疇になじまないもの」として,「家事使用人給料」を除外したことによるものと考えられる。しかし,「家事使用人給料」は,家事の社会化の一環であり,現在は,金持ちだけが受けているサービスではない。家事(料理,後かたづけ,掃除,洗濯)は,高齢者(特に単身者)にとって,怪我や負傷のリスクを伴うため,この社会化されたサービスに対する需要は高齢になればなるほど強くなる。むしろ,現代では高齢者の特別需要として,社会的交流援助と並ぶ双璧とさえ言い得るものであり,需要の実態を何ら考慮することなく,一律に「家事使用人給料」を除外することは誤りである。
(d) 「交通・通信」の不整合について
[121] 被控訴人らは,「自動車関係費」は生活扶助からの支出が基本的に認められないから「交通・通信」から除外したとする。
[122] しかし,高齢者は,同時に障害者であることも少なくなく,また,高齢化率の高い山間へき地では通勤用に自動車の保有が認められているところ,山間へき地では高齢化率が高く70歳以上になっても働く人が少なくないなどの事情から,自動車の保有が認められる場合も少なくないと考えられる。また,平成20年生活保護関係全国係長会議(平成20年3月4日開催)においては自動車保有要件の大幅緩和がなされるなど,自動車保有の要件は流動的なものである。また,自家用自動車の保有をして外出行動の用にそれを供している場合,外出時に要する他の交通手段などに要する費用の支出はその分節約される。自動車を有しない被保護者は,自動車以外の有償の交通手段で外出の需要を充足しなければならないし,高齢の被保護者は徒歩以外の方法での交通手段を要することが肉体的衰えの状態からも必要なことが多いのであるから,「交通・通信」から「自動車関係費」を控除した残余があればそれだけで,生活の必要に応じた「交通・通信」の需要が満たされるとするのは疑問である。
c 比較(b)が,「生活扶助相当消費支出額」を低所得世帯の消費水準と比較したことの不合理性
[123] 現行の生活扶助基準の算定方式である水準均衡方式は,毎年度の政府経済見通しにより見込まれる民間最終消費支出の伸び率を基礎とし,前年度の同支出の実績等を勘案して必要な調整を行うもので,一般国民の消費水準との調整が課題であり,第I-5分位,第I-10分位という低所得層と比較して調整を図ることはされていない。また,このような低所得層の中には,要保護世帯でありながら,さまざまな事情から保護を受けず,被保護世帯以下の収入によって生活を維持している世帯も含まれている。昨今の格差社会のもとで,このような最底辺層の救済が社会問題化し,漏給層が広がっている現在,「生活扶助相当消費支出額」を低所得世帯の消費水準と比較していけば,保護基準が際限なく下がっていく危険がある。
[124] すなわち,70歳以上では,第I-10分位の消費水準は,第III-5分位の48%と5割を割っており,第I-5分位も54.8%と6割には満たないものである。そして,第I-10分位の「生活扶助相当消費支出額」は5万7553円,第I-5分位のそれが6万4838円であるのに対して,それぞれの生活扶助基準の平均額は,それぞれ6万9628円,6万9884円であり,いずれの「生活扶助相当消費支出額」も生活扶助基準を下回っているものである。
[125] このように比較(b)を根拠とした老齢加算の廃止は,第I-5分位,第I-10分位という低所得層の生活実態の検証を行わないまま,その生活に合わせて,保護基準を引き下げるというものであり,劣等処遇にほかならない。これは憲法及び生活保護法の趣旨・目的に反するものであり,およそ「正当な理由」は認められないというべきである。
エ 「平成15年中間取りまとめ」に基づく老齢加算の廃止の違法性(当審における主張)
(ア) 「平成15年中間取りまとめ」は,あくまで「中間」の報告書であること
[126] 専門委員会は,平成15年8月6日から平成16年12月16日までの間に合計18回の会合を開き,最終報告書を発表した。
[127] これに対し,「平成15年中間取りまとめ」は,平成15年12月15日に発表された,あくまで「中間」の報告書である。
[128] その後,最終報告書の発表を待つことなく,老齢加算の廃止が実施され,これが既成事実化されたため,最終報告書は,老齢加算について,「既に中間取りまとめにおいてその廃止の方向での見直しを提言したところであるが」と言及するにとどまったが,仮に,最終報告書発表の時点で,老齢加算の廃止が実施されていなければ,老齢加算について,「平成15年中間取りまとめ」とは異なった,又は「平成15年中間取りまとめ」での提言内容を前提としつつも,これに修正を加えた提言がされた可能性は否定できない。
(イ) 老齢加算の廃止は,「平成15年中間取りまとめ」の内容に反すること
[129]a 「平成15年中間取りまとめ」は,老齢加算そのものについては「廃止の方向で見直すべき」としながら,
「ただし,高齢者世帯の社会生活に必要な費用に配慮して,生活保護基準の体系の中で高齢者世帯の最低生活基準が維持されるよう引き続き検討する必要がある。」として,老齢加算を廃止する場合には,保護基準の体系の見直し(基準生活費の改善)が必要である旨を提言していることは,前記ウ(ア)b(c)のとおりである。
b 激変緩和措置について
[130] また,「平成15年中間取りまとめ」は,
「被保護世帯の生活水準が急に低下することがないよう,激変緩和の措置を講じるべきである。」としていたところ,専門委員会が厚生労働省の事務局と合意した激変緩和措置は,一時扶助など,何らかの形で高齢者の特別需要に応えるということであり,段階的な老齢加算の廃止は,これに当たらない。
[131] 老齢加算の廃止は,わずか3年間で単身高齢者の生活扶助費の約2割をカットするという極めて過酷なものであり,「激変緩和の措置」の名に値しないし,必要最小限度の不利益変更ということもできない。
[132]c 以上のとおり,専門委員会は,「平成15年中間取りまとめ」において,「加算そのもの」については「廃止の方向で見直すべき」としたが,あくまで保護基準の体系の見直し(基準生活費の改善)とセットで行われるべきであるとしていたのである。
[133] したがって,老齢加算の廃止は,「平成15年中間取りまとめ」の提言に従ったものではなく,政府・厚生労働省は,「平成15年中間取りまとめ」のうち,「(老齢)加算そのものについては廃止の方向で見直すべきである。」との一部の文言をつまみ食い的に取出して,老齢加算の廃止の根拠としているが,老齢加算の廃止は,「平成15年中間取りまとめ」の内容と整合せず,むしろ,これに反するものである。
(ウ) 厚生労働大臣の裁量権と「平成15年中間取りまとめ」の関係
[134] 厚生労働大臣が保護基準の設定について一定の裁量権を有するとしても,それは,この設定に当たって高度の専門技術的な考察が必要とされるからであり,この点を離れて自由な裁量が認められるものではないことはいうまでもない。そして,厚生労働大臣がその判断を行うにあたって,専門委員会にその審議を委ねた以上,厚生労働大臣は,その審議内容及び結果に絶対的に拘束されることはないとしても,これと矛盾,齟齬する措置を採る場合には,相応の合理的な根拠・理由が必要であるというべきであり,とりわけ,その措置が被保護者にとって不利益なものである場合には,法56条の趣旨からも,高度の合理性が要求されるというべきである。
[135] 厚生労働大臣が上記の根拠・理由なくした老齢加算の廃止は,その裁量権を逸脱・濫用したものであり,法56条の「正当な理由」を欠くというべきである。
オ もっぱら財政的な動機による保護基準の不利益変更と憲法25条等違反(当審における主張)
[136] 老齢加算の廃止は,平成15年当時の政府(小泉純一郎内閣)による予算削減目標の達成という,もっぱら財政的な動機によるものであって,仮にそれ以外の動機があったとしても,副次的ないし形式的なものにすぎず,専門委員会の「平成15年中間取りまとめ」や,厚生労働省が専門委員会に提出した資料(比較(a)及び(b)等)は,上記の動機を取り繕うための表面的な口実(カムフラージュ)にすぎない。
[137] ところで,憲法は,前文第2段で,「われらは,平和を維持し,専制と隷従,圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めている国際社会において,名誉ある地位を占めたいと思ふ。」と謳い,敗戦後のわが国が平和で民主的な福祉国家の建設を目標理念として進むべきことを高らかに宣明した。この新たな国家目標を支えるための中心規定が憲法9条であり,25条であることは言をまたないところである。したがって,国(政府)がその財政を運営する際にも,かような国家目標や理念に即して行われるべきことは当然の理であって,財政は,憲法の理念や原則にリードされ,コントロールされることはあっても,その逆であってはならない。
[138] 老齢加算の廃止は,これによって単身高齢の被保護世帯の生活にいかなる影響・ダメージがもたらされるかをはじめ,対象国民の生活や人権に対する配慮,ひいては憲法25条や生活保護法56条・8条等への顧慮が全く見られないものである。このように国の財政上の必要を絶対的に優先させ、対象国民の生活や人権への配慮を欠くか,劣後に置くような生活保護の行政措置が,すべての国民に「健康で文化的な最低限度の生活」を保障すべきことを国に義務づけている憲法25条の趣意に適合しないことは確かであり,さらに,保護基準の不利益変更を禁止する法56条の「正当な理由」の要件を充たすとはいえないこと,すべての貧窮者に「人間らしい生活」の最低限度を確保することを国に義務づけた法3条や8条等に違反することも多言を要しないところである。
[139] 以下に述べるとおり,老齢加算廃止後の生活扶助基準は,金澤教授が合理的根拠に基づいて算定した単身高齢の最低生計費に比してあまりにも低額過ぎるという点でも,また,控訴人ら70歳以上の被保護者の生活状況からも,「健康で文化的な最低限度の生活」の需要を満たすに十分なものとはいえず,法8条2項に違反し,同法1条,3条,9条及び憲法25条1項に反するものである。
ア 健康な生活及び文化的な生活の意義
(ア) 健康な生活とは
[140] WHO(世界保健機関)は,その憲章前文において,「健康」を「完全な肉体的,精神的及び社会的福祉の状態であり,単に疾病又は病弱の存在しないことではない。」と定義してきた(甲42の昭和26年官報掲載の訳)。このように「健康な生活」とは,単に肉体的な疾病または病弱が存在しないというだけにとどまらず,精神的にも活力ある状態が保持され,社会的にも社会内で孤立することなく他者との関係が保持されている生活をいうものである。
(イ) 文化的な生活とは
[141]「文化」とは,真理を求め,常に進歩・向上をはかる,人間の精神的活動あるいはそのような活動によって作り出されたものをいう。人間が文化的な生活を実現するに当たっては,新しい知識や教養を身につけるとともに,それを生かして社会に働きかけ,他者からの評価を受けるなどの活動が不可欠である。「生涯学習の進行のための施策の推進体制等の整備に関する法律(平成2年法律第71号)」の成立及びその後の生涯学習の広がりも,まさにそのような文化的な生活を実現するものといえる。
イ 現代日本における高齢者の「健康で文化的な最低限度の生活」
[142] このように,現代の日本の高齢者の多くは,肉体的な衰えという不安を抱えながら,家族や地域社会との関わりを維持し,地域グループの活動や余暇活動等を通じた社会参加を積極的に行っている。そして,多くの高齢者は,家族や知人を通した社会とのつながりを維持し,文化的な活動に関わっている。
[143] したがって,憲法25条及び生活保護法3条の「健康で文化的な最低限度の生活」においても,現代の日本において高齢者は,肉体的な健康は当然として,最低限度の家族や知人との付き合い,余暇活動,生涯学習等による自己実現や社会参加なしには,「健康で文化的な最低限度の生活」を実現することはできないものである。
ア 「最低生計費」の考え方
(ア) はじめに
[144] 金澤教授による「最低生計費」の研究と調査結果は,マーケット・バスケット方式によるものであるところ,金澤教授の「最低生計費」の算定方式は,以下に述べるとおり,厚生労働大臣が扶助基準の算定方式の1つとして採用するのに十分な合理性を有するものである。
(イ) 生活実態の検証の必要性
[145] 憲法25条1項の「健康で文化的な最低限度の生活」を具体化した生活保護法3条の「健康で文化的な生活水準」を更に具体化する際,単に低所得層と比較によって相対的に定めるだけでは,その収入によって「どういったことができるのか」,また「どういった状態になれるのか」といった「生活の質」(アマルティア・センの生活の「機能」という概念に相当するもの)は明らかにならず,その収入によってできる生活の質・内容を検証する必要がある。
[146] 特に,平成9年を起点として家計収入が低下し,格差と貧困が広がって,第I-5分位の低所得層の生活が苦しくなっている現状の下では,「健康で文化的な生活水準」を具体化して定めるには上記の生活の質を問う手法を用いる必要がある。とりわけ,老齢加算の廃止によって約2割近くの保護費が減額されるのであるから,仮に生活実態の調査をしないのであれば,しないことを補充する趣旨で,生活の質を問う手法である「最低生計費」との比較による検証が強く要請されるというべきである。
(ウ) 「生活の質」の絶対性(アマルティア・センの生活の「機能」)
[147] ここでいう「生活の質」とは,大別して2種のものに分けることができる。
[148] 第1は,「適切な栄養を得ているか」「雨露をしのぐことができるか」「避けられる病気にかかっていないか」「健康状態にあるか」といったいわば生命や健康の維持のための「生活の質」であり,第2は,「移動することができるか」「人前に出て恥をかかないでいられるか」「読み書きできるか」「自尊心を保つことができるか」「社会生活に参加しているか」といった社会的・文化的生活の維持のための「生活の質」である。
[149] こうした「生活の質」は,人間の生活にとって基本的で基底的なものであり,したがって,誰にとっても合意可能なものである。その内容は憲法25条1項の「健康で文化的な最低限度の生活」及び生活保護法3条の「健康で文化的な生活水準」をより具体的に示したものということができる。
[150] そして,これらの「生活の質」は,時代や社会が変化したとしても変わらない「絶対的」なものであり,個々人のさまざまな目的や価値,人生設計の中で,優先順位が高いものと位置づけられる。
[151] なお,これらの「生活の質」を達成するためには財やサービスが必要であるが,その財やサービスは,時代や社会とともに,産業の発展,社会制度の発展の中で変化する。その意味では「相対的」なものである。
(エ) 人間存在の多様性
[152] また,人間は多様な存在である。アマルティア・センは,生活の「機能」を達成するためには財やサービスが必要であるが,それを生活の「機能」に変換する変換率が個々人によって異なる場合が存在するとし,それを「人間存在の多様性」としている。
[153] 「健康で文化的な生活水準」とは,以上のような「生活の質」とそれを達成するための財やサービスに加え,「人間存在の多様性」に配慮したものでなければならない。
(オ) 価値の多様性
[154] 現代社会は,生活形態・生活様式が多様化しており,個々人の価値観も多様化している。特に,親族・友人との交際や地域社会への参加その他の社会活動を行うことや趣味その他の形態で様々の精神的・肉体的・文化的活動を行うことは人間性の発露としてすべての人に保障されなければならない。「生活の質」として挙げた「社会生活に参加しているか」という指標によって吟味されるものである。
[155] しかし,その具体的な内容は,価値観の多様性から個々人の選択に委ねられるものであるため,その保障のあり方は,そのための一定額の費用が認められることである。その費用を支出するための最低限度の所得が保障されなければ,個々人が自らの価値や目的を選択し実現することはできない。
(カ) 「最低限の生活水準」の客観的測定・把握の可能性
[156] 憲法25条1項の「健康で文化的な最低限度の生活」を具体化した生活保護法3条の「健康で文化的な生活水準」は,特定の国における特定の時点においては一応客観的に決定すべきものであり,またしうるものである。被保護者の需要の測定・把握は可能なことである。
[157] 金澤教授は,マーケット・バスケット方式を原則として採用した上で,現実の生活に即し,上記の「生活の質」を達成するための財やサービスとして,現在のわが国において,どのようなものが存在するかについて「持ち物財調査」を行い,また生活の仕方その様式を調べるために「生活実態調査」を行っている。この点では「相対論」をとるものである。
[158] 「持ち物財調査」によって,保有率が原則として7割を超えるものについては,「人前に出て恥をかかないでいられる」ために必要な生活財とする。
[159] なお,金澤教授が持ち物財について保有率を7割としたことは,今日の日本において原則として7割の人々が保有する持ち物については,誰でも保有していないと「人前で恥をかかないでいられ」ないなど,社会的合意がほぼ存在すると考えられるからである。
(キ) マーケット・バスケット方式の妥当性
[160] マーケット・バスケット方式は,現在,イギリスで採用されている方式であるというだけでなく,我が国においても昭和23年から昭和35年まで採用されていた方式であって,その後,他の方式が採用されているという理由だけで,その考え方が完全に放棄されていると理解するべきではない。すなわち,その後,エンゲル方式,格差縮小方式,そして現在の水準均衡方式に至るまで複数の算定方式が採用されてきているが,いずれもわが国の経済発展と,食生活が豊かになるなど一般世帯の生活水準の向上の中で,被保護世帯の生活水準との格差が拡大したため,一般世帯との格差の縮小を図るために採られてきたものであって,マーケット・バスケット方式は,それらの方式の基礎にあると理解すべきである。
[161] そして,現在の日本は,戦後の混乱期,その後の高度成長期,そして低成長期を経て,社会秩序がほぼ安定・固定化していることから,法3条の「健康で文化的な生活水準」に必要な財やサービスを選択しその費用を積算できる可能性,現実性が高まっており,マーケット・バスケット方式は,再び合理的な算定方式の1つとして,十分考慮に値する方式となっている。さらに,最低限度の「生活の質」を満たすためにどれだけの財やサービスが必要であるかを測るためには,必要な財やサービスを1つ1つ積み上げる方法が最も適しているし,またその当不当を判断しやすいのである。
[162] もっとも,マーケット・バスケット方式の欠点として,食費についてはカロリー計算や必要栄養を満たすような栄養学による一定の指標が存在するが,それ以外の費目については具体的な指標が存在しないという指摘がある。そこで,金澤教授は,現在の我が国における最低限度の「健康で文化的な生活水準」については一般世帯の7割の水準が相当であるとの社会的合意がほぼできていると考えられることから,現在の日本における社会制度,生活様式を前提として「持ち物財調査」,「生活実態調査」を行い,持ち物財について原則として7割基準を採用し,その「価格調査」を行なって,今日の日本の社会においての絶対的な最低限度の水準を算定しているのである。
(ク) 価格調査などについて
[163] 金澤教授は,後記イ(イ)の東京都練馬区における「最低生計費」の試算の際には,価格調査は,「最低価格」「標準(最頻度)価格」「最高価格」をそれぞれ調査し,外出着などは「人前に出て恥をかかないでいられるか」といった生活の質を満たすように標準価格を採用し,その他は最低価格を採用している。
イ 単身高齢世帯の「最低生計費」の算定結果
(ア) 京都市における試算
[164] 金澤教授による平成17年の京都市における調査を基に計算された75歳男子単身高齢者の税込月額「最低生計費」の算定額は,月額18万5061円である(甲18)。
[165] 生活保護受給世帯は,所得税・住民税のほか,社会保険料や医療費を負担しておらず,NHK受信料等も免除される。また,生活保護における住居費についても,基準内で実費が支給される。そこで,上記18万5061円から住居費,所得税・住民税,社会保険料及びNHK受信料等の各項目を控除し,「生活扶助相当消費支出額」を算出すると,予備費を含めて11万8112円となり,予備費を含めない場合でも10万3112円となる。つまり,算定された「最低生計費」は,予備費を含めない場合であっても,京都市及び東京都各区等(1級地―1)における老齢加算相当額を加えた生活扶助基準である9万3700円(平成19年度。平成15年度は9万3850円であった。)を上回る水準であり,逆にいうと,生活扶助基準は,老齢加算を加えた場合でもわずかにこの「最低生計費」に満たないものである。
[166] このように,老齢の被保護者は,老齢加算が満額受給されていた状態で,ようやく最低限度の生活が辛うじて保障されるか否かの瀬戸際だったのであって,老齢加算が廃止された現在では,「最低限度の生活」を大きく下回る生活を余儀なくされていることが明らかである。
(イ) 東京都練馬区における試算
[167] 金澤教授は,平成20年7月,東京都練馬区において,京都市におけると同様の方法で調査を行い,75歳女子単身高齢者世帯の「最低生計費」を算定した。
[168] その結果,練馬区における「最低生計費」の算定額は,税抜きで月額18万0990円,予備費を含めない場合には月額16万4990円,予備費を含めて税込みで月額20万6189円であった(甲88)。この「最低生計費」のうち,予備費(NHK受信料,健康保持用摂取品を除く。)を除いた保護基準相当額は月額10万5731円であった(住宅関連費を含めない。)。
[169] 一方,老齢加算が廃止された現在の単身高齢の被保護者の生活扶助基準額は,東京都練馬区の場合,月額で,1類費3万2340円,2類費4万3430円に加え,冬季加算と期末一時扶助費の月額平均額2469円を加算した月額7万8329円であった。なお,これに老齢加算の1万7930円を加えた場合には月額9万6259円となる。
[170] 現在の生活扶助基準額を金澤教授が算定した「最低生計費」と比較すると,現在の生活扶助基準額である月額7万8329円は,「最低生計費」より大幅に低く,また老齢加算を加えても,「最低生計費」より9472円低いものとなっているから,老齢加算廃止後の生活扶助基準額は,生活保護法3条の「健康で文化的な生活水準」を満たさない違法なものであり,憲法25条1項にも違反するものである。
[171] 前記(1)のとおり,「健康で文化的な最低限度の生活」とは,ただ生命を維持していければすむというものではないはずであり,心身ともに健康で,人生を楽しみ,自尊心を持って生きていくことが保障されて,はじめて「健康で文化的な最低限度の生活」といえるのである。
[172] しかし,70歳以上の高齢の被保護者の生活が老齢加算の廃止によって生命を維持していくことも危うい状態にまで追い込まれていることが,全日本民主医療機関連合会ソーシャルワーカー委員会の「生活保護受給者老齢加算廃止後の生活実態調査報告書」(以下「民医連調査報告」という。甲52)及び「生活保護受給者老齢加算廃止後の生活実態調査追加報告書」(以下「同追加報告」という。甲106)からも明らかとなっている。
[173] 老齢加算が廃止されたことによって,控訴人ら及びその他の70歳以上の被保護者は,生活保護法3条及び憲法25条の定める「健康で文化的な最低限度の生活」を下回る生活水準を強いられている。
ア 控訴人らの生活状況
(ア) 食生活の状況
[174] 控訴人らの食生活を「低栄養予防のための食生活指針」(甲95)に照らすと,「1 3食のバランスをよくとり,欠食は絶対さける」「2 動物性たんぱく質を十分に摂取する」「3 魚と肉の摂取は1:1程度の割合にする」「4 肉は,さまざまな種類を摂取し,偏らないようにする」「5 油脂類の摂取が不足しないように注意する」「6 牛乳は,毎日200ml以上飲むようにする」「7 野菜は,緑黄色野菜,根野菜など豊富な種類を毎日食べる。火を通して摂取量を確保する。」「10 酢,香辛料,香り野菜を十分に取り入れる。」「12 和食,中華,洋風とさまざまな料理を取り入れる。」「13 会食の機会を豊富につくる。」等,指針のほとんどに明らかに反している。
[175] 高齢者が健康を維持する上では,食生活の多彩な食品を摂取し,バランスのよい食事をすることが必要不可欠である。しかるに,控訴人らの食生活が品数も少なく,単調なものになっているだけでなく,控訴人らの代理人弁護士が平成21年3月に行った控訴人ら12人を含む35世帯計42人の70歳から86歳までの東京生活を守る会の会員の生活保護受給者を対象にしたアンケート調査結果(甲105)によっても,高齢生活保護受給者の内容が食品摂取の多様性を欠き劣悪な食事バランスに陥っていることが明らかとなっている。
[176] 70歳以上の被保護者は,健康を維持するための多様な食生活を送ることができない状況に追い込まれており,その原因は,バランスのとれた食事を摂取するだけの金銭的余裕がないことが決定的要因である。
(イ) 被服・履物
[177] 控訴人らは,被服費はほとんど支出しないとか,購入するのは下着や靴下だけ,履物も必需品であるが安いものを長く履き古して間に合わせている状況にあり,このような控訴人らの生活が,「健康で文化的な最低限度の生活水準」を下回ったものであることは明らかである。
(ウ) 電気製品・備品及び水道・光熱費など
[178] 控訴人らは,水道光熱費を厳しく切り詰め,その結果,入浴や冷暖房など経済的に制約を受ける生活を余儀なくされており,このような状態が,「健康で文化的な最低限度の生活水準を」大きく下回るものであることは明らかである。
(エ) 教養娯楽・社会的活動・交際など
[179] 控訴人らの親族や友人・知人との付き合いなど他人との交流は,明らかに不十分な水準にあり,「健康で文化的な最低限度の生活」とは到底いえないものである。
(オ) 高齢被保護者の健康について
[180] 高齢生活保護世帯の高齢者の健康状態は,一般世帯に比較して悪いことが指摘されているが,控訴人ら代理人によるアンケート調査によっても,控訴人らを含めた高齢生活保護世帯の健康状態が悪いことが明らかになった(甲105,3頁以下)。
[181] アンケート調査によれば,主観的健康感は著しく低く,うつの尺度を示す精神的健康度(GDS)指標の点数が高く(抑うつ症状があること),精神的健康度は低いことが示された。
[182] こうした控訴人らの健康状態は,「健康で文化的な最低限度の生活水準を」大きく下回るものである。
イ 控訴人らの困窮状態と老齢加算廃止による影響
[183](ア) 控訴人らの困窮は,老齢加算廃止によって深刻化したものであることは明らかである。
[184] 老齢加算1万7930円の廃止により,亡くなったH事件控訴人Aは,食費で約3000円,友達のとの付き合いを減らして約3000円,趣味の友人との旅行や写真を控えて約1万円,明かりや電気製品の使用を減らし,また風呂に入る回数を減らし,暖房をできるだけ使わないようにして光熱費を節約するなどして約500円~2000円を減額して対処していたが,他の控訴人らも同様であって,もともと豊かでない食費をさらに削り,被服費を極限まで減額し,光熱費をさらに削り,趣味や旅行などの教養・娯楽をあきらめ,冠婚葬祭の出席を取りやめ,同窓会などの交際を断念して対処している。
[185] もっとも,控訴人らがどの部分をどの程度減額しているか,逆に何に多くの支出をしているかについては,控訴人らによって異なっている。何に価値を見出しているか個々人によって異なるからであり,一律であることはあり得ない。その選択は,個々人に委ねられており,人間存在の多様性が表れている。しかし,どこかに人並みの支出をすれば,他の部分を厳しく切り詰める必要がある。
[186] 控訴人らは,限定された生活費をそれぞれに削れない部分に集中して使いながら,他のある部分をあきらめて生活している。そのあきらめている部分は小さなものではなく生活全体にわたる大きなものであるが,それは,全ての控訴人らが,そして控訴人らだけではなく多くの高齢被保護者が,食費を減額せざるを得なくなっている事実に現れている。食費をさらに削るのは他に切り詰められるものがなくなっているからであり,加算廃止の影響の深刻さの度合いを示しているのである(甲52,甲106,民医連調査報告書)。
(イ) 低所得者らの所得低下の影響
[187] 被控訴人らが,加算廃止の根拠とした比較(b),つまり比較の対象とされた低所得者層の生活においても控訴人らと同様の事態が生じている。
[188] 低所得者層において,所得が減少し,そのために可処分所得も減少し,その結果,消費支出が減少していく場合,その影響が全ての支出項目において等しく現れることはない。つまり支出がすべての支出項目で等分に減少することはなく,食費や被服費といった費目は支出を削りにくく,他方で衣服,娯楽や趣味,交際費を大きく削ることで,可処分所得の減少に対応している(甲33)。
[189] ぎりぎりの生活をしている低所得者の場合,それでも消費支出を削らなければならない場合には,削りやすいものから削っていくしかない。消費支出の減少を余儀なくされると,嫌であっても,生きていくためには減少に適応するするしかない。ここで生じている事態は,人間らしい生活の質を落としながら削りやすいものから削っているのである。
[190] 特に人との交流は,人が人間としてあり続けるために不可欠なことであるが,そのためにかかる費用を出せずに人との交わり自体を縮小し断念していくことは,人間らしい生活の質が劣化することに他ならない。
[191] 人は他者と交流し,互いに影響しあって初めて人間らしく生きる条件が確保できるものである。人は他者と交流の中で視野や世界が広まり,また人間らしい心が生まれ,人間らしい精神生活ができるようになる。それは,食生活と同じく,日々,必要なことであって,人との交わりが狭くなったり途絶えたりすれば,身体の活力も気力も維持が困難となっていく。高齢者ほどその必要が高いのである。
[192] 極限まで交際費を削っていくことは,人間らしく生きるための条件を削っていくことに他ならない。その極限では,外出を控え,世界を狭くして,閉じこもり状態に追い詰められていくことになる。交際費の極度の圧縮は「健康で文化的な最低限度の生活」を下回る生活水準を強いるものである。
[193](ウ) 老齢加算が完全に廃止されて丸4年が経過し,その間控訴人らを含めて,現に,老齢加算の対象だった高齢者らの生活がなんとか続いてきたという事実自体を,「最低限度の生活」が保持されているとの根拠とすべきではない。人は,どのような事態になっても,自ら生を放棄しないで生き続ける以上,直ちに生活自体ができなくなるわけではない。極端に言えば,どんな状況にあっても人は生きるために最大限の工夫,努力をして生き続けるものであり,同様に,「健康で文化的な最低限度」以下の生活を余儀なくされても,誇りをもって生き続けるものである。しかし,貧困は,辛く苦しいものである。その辛さや苦しさを,日々,余儀なくされている状態は,およそ人間的な生活とは言えない。少なくとも現代の民主的で「豊かな」社会の中に,一方で辛く苦しい貧困が存在することは,容認されることではないはずである。
[194] 控訴人らの困窮は,老齢加算廃止によって深刻化したものであることは明らかであり,その現在の生活状況は,「健康で文化的な最低限度の生活」の水準を下回っているものである。
[195](1) 保護基準は法8条2項所定の事項を遵守したものであることを要し,憲法の定める健康で文化的な最低限度の生活を維持するに足りるものでなければならないが,何が健康で文化的な最低限度の生活であるかの認定判断(保護基準の設定)は,厚生労働大臣の合目的的裁量にゆだねられており,裁量権の範囲の逸脱又は濫用がない限り,違法とされることはない。厚生労働大臣が本件各決定に適用される保護基準を改定したことについて何ら裁量権の範囲の逸脱,濫用も認められないことは,既に述べたところから明らかであり、その保護基準に基づき行われた本件各決定も適法なものであって,憲法25条に違反しないことはもとより,法1条,3条又は9条に違反するものではない。
[196](2) 単身高齢世帯の最低生計費についての控訴人らの主張は,以下のとおり妥当性を欠くものである。
ア 生活実態調査及び持ち物財調査の問題点
[197] 金澤教授らは,京都地方労働組合総評議会(以下「京都総評」という。)と京都生活と健康を守る会の協力を得て実施した生活実態調査及び持ち物財調査を基にマーケット・バスケット方式による最低生計費を算定したとしている。しかしながら,これらの調査の目的は,賃金引上げの要求や最低年金の要求などの,社会保障要求の基礎資料を得ることであり(金澤証人調書16頁6ないし8行目),その目的を,調査対象者である京都総評傘下の労働組合の組合員,京都生活と健康を守る会会員,年金者組合の組合員等の協力者の会員に伝えた上で実施されているものである(甲18の24頁,金澤証人調書17頁6ないし9行目,乙42の125,127頁)。生活と健康を守る会は,社会保障を充実させる運動に取り組んでいる団体であり(金澤証人調書17頁3ないし5行目),年金者組合はそのホームページによれば「最低保障年金制度」を要求することを目的とする団体である(乙43)。
[198] こうした一定の組織目的に沿つて活動する団体の構成員を対象として実施した調査は,無作為抽出の調査と比べて抽出した客体に偏りがあることから,京都市又は全国の高齢者を母集団としたときに,その結果をもつて,高齢者全体を代表しているというには問題があるといわざるを得ない。
イ 計算過程における恣意性
[199] 最低生計費は,マーケット・バスケット方式であるため,その計算過程に恣意的な要素が入りやすい。以下具体的に問題点を挙げる。
(ア) 購入量
[200] 購入量について,持ち物財調査の結果から原則として保有率7割以上のものを算定しているとのことであるが,上記のとおり,持ち物財調査は一部の集団に対する調査であることから,これをもって京都市又は全国の高齢者の生活実態を表しているというには客観性に問題がある。
(イ) 価格設定
[201] 金澤教授らは,生活実態調査に基づいて安価な量販店又は大規模店で購入することを想定して価格を設定したとしている(甲33の26頁,金澤証人調書23頁22ないし26行目)。しかし,量販店・大規模店であれば同種商品が1種類ということはなく(金澤証人調書23頁18行目),大規模店だけに品ぞろいは豊富であると推測され,同種商品といえども価格には幅があると考えられる。ここで,同種商品のうち,最低価格を採るか,平均価格を採るかで,最低生計費の結果が異なってくるのは明らかである。この点,金澤教授は,「最低でも中間くらいを採つた」と供述するところ(金澤証人調書24頁3行目),最低生計費を算定する上で,なぜ,中間以上の価格帯を選択するのかについて,何ら合理的な説明をしておらず,この供述からは,大型の量販店ではあるが最低価格ではなく,中間以上の価格帯から恣意的に価格設定したことが認められる。したがって,このように算定された最低生計費が,最低生活費としてふさわしいかどうかは疑義があるといわざるを得ない。
(ウ) 耐用年数
[202] 耐用年数は,それをどのように設定するかで最低生計費の額が大きく変わる重要な要素である。この点について,金澤教授は,伝統的に昔から旧総評が計算に用いているものや連合が計算に用いているものを参考とした(金澤証人調書24頁4ないし11行目)とするのみであり,第三者が客観性を確認できないものである。そもそも,伝統的に旧総評が計算に用いているものとは,旧総評が賃金引き上げ要求や社会保障の要求のために算定したいわゆる旧総評理論生計費にほかならない。そして,最高裁判所は,いわゆる総評サラリーマン税金訴訟の上告審判決において,旧総評理論生計費を,
「日本労働組合総評議会(総評)にとつての望ましい生活水準ないしは将来の達成目標にほかならず,これをもつて『健康で文化的な最低限度の生活』を維持するための生計費の基準とすることができないことは原判決の判示するところであ」ると判示している(最高裁平成元年2月7日第二小法廷判決・訟務月報35巻6号109頁)。そして,旧総評と同じ耐用年数を参考にしている金澤教授らの京都総評最低生計費試算プロジェクトの最低生計費も,最低生活費ではなく,望ましい生活費の水準であると推認される。
(エ) 交際費及びこづかい
[203] 金澤教授の最低生計費の試算では,交際費の価格設定が高く,また,こづかいが二重計上されている可能性がある。このほかにも,上記プロジェクトにおいては,望ましい支出,金額を追加するとの金澤教授らの意図から,礼服など,実際の生活実態調査の結果いかんにかかわらず算入されているものがある。
ウ 結果としての最低生計費の水準の高さ
[204] このような計算過程を経て算定された最低生計費は,全国でそれ以下の消費生活をしている世帯の割合が,65歳以上の高齢単身世帯で87.1パーセント,65歳以上の夫婦のみ世帯で52.1パーセント存在するという高い水準のものであった(甲18の66ページ)。
[205] 国民の圧倒的多数がその水準以下となる試算結果に対して疑問を持たなかったかどうかとの被控訴人ら指定代理人からの質問に対し,金澤教授は,その最低生計費が国民生活の実態から乖離している可能性について疑問を持たず,むしろ
最低生計費以下の国民が「それだけいるということを社会的にアピールし,公表することというのは,その存在をなくするという強い意思がそこに働いていると思いますので,そういうことは大切なことじゃないでしょうか。」と供述している(金澤証人調書26頁13行目ないし27頁1行目)。しかし,最低生活保障水準は,一般国民の生活水準との比較において相対的に定められるべきところ,このような国民の圧倒的多数がその水準以下となる最低生計費は,一般国民の生活実態から遊離している試算といわざるを得ず,到底最低生活保障水準の基礎とはなり得ないものである。
エ まとめ
[206] 金澤教授は,老齢加算廃止前の生活保護水準も不十分であるとの認識のもとに(金澤証人調書19頁8ないし13行目),金澤教授及び京都総評最低生計費試算プロジエクトにとって望ましい,あるいは将来の達成目標としての最低生計費を算定したにすぎない。したがって,一般国民の生活水準との比較において定める相対的最低生活水準の考え方に立って設定されるべき最低生活費の基準とは到底なり得ないものであるから,これを前提にする控訴人らの主張は失当である。
[207](3) 控訴人らの生活実態が「健康で文化的な最低限度の生活」を下回っているとの控訴人らの主張は,以下のとおり,理由がない。
[208] 控訴人らは,本人尋問や陳述書において,老齢加算の段階的廃止前に維持していた生活水準と現在の生活水準とを比較して,専ら,老齢加算の廃止によってそれがいかに低下したかについてるる主張する。しかし,控訴人らは,老齢加算廃止後の生活保護基準が健康で文化的な最低限度の生活を維持できない水準であることを主張立証すべきところ,本人尋問によって明らかになったことは,控訴人らはいずれも,そのような生活実態になく,むしろ,老齢加算廃止後も社会生活を損なうことなく一定の生活水準を維持できているということであった。
[209] すなわち,控訴人らは,いかに日常生活において加齢に伴う特別需要があるかについて主張するが,生活保護には,生活扶助以外にも,特別需要にきめ細かく対応するため各種扶助があり,また,一時扶助や特別基準が設けられているところ,控訴人らが挙げる特別需要は,他の扶助や一時扶助で対応できるもの(医療費,介護費,おむつ代,眼鏡代,葬儀費用,葬儀へ参列するための交通費,医療機関への通院又は往診のための交通費)か,個人の自由な意思によるもの(香典等)であった。このように,老齢加算廃止後の生活扶助基準が,最低限度の生活の需要を満たすのに不十分である事実は認められない。
[210] したがって,厚生労働大臣に裁量権の逸脱・濫用にあたる違法がなかつたことは明らかというべきである。
[211] 社会権規約は,(a)社会保障,(b)相当な生活水準及び生活条件の改善,(c)文化的な生活への参加等に係るすべての者の権利を認めており(9条,11条1項,15条1項),その具体的措置を規定した生活保護法の上位規範として位置付けられるべきであって,生活保護法の解釈は社会権規約の解釈に従ったものでなければならない。そして,社会権規約の解釈基準となる,国連社会権規約委員会の定めた一般的意見(甲51の1・2)は,締約国に対し,(d)高齢者の権利の尊重から要求される限りにおいて,利用可能な資源を最大限に用いて,特別の措置をとることを要求し(一般的意見第6・平成7年(1995年)),(e)景気後退及び経済の再調整の時期には,高齢者が特に危機にさらされるとして,社会の弱い構成員を保護する義務を負わせ(一般的意見第3・平成2年(1990年)),(f)意図的に後退的措置がとられる場合には,すべての選択肢を最大限に慎重に検討した後に導入し,利用可能な最大限の資源の完全な利用という文脈において,規約に規定された権利全体との関連でそれが正当化されることを証明する責任を負わせている(一般的意見第14・平成12年(2000年))ところ,老齢加算の減額・廃止に係る保護基準の改定は,以上のような一般的意見に反するものであって,社会権規約の趣旨に反し,法8条に違反する。
[212] 社会権規約9条は,「この規約の締約国は,社会保険その他の社会保障についてのすべての者の権利を認める。」と規定し,同11条1項前段は,「この規約の締約国は,自己及びその家族のための相当な食糧,衣類及び住居を内容とする相当な生活水準についての並びに生活条件の不断の改善についてのすべての者の権利を認める。」と規定し,同15条1項は,「この規約の締約国は,すべての者の次の権利を認める。(a)文化的な生活に参加する権利,(b)科学の進歩及びその利用による利益を享受する権利,(c)自己の科学的,文学的又は芸術的作品より生ずる精神的及び物質的利益が保護されることを享受する権利」と規定しているが,これらは,締約国において,社会保障についての権利その他各条項所定の権利が,国の社会政策により保護されるに値するものであることを確認し,上記権利の実現に向けて積極的に社会保障政策を推進すべき政治的責任を負うことを宣明したものであって,個人に対し即時に具体的権利を付与すべきことを定めたものではない。このことは,同規約2条1項が,締約国において「立法措置その他のすべての適当な方法によりこの規約において認められる権利の完全な実現を漸進的に達成する」ことを求めていることからも明らかである。
[213] そうすると,社会権規約9条,11条1項前段及び15条1項は,いずれも,個人に対し即時に具体的権利を付与すべきことを定めたものではないのであって,老齢加算廃止に係る保護基準の改定がこれらの規定に違反するとの控訴人らの主張は,失当である。
[214] 当裁判所も,本件各決定は,いずれも適法であり,その取消しを求める控訴人ら(H事件控訴人Aを除く。)の請求は,いずれも理由がないので棄却すべきであり,本件訴訟のうちH事件控訴人Aに関する部分は,同控訴人の死亡により終了したものと判断する。その理由は,以下のとおりである。
[215]1 老齢加算導入の経緯及びその後の推移,この間の生活保護制度の動向,老齢加算廃止に至る経緯は,次のとおり補正するほか,原判決の「事実及び理由」欄の「第3 争点に対する判断」の1(原判決11頁3行目から21頁19行目まで)に記載のとおりであるから,これを引用する。
[216](1) 原判決20頁14行目の「すべきである。」の次に以下のとおり加える。
「ただし,高齢者世帯の社会生活に必要な費用に配慮して,生活保護基準の体系の中で高齢者世帯の最低生活基準が維持されるよう引き続き検討する必要がある。」[217](2) 原判決20頁16行目末尾の次に以下のとおり加える。
「なお,「平成15年中間取りまとめ」は,このほかに,「生活扶助基準第1類費と第2類費の設定の在り方」として,「標準3人世帯を基準として具体的な世帯類型別にこれを展開してみると,いくつかの問題点がみられる。」と指摘した上で,まず,「第1類費の年齢別格差」として,「マーケット・バスケット方式時の栄養所要量を基準として設定されている現行の第1類費の年齢別格差について,直近の年齢別栄養所要量及び一般低所得世帯の年齢別消費支出額と比較として検証したところ,概ね妥当であるが,年齢区分の幅についてはもう少し大きく取るべきだとの意見もあるなど,その在り方については引き続き検討することが必要である。」と指摘し,ついで,「世帯人員別生活扶助基準」として,「生活扶助基準額は,個人消費部分(第1類費)と世帯消費部分(第2類費)によって構成されているが,この両者の割合は一般低所得世帯の消費実態と比べると第1類費が相対的に大きい。また,このように相対的に大きな第1類費が年齢別に組み合わされるために,多人数世帯ほど基準額が割高になることが指摘されている。」などと指摘し,さらに,「単身世帯の生活扶助基準」として,「単身世帯の生活扶助基準における第1類費及び第2類費の構成割合については,現在の3人世帯を基軸とする基準設定では,必ずしも一般低所得世帯の消費実態を反映したものとはなっていない。」,「したがって,一般に単身世帯数が増加している中で,とりわけ被保護者世帯の約7割が単身世帯であること,単身世帯における第1類費と第2類費については一般世帯の消費実態からみて,これらを区分する実質的な意味が乏しいことも踏まえ,単身世帯については,一般低所得世帯との均衡を踏まえて別途の生活扶助基準を設定することについて検討することが望ましい。」と指摘していた(乙1)。」[218](3) 原判決21頁1行目の「加えており,」の次に以下のとおり加える。
「生活保護において保障すべき最低生活の水準は,一般国民の生活水準との関連においてとらえられるべき相対的なものであり,具体的には,年間収入階級第I-10分位の世帯の消費水準に着目することが適当であると指摘し,このような考え方に基づき,」[219](4) 原判決21頁19行目末尾の次に改行して以下のとおり加える。
「オ 政府の財政面からの生活保護の見直しの動き[220](1) 憲法25条1項は,「すべて国民は,健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」と定め,これを受けて,法3条は,「この法律により保障される最低限度の生活は,健康で文化的な生活水準を維持することができるものでなければならない。」と,法8条は,「保護は,厚生労働大臣の定める基準により測定した要保護者の需要を基とし,そのうち,その者の金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度において行うものとする。」「前項の基準は,要保護者の年齢別,性別,世帯構成別,所在地域別その他保護の種類に応じて必要な事情を考慮した最低限度の生活の需要を満たすに十分であって,且つ,これをこえないものでなければならない。」と定めている。そして,法8条に基づき厚生労働大臣が定める保護基準が,憲法25条1項,法3条にいう「健康で文化的な最低限度の生活」を維持するに足りるものでなければならないことは明らかである。
(a)財政審の平成15年6月9日の建議は,「歳出見直しの基本的考え方」として,「持続可能な財政構造の確立のためには,諸制度の根幹に立ち返り,義務的な経費,裁量的な経費を問わず,聖域なく歳出内容を徹底して見直すことが不可欠である。」とし,「社会保障」の項目では,「社会保障関係費は年々増加し,一般歳出の約4割を占めるに至っており,その抑制を図ることは,我が国財政上,最大の構造問題である。このため,平成16年度の具体的な予算編成に当たっては,現行の制度,給付水準,単価などを前提とした社会保障関係の自然増を放置することは許されず,概算要求段階から制度改革による公的給付の抑制により削減を図ることが必要である。」とし,「生活保護」の項では,「生活扶助基準・加算の引き下げ・廃止,各種扶助の在り方の見直し,扶助の実施についての定期的な見直し・期限の設定など制度・運営の両面にわたり多角的かつ抜本的な検討が必要である。特に,原則70歳以上の高齢者に上乗せされる老齢加算(1万7930円 1級地―1)は,福祉年金創設との関係から昭和35年に創設されたが,年金制度改革の議論と一体的に考えると,70歳未満受給者との公平性,高齢者の消費は加齢に伴い減少する傾向にあること等からみて,廃止に向けた検討が必要であると考えられる。」としていた(甲6)。
また,(b)政府が平成15年6月27日に閣議決定した「経済財政運営と構造改革に関する基本方針」(いわゆる骨太の方針2003)は,「第2部 構造改革への具体的な取組」の中で,「生活保護においても,物価・賃金動向,社会経済情勢の変化,年金制度改革などとの関係を踏まえ,老齢加算等の扶助基準など制度・運営の両面にわたる見直しが必要である。」とした上,「第3部 平成16年度経済財政運営と予算のあり方」において,「社会保障については,一般歳出の約4割を占め,年々増加する社会保障関係費の伸びの抑制が財政上の最大の問題である。このため,予算編成過程において,社会保障関係の自然増を放置することなく,『第2部 5 社会保障制度改革』を踏まえ,年金をはじめ医療・介護・その他の分野の制度改革等や,給付・コストの見直しにより,その抑制を図る。」とした(甲7)。
さらに,(c)財務省主計局は,上記(b)の「骨太方針2003」が閣議決定されたのと同日に「予算執行調査資料」をまとめたが,その中には,「老齢加算,母子加算については,『老齢』『母子』というだけで一律に計上されており,必要性が乏しい。また,一般世帯との均衡がとれていないため廃止すべきである。(関東財務局)」との意見もあった(甲65)。
そして,(d)政府は,平成15年8月1日,平成16年度予算の概算要求に当たっての基本的な方針について」(平成16年度概算要求基準)を閣議了解し,同年度における医療・年金・介護等の社会保障関係費(いわゆる義務的経費)の自然増分が9100億円と試算されていたところ,これを2200億円削減して6900億円にまで抑制することとした(甲39,67)。
一方,(e)厚生労働省は,上記(d)の概算要求基準(閣議了解)を踏まえて,平成15年8月28日,「平成16年度厚生労働省予算概算要求の主要事項」を作成し,同省の当年度予算の概算要求を提出したが,その中で上記2200億円の削減目標に関しては,「義務的経費については,概算要求基準額(6871億円)の範囲内に納めるための方策について予算編成過程において引き続き検討することとしている。」とした(甲70)。
さらに,(f)財政審は,平成15年11月26日,「平成16年度予算の編成等に関する建議」において,生活保護制度について,「制度・運営の両面にわたる抜本的な改革が必要である。」とし,「被保護者の属性に着目して一律に適用される加算については,一般世帯との均衡がとれていないことから,必要性について検証した上で,見直すことが必要である。特に,原則70歳以上の高齢者に上乗せされる老齢加算(1万7930円 1級地―1)は福祉年金創設との関係から昭和35年に創設されたが,70歳未満受給者との公平性,加齢に伴い減少する高齢者の消費実態等からみて,廃止することが適当である。」とした(甲71)。
(g)政府は,財政審の上記(f)の建議を受けて,平成15年12月5日,「平成16年度予算編成の基本方針」を閣議決定し,その中で「生活保護については,物価・賃金動向,社会経済情勢の変化,年金制度改革等との関係を踏まえ,老齢加算等の扶助基準など制度・運営の両面にわたる見直しを行う。」とし,これに基づき,老齢加算の減額を前提とした平成16年度予算の財務省案・政府案が作成された(甲8及び弁論の全趣旨)。
(h)厚生労働大臣は,平成16年度から保護基準を改定し,平成18年度までに老齢加算を段階的に廃止した。」
[221] そこで,厚生労働大臣による保護基準の設定が憲法25条1項,法3条に違反しないかどうかを判断する場合の判断基準が問題となるが,健康で文化的な最低限度の生活なるものは,抽象的な相対的概念であり,その具体的内容は法令で示されていないから,文化の発達,国民経済の進展に伴つて向上するのはもとより,多数の不確定的要素を総合考量してはじめて決定できるものというべきである。そして,厚生労働大臣による保護基準が憲法25条1項,法3条に違反しないかどうかについては,前掲最高裁昭和42年5月24日大法廷判決(朝日訴訟最高裁判決)が傍論としてではあるが判断基準を示しており,同判決がされて既に40年以上が経過し,この間,我が国においては経済・社会情勢の変動があったものの,憲法25条1項にいう「健康で文化的な最低限度の生活」の文言の抽象性と各時代の多数の不確定要素を総合考量して決定できるというその性格に照らせば,同判決の示す解釈は今日においても妥当するものであって,これに従うのが相当であると考えられる。すなわち,何が健康で文化的な最低限度の生活であるかの認定判断(保護基準の設定)は,一応,厚生労働大臣の合目的的な裁量にゆだねられており,その判断は,現実の生活条件を無視して著しく低い基準を設定する等憲法及び生活保護法の趣旨・目的に反し,法律によって与えられた裁量権の範囲を超え又は裁量権を濫用した場合に限り違法として司法審査の対象となるが,それ以外は当不当の問題として政府の政治責任が問われることはあっても,直ちに違法の問題を生ずることはなく,また,厚生労働大臣が,保護基準の設定に当たって,設定当時の国民所得ないしその反映である国の財政状態,国民の一般的生活水準,都市と農村における生活の格差,低所得者の生活程度とこの層に属する者の全人口において占める割合,生活保護を受けている者の生活が保護を受けていない多数貧困者の生活より優遇されているのは不当であるとの一部の国民感情及び予算配分の事情のような生活外要素を考慮することは,保護基準の設定について厚生労働大臣の有する裁量の範囲に属することであって,その判断については,法の趣旨・目的を逸脱しないかぎり,当不当の問題を生ずるにすぎないのであって,違法の問題を生ずることはないと解するのが相当である。
[222] 法56条は,「被保護者は,正当な理由がなければ,既に決定された保護を,不利益に変更されることがない。」と規定しているところ,この規定は,被保護者と保護の実施機関との間における基本的な関係を規定したものであって,一旦,保護の実施機関が被保護者に対し一定の保護を決定した場合には,法の定めるところの事情の変更の場合に該当し,かつ,保護の実施機関が法の定めるところによって変更の手続をとらない限り,その決定された内容のとおり保護の実施を受ける権利が既得権となり,被保護者は,これに基づいてその実施を請求する権利を有することを定めたものである。したがって,同条にいう「既に決定された保護」とは,法24条1項の規定により保護の決定通知書に記載されたすべての事項,すなわち,保護の種類,程度及び方法のすべてをいうものであり,同条にいう「正当な理由」とは,決定された保護の変更が法や保護基準で定める変更や停止又は廃止の要件(法25条2項、26条,28条4項及び62条3項参照)に該当することをいうと解すべきである。
[223] これに対し,法は,厚生労働大臣が保護基準を設定する場合の基準として,法3条,8条2項を規定しており,保護基準の改定について,上記のとおり既に保護の決定を受けた個々の被保護者の権利を擁護する趣旨で設けられた法56条の適用はないと解するのが相当であり,前示のとおり,保護基準の改定は,現実の生活条件を無視して著しく低い基準を設定する等憲法及び生活保護法の趣旨・目的に反し,法律によって与えられた裁量権の範囲を超え又は裁量権を濫用した場合に限り違法として審査の対象となるに止まるものである。
[224] もっとも,前記のとおり,厚生労働大臣の裁量権の行使は,合目的的なものであることを要するから,厚生労働大臣が,一旦,法3条,8条の定める基準に従い適法に設定された保護基準について,これを何らの理由もなく被保護者に不利益に改定することは,憲法及び生活保護法の趣旨・目的に反し,法律によって与えられた裁量権の範囲を超え又は裁量権を濫用したものとして許されないというべきである。本件に即して言えば,老齢加算は,昭和35年度から平成18年度まで45年以上にわたって継続されてきたものであり,この間,保護基準において,70歳以上の高齢の被保護者については,基準生活費と老齢加算を併せて,「最低限度の生活の需要を満たすに十分なものであって,且つ,これをこえないもの」(法8条2項)とされてきたのであるから,厚生労働大臣が保護基準を改定し,老齢加算を廃止するについては,相応の合理的理由があることを要すると解するのが相当である。加えて,上記改定後の保護基準が現実の生活条件を無視して著しく低い基準を設定する等憲法及び生活保護法の趣旨・目的に反し,法律によって与えられた裁量権の範囲を逸脱又は濫用したとみられる場合には,本件各決定が違法との評価を免れないことは,前記説示から明らかである。
[225] 控訴人らは,上記と異なる見解に立ち,厚生労働大臣による保護基準の不利益変更にも法56条が適用されることを前提として,同条の「正当な理由」の判断についての厚生労働大臣の裁量権と,法8条2項に基づく厚生労働大臣の保護基準の設定に関する裁量権は,質的に異なるものであり,保護基準の不利益変更については,厚生労働大臣の裁量権に対する一般的な制約とは質的に異なる厳格な基準によって判断されなければならないと主張するが,採用することはできない。
[226]3 そこで,上記2の基本的枠組みに従って,まず,厚生労働大臣による保護基準の改定(老齢加算の廃止)について相応の合理的理由があるかについて検討する。
[227]ア 被控訴人らは,専門委員会の検討資料,すなわち,(a)60歳以上69歳以下の者と70歳以上の単身無職者のそれぞれ全体(平均),第I-5分位及び第I-10分位の「生活扶助相当消費支出額」の比較(比較(a)),(b)70歳以上の単身無職者のうち第I-5分位の者の「生活扶助相当消費支出額」と老齢加算を除いた生活扶助基準額の平均との比較(比較(b))とを踏まえて,70歳以上の高齢者に老齢加算に相当するだけの特別需要がないと認められること,老齢加算制度の合理性を基礎付けていた事情が現在ではほぼ失われていると解されることを老齢加算の廃止の主要な根拠として主張している。
[228]イ 比較(a)は,国民一般及び低所得者層の各単身高齢者の消費水準について,60歳以上69歳以下の者と70歳以上の者とを比較したものであり,比較(b)は70歳以上の単身無職者について,低所得者層の消費水準と老齢加算を除いた生活扶助基準額とを比較したものであって,これらは,老齢加算の対象となっていた70歳以上の単身無職者の消費水準が,これと隣接する年齢区分の者のそれと比べて低いこと(比較(a)),老齢加算を付加しない保護のみによっても,70歳以上の単身無職者の低所得者層の一般的な消費支出を充足するに足りるものであること(比較(b))を示したものということができる。そして,このことは,70歳以上の高齢者の被保護者において,老齢加算を付加しなければならない特別の需要がないことを基礎付けるものと評価することができる。前記認定のとおり(原判決19頁から20頁にかけてのc),被保護高齢単身世帯の消費実態についてみると,老齢加算が,加算が想定する需要を充たすために消費されず,少なからず貯蓄等に回っていることが判明しているが,この事実も特別の需要の喪失を裏付けるものということができる。
[229] なお,前記のとおり(原判決20頁(イ)),専門委員会も,「平成15年中間取りまとめ」において,
「単身無職の一般低所得高齢者世帯の消費支出額について,70歳以上の者と60歳以上69歳以下の者との間で比較すると,前者の消費支出額の方が少ないことが認められる。したがって,消費支出額全体でみた場合には,70歳以上の高齢者について,現行の老齢加算に相当するだけの特別需要があるとは認められないため,加算そのものについては廃止の方向で見直すべきである。」とし,比較(a)を根拠の一つとして,老齢加算を廃止の方向で見直すべきとしていたものである。
[230]ウ 前記認定によれば,厚生労働大臣が老齢加算廃止の措置をとったことについては,上記イのような老齢加算に相当する特別需要の喪失を基礎付ける事情の存在のほか,以下のとおり,社会経済情勢の変化,我が国の財政状態などの背景事情があったものと認められるのであって,その措置に相応の合理的な理由があるか否かの判断に当たっては,それらの背景事情を考慮に入れるべきものと考えられる。
(ア) 社会経済情勢の変化
[231]a 生活扶助基準の算定方式としては,前記認定のとおり(原判決15頁ア),(a)昭和23年以降は,最低生活を営むのに必要な飲食物費,衣類費,家具什器費,光熱水費等の個々の需要を一つ一つ積み上げて計算するマーケット・バスケット方式が,(b)昭和36年以降は,標準的栄養所要量を満たす飲食物費を計算し,これと同等程度の飲食物費を支出している世帯のエンゲル係数で割り戻すことによって算定するエンゲル方式が,(c)昭和40年以降は,高度経済成長期の国民の生活水準の向上に合わせて保護基準の引上げを図るため,政府経済見通しにおける民間最終消費支出の伸び率(見通し)に格差縮小分を加味して改定する格差縮小方式が,(d)昭和59年以降は,政府経済見通しにおける民間最終消費支出の伸び率に準拠して改定する水準均衡方式が,それぞれ採用されて現在に至っている(乙11の2,乙13)。そして,昭和55年中間的取りまとめ(乙6)にあっては,生活扶助基準について,昭和40年度当時と比較して相当の改善が図られたものの,一般世帯との格差縮小がなお不十分であるとして,上記(c)の格差縮小方式の考え方が妥当性を有するとされていたところ,昭和58年意見具申(乙7)にあっては,現在の生活扶助基準は,一般国民の消費実態との均衡上ほぼ妥当な水準に達している旨評価されており,上記(c)から(d)への算定方式の変更も,こうした評価を受けて行われた。
[232] その結果,前記認定のとおり(原判決16頁イ),一般勤労者世帯の消費支出を100としたときの被保護勤労者世帯の消費支出の割合(格差)は,昭和45年度には54.6パーセント(小数点2桁以下四捨五入。以下同じ。)であったものが,格差縮小方式が採用されていた昭和58年度には66.4パーセントとなり,その後,水準均衡方式が採用されてからはおおむね7割弱で推移しており,平成13年度には71.9パーセント,平成14年度には73.0パーセントと,70パーセントを超える水準に達していたことが認められる。なお,前記認定のとおり(原判決21頁),専門委員会の「平成15年中間取りまとめ」では,生活扶助基準の水準についても検討を加えており,平成8年から平成12年までの間の第I-10分位の勤労者3人世帯の消費水準に着目して,これと生活扶助基準額とを比較した上で,(a)第I-10分位の消費水準よりも生活扶助基準額の方が高いこと,(b)食費,教養娯楽等の減少が顕著な第I・第II-50分位の消費水準よりも生活扶助基準額の方が高いこと,(c)第IIIないし第V-50分位の消費水準と勤労控除額(収入認定において就労に伴う必要経費を控除するものであり,控除額は就労収入によって異なる。平成8年から平成12年までの間の平均控除額は2万0599円である。)を除いた生活扶助基準額とは均衡が図られているが,勤労控除額を含めると生活扶助基準額の方が高いことなどの評価が加えられているところである。
[233] 昭和40年代以降,我が国がめざましい経済成長を遂げ,経済力を著しく増大させたことは公知の事実であり,このような経済成長,経済力の増大に伴い保護水準も逐次改善されていき,昭和60年以降は一般勤労者世帯の消費支出を100としたときの被保護勤労者世帯の消費支出の割合(格差)が70パーセントを超える水準を維持してきたものということができる。
[234]b しかし,平成3,4年ころ,いわゆるバブル経済が終焉を迎え,我が国の経済成長が足踏み状態となった後,比較的長期に経済が低迷する状態が続き,それに伴い我が国の財政状態も悪化していったことは公知の事実である。
[235] そして,前記認定のとおり(原判決16頁から17頁にかけてのウ),各種の調査結果から以下のことが見てとれる。
[236](a) 厚生労働省「毎月勤労統計調査」により,一般勤労者世帯の賃金(事業所規模30人以上,調査産業計の現金給与総額)をみると,平成10年から前年比マイナスに転じ,平成16年まで減少が続いていることが分かる。
[237](b) また,総務省統計局「家計調査」により全国勤労者世帯の家計収支の推移をみると,実収入,可処分所得及び消費支出のいずれも平成10年からマイナスに転じ,平成15年まで減少が続いていることが分かる。
[238](c) さらに,厚生労働省「国民生活基礎調査」により,昭和60年以降の全世帯の一世帯当たり平均所得金額の推移をみると,平成6年の664万2000円をピークに減少傾向となり,平成15年には579万7000円となったこと,平成16年には一旦上昇したが,平成17年には563万8000円と再び減少に転じた(乙18,19)こと,平成6年と平成17年の水準を比較すると,その差は100万4000円,15.1パーセントの減少となっていること,これを所得階級別にみると,第I-5分位では,平成7年に163万1000円であったものが,平成16年には123万9000円となっており,その差は39万2000円,24.0パーセントの減少となっていること,第II-5分位では,平成7年に364万円であったものが,平成16年には291万7000円となっており,その差は72万3000円,19.9パーセントの減少となっていることが分かる。
[239] 以上の調査結果から,我が国の経済の低迷に伴い,一般国民の所得及び消費支出の水準が相当程度低下していることは明らかである。
[240]c なお,前記認定のとおり(原判決18頁から19頁にかけてのb),専門委員会では,昭和58年の意見具申で生活扶助基準が妥当な水準とされた以降の社会情勢の変化についても着目しており,第6回の委員会においては,当該期間中の生活扶助基準改定率,消費者物価指数,賃金及び基礎年金改定率の推移を比較した資料が提出され,検討が行われており,これによれば,昭和59年度を100とした場合,平成14年度においては,生活扶助基準は135.5パーセントであるのに対し,消費者物価指数(暦年)は116.5パーセント,賃金は131.2パーセントであり,生活扶助基準の改定率が上回っていること,特に平成7年度を100とした場合には,生活扶助基準が104.3パーセントであるのに対し,消費者物価指数は99.9パーセント,賃金は98.7パーセントであり,物価,賃金ともにマイナスとなっていることが判明した。また,専門委員会は,昭和55年と平成12年の消費支出を比較しているが,これによると,一般勤労者世帯(全国,平均),一般勤労者世帯(全国,第I-10分位),被保護勤労者世帯(全国,平均)ともに消費支出に占める食料費の割合(エンゲル係数)が低下していることなどが判明した。
[241](イ) 政府・財務当局及び厚生労働省が平成16年度予算案の作成過程において,社会保障費削減の一環として,老齢加算の廃止を検討し,平成16年度からこれを段階的に廃止した経過は,前記1(4)に記載のとおりであり,政府は,平成16年度の社会保障費の自然増分が9100億円に上ぼると試算されていたことから,これから老齢加算の減額分を含めて2200億円を削減して自然増分を6900億円にまで抑制するとの判断の下に予算編成を行ったものであり,保護基準における老齢加算の廃止の措置も,その判断を受けて行われた経緯があると認められる。老齢加算を減額の対象としたことの政治的な当否は別として,予算編成における上記のような政府の方針を不合理ということはできない。
[242]エ 厚生労働大臣による保護基準の改定(老齢加算の廃止)は,上記イのとおり,今日においては老齢加算に相当するだけの特別の需要が失われていることを基礎付ける事情があることに加え,上記認定の社会経済情勢の変化や我が国の財政状態を背景として行われたものであり,そうであれば,同改定は厚生労働大臣にとって我が国の経済力や財政状態がしからしむるやむを得ない選択であったというほかなく,同改定には相応の合理的な理由があるとするのが相当というべきである。
[243] 控訴人らは,これに対し,特別需要の存否及びその検証手法等を巡り,詳細な批判を展開している。すなわち,控訴人らは,高齢者における特別需要の存在が老齢加算が設けられた根拠とされており,老齢加算制度が昭和35年に老齢福祉年金制度の発足を契機として創設され,昭和51年に至って老齢福祉年金制度と切り離され,高齢者の特別需要を満たす基準として純化され,生活保護の特別基準として本来の性格を確立し,これまで生活保護の見直し等が実施された機会にも,高齢者の特別需要の存在とこれを理由とした老齢加算の必要性・妥当性が繰り返し確認されてきているところ,老齢加算廃止の措置に至る検証過程においては,消費支出の総額しか問題とされておらず,消費構造の比較検討,特に,昭和58年意見具申において行われた高齢者とそれ以外の年齢層との支出科目ごとの比較が行われていないため,従前の老齢加算制度の合理性を基礎付けていた事情,特別需要の存否についての検証は全く行われていないに等しいとして,厚生労働大臣らの検証手法等に関して様々な主張をする。
[244] これらの主張に対する当裁判所の判断は,次のとおり補正し,後記4(3)ないし(5)において,控訴人らの当審における主張に対する判断を付加するほか,原判決の「事実及び理由」欄の「第3 争点に対する判断」の3(2)のアないしカ,ク及びケ(原判決30頁22行目から42頁12行目まで,44頁14行目から47頁23行目まで)に記載のとおりであるから,これを引用する。
[245]ア 原判決37頁24行目末尾の次に改行して以下のとおり加える。
「(ウ) 控訴人らは,「60歳~69歳の者」には,老齢加算制度本来の趣旨からすれば,支給対象となるべき,あるいは,支給対象として検討されるべき者が含まれているところ,「60歳~69歳の者」と「70歳以上の者」との比較は「同じ特性を持った方同士」の比較ということができるのであり,このような両者を比較して高齢者の特別需要の有無・程度と老齢加算の要否を検討する手法には合理性がないとも主張している。[246]イ 原判決46頁10行目冒頭から14行目末尾までを以下のとおり改め,47頁20行目の「減額・廃止を行ったとしても,」の次に「直ちに,」を加える。
しかし,保護基準においては,「60歳~69歳の者」については,老齢加算が加算されないものとして生活扶助基準が定められており,本件においてその生活扶助基準の定めが現実の生活条件を無視して著しく低い基準を設定する等憲法及び法の趣旨・目的に反する事情はうかがわれないから,その生活扶助基準は当該年齢層の者の特有の生活の需要を含めて最低限度の生活の需要を満たしているものと判断するのが相当である。そうであれば,高齢単身世帯の消費支出について,単身無職の70歳以上の者と60~69歳の者との間でその多寡を比較し,70歳以上の者について,老齢加算に相当する特別需要が存在しないと判断することを不合理ということはできないのであって,控訴人らの上記主張は採用することができない。」
「以上のとおり,控訴人らの各主張のいずれの点を取上げて検討してみても,本件各決定の前提となる保護基準の改定が相応の合理性を欠き,厚生労働大臣の裁量権の範囲を逸脱し,又は濫用したとまで認めることはできないといわざるを得ない。」ア 比較(a)及び(b)は老齢加算廃止の根拠とはなり得ないとの主張について
[247](ア) 控訴人らは,「平成15年中間取りまとめ」は,これまで老齢加算によって対応してきた高齢者の特別需要の存在を当然の前提とするものであり,「平成15年中間取りまとめ」が老齢加算に関して指摘しているのは,「消費支出全体でみた場合には」,特別需要があるとは認められないということにすぎず,また,「現行の老齢加算に相当するだけの」特別需要があるとは認められないとしているにすぎず,「平成15年中間取りまとめ」は,老齢加算そのものについて廃止の方向で見直すべきとしているにすぎないのであり,これまで加算の形で支給されてきたものをすべて削減すべきであるとか,削減してもよいとはしていないから,比較(a)は,老齢加算廃止の根拠となるものではないと主張する。
[248] しかし,比較(a)は,仮に高齢者に特別需要があるとしても,他の年齢層に比較して,支出項目が少ない需要もあり,その支出額の減少分が特別需要に対する支出額を上回ることから,老齢加算の対象となっていた70歳以上の単身無職者の消費水準が,これと隣接する年齢区分である60歳以上69歳以下のそれと比べて低いことを示すものであって,老齢加算廃止の根拠となりうることは明らかである。
[249](イ) また,控訴人らは,(a)比較(b)は,専門委員会の資料とはされたが,「平成15年中間取りまとめ」では全く言及されていないこと,(b)専門委員会は,単身70歳以上の生活扶助基準額(老齢加算を除いたもの)が第I-5分位の「生活扶助相当消費支出額」を上回っているからといって,これが老齢加算廃止の根拠となり得ると考えてはいなかったものであることを主張する。
[250] しかし,前記1(3)に認定のとおり,「平成15年中間取りまとめ」は,
「生活保護において保障すべき最低生活の水準は,一般国民の生活水準との関連においてとらえられるべき相対的なものであり,具体的には,年間収入階級第I-10分位の世帯の消費水準に着目することが適当である。」としているのであって,これは,専門委員会が,比較(b)を「平成15年中間取りまとめ」の前提としていたことを示すものと解されるから,上記(a)の主張は採用することはできない。 [251] 上記(b)の主張については,後記(4)のとおり,専門委員会はあくまでも厚生労働大臣の諮問機関と位置付けられるものであり,保護基準の改定に当たり,厚生労働大臣は,その考え方に拘束されるものではないから,採用の限りでない。
イ 比較(a)及び比較(b)が不合理・不当なものであるとの主張について
(ア) 比較(a)が,70歳以上の単身無職者の消費水準が,これと隣接する年齢区分の者(60歳以上69歳以下)のそれと比べて低いと評価することの問題点に関する主張について
[252]a 控訴人らは,比較(a)の統計上の誤謬として,(a)消費支出額が支出の原資となる所得(収入・貯蓄)の金額に制約されることを看過していること,(b)ある年齢層の消費支出額(所得額)の分布と他の年齢層のこれが等しいか,同視し得ない限り,年齢層間の消費支出額が異なる原因が,年齢の相違にあるということができないことを看過していること,(c)平成11年という単年度の調査によって得られた全世帯平均,第I-5分位及び第I-10分位において,60歳から69歳までの者より70歳以上の者の「生活扶助相当消費支出額」が低い状況となっているとの一統計事実(比較(a))を不変のものとしていることを挙げる。
[253]b しかし,原判決の説示するとおり(原判決33頁(イ)),消費支出が需要のすべてを反映するものではないとしても,需要との間に一定の相関関係があることは十分に推認できるところであり,また,そもそも消費支出,更には収入によって条件付けられず,その制約を受けない客観的な需要なるものが存在するものといえるか,それをどのような方法で測定・検証するのかについて疑問が残り,また,その測定が可能であるとしても,「健康で文化的な最低限度の生活水準」に沿うべきものである保護基準を定めるに当たり,これを参照して,直接反映させなければならないとする根拠も見当たらないから,上記(a)の主張は採用することができない。
[254]c 上記(b)の主張は,母集団の所得分布が支出額に影響することを問題とするものであり,結局,支出額が所得の金額に制約されることをいうものと解されるから,上記(a)と同様,採用することはできない。
[255]d 上記(c)の主張については,比較(a)を不変のものとすることができないのは,そのとおりと考えられ,また,平成11年と平成16年の全国消費実態調査(別紙1)によれば,65歳以上69歳以下と70歳以上74歳以下を比較すると,男性については,「無職世帯」と「全世帯」のいずれにおいても,70歳以上74歳以下が65歳以上69歳以下よりも消費支出額が増加していること,女性については,おおむね消費支出額が減少する傾向にあるものの,例外的に平成16年の「全世帯」の女性((12)表)のように増加していることもあること,男女平均では,消費支出がおおむね増加しているが,平成16年の「無職世帯」の男女平均((2)表)のように例外的に減少することもあることが認められる。
[256] しかし,上記各調査(別紙1)によれば,75歳以上の消費支出額は,男性・女性とも,それ以下の年齢層のいずれよりも少ない傾向が認められるのであり(例外は,平成16年の「全世帯」の男性((10)表)のみである。),また,女性については消費支出が加齢とともに顕著に減少していく傾向が明らかに認められるのであり,これらの事実によれば,70歳以上の高齢者について,消費支出額がそれ以下の年齢層よりも一般的に増加するという特別需要の存在を裏付ける一般的な傾向は認めることができない。
[257] また,前記のように,男性高齢者においては,70歳以上74歳以下の消費支出が65歳以上69歳以下よりも増加する傾向を示しているが,男女の平均寿命の差等から,70歳以上の高齢者のなかで,70歳以上74歳以下の男性が占める割合は比較的小さいはずであるから,これをもって,70歳以上の高齢者について,消費支出額がそれ以下の年齢層よりも一般的に増加するという特別需要が存在するとみるのは相当でない。
[258] なお,控訴人らの主張するように,世代ごとに消費支出額の傾向が異なることは当然予想されるが,少なくとも平成16年予算編成時(平成15年時点)においては,戦中・戦後の厳しい経済状態を直接体験している70歳以上の高齢者(平成15年を基準とすると、おおむね昭和8年以前に出生した者がこれに相当する。)の消費支出額が,このような体験が比較的少ないそれ以下の年齢層を下回る傾向があることが予想されるところであり,上記各調査は,これを裏付けるものと解することができる。
[259]e したがって,控訴人らの上記(a)ないし(c)の主張は採用することはできない。
(イ) 比較(a)が統計上の消費支出額と異なる「生活扶助相当消費支出額」を設定して消費水準を比較していることについて
[260] 控訴人らは,比較(a)が比較のものさしとした「生活扶助相当消費支出額」は,厚生労働省の特別集計により算出された不合理・不当なものであるから,比較(a)は,老齢加算の廃止を正当化する根拠にはなり得ない旨るる主張するが,その主張は,要するに,(a)特別集計では,「生活扶助相当消費支出額」を算定する際,一定の消費細目の金額を除外しているが,どのような支出をどのような根拠で除外したのか,被控訴人らは主張・立証していない,(b)全国消費実態調査の集計世帯と,特別集計の基礎とした集計世帯が範囲(数)が異なっているとすれば,集計結果の数値は当然異なるから,特別集計の信頼性はないというものと解される。
[261] しかし,上記(a)の主張については,原判決の説示するとおり(原判決38頁から39頁にかけての(イ)),専門委員会の検討資料の作成過程に特段不合理なところはなく,信憑性に疑義を生じさせるような事情も見当たらず,「生活扶助相当消費支出額」を算定するに当たり控除した支出の項目についても,生活扶助の対象となるべき消費支出額を算定する方法としては合理的なものであり,恣意が介在するなど不適切な処理をうかがわせる事情もないから,採用することはできない。
[262] これに対し,控訴人らは,特別集計では「生活扶助相当消費支出額」を算定する際,どのような支出がどのような根拠で除外されたのか,被控訴人らが主張・立証すべきであると主張するが,「生活扶助相当消費支出額」を算定する際,どのような支出をどのような根拠で除外するかは,厚生労働大臣の合目的的裁量に委ねられた事項というべきであり(控訴人らの主張する「家事使用人給料」や「自動車関係費」を控除すべきか否かは,まさにこれに当たるというべきであろう。),その点に裁量権の範囲の逸脱又は濫用があるとする事情は認められない。
[263] また,上記(b)の主張についても,統計学上,母集団の属性を判断するに相当な数のサンプル(標本)が確保されていれば,統計の信頼性は確保されるから,全国消費実態調査の集計世帯と,特別集計の集計世帯の範囲(数)が仮に異なっているとしても,特別集計の信頼性が直ちに否定されるものではない。なお,控訴人らの主張するとおり,「食料」については,加重平均の消費支出額よりも「生活扶助相当消費支出額」の方が少ない結果が生じているが,証拠(乙22の1,乙23の3)及び弁論の全趣旨によれば,全国消費実態調査の調査においては,一部の食品以外の項目については,調査対象となった世帯が,支出項目ごとに支出金額を明示して調査票に記載するのではなく,支出額を手書きで逐一家計簿に記載していく方式でされているため,全国消費実態調査では総務省が,特別集計では厚生労働省がそれぞれ家計簿に記載された支出を項目ごとに分類集計する必要があることが認められるのであって,「食料」の概念が両者で食い違っている可能性もある(例えば,分類方法によっては,旅行中の食事代は,「食料」にも,「その他の消費支出」等にも計上されうる。)から,上記の結果は,特別集計の信頼性を直ちに否定するものとは解されない。
(ウ) 比較(b)が「生活扶助相当消費支出額」を低所得世帯の消費水準と比較したことの不合理性について
[264] 控訴人らは,比較(b)を根拠とした老齢加算の廃止は,第I-5分位,第I-10分位という低所得層の生活実態の検証を行わないまま,その生活に合わせて,保護基準を引き下げるというものであり,劣等処遇にほかならず,憲法25条及び生活保護法の趣旨・目的に反すると主張する。
[265] しかし,厚生労働大臣が保護基準を設定するに当たり,「低所得者の生活程度とこの層に属する者の全人口における占める割合,生活保護を受けている者の生活が保護を受けていない多数貧困者の生活より優遇されているのは不当であるとの一部の国民感情」といった生活外要素を考慮することができることは,既に説示したとおりであり,生活保護制度が無拠出制の公的扶助である以上,生活保護において保障すべき最低生活の水準を設定するについて,第I-5分位ないし第I-10分位といった低所得世帯の消費水準に着目することが不当ということはできない(前記1(3)に認定のとおり,「平成15年中間取りまとめ」も,「生活保護において保障すべき最低生活の水準は,一般国民の生活水準との関連においてとらえられるべき相対的なものであり,具体的には,年間収入階級第I-10分位の世帯の消費水準に着目することが適当である。」としているところである。)。
[266](エ) 以上のとおり,比較(a)及び比較(b)が不合理・不当なものであるということはできず,控訴人らの主張は採用することができない。
ウ 基準生活費と(老齢)加算では,その減額・廃止についての違法性の判断基準が異なるとする原判決の「二重の基準論」が誤りであるとの主張について
[267] 控訴人らは,原判決が
「生活扶助基準のうち,本体ともいうべき基準生活費の減額が問題とされるのであれば,法の要求する生活水準を満たすかどうかという観点から,被保護者の生活実態に係る調査を行うことが極めて強く要請されるとも考えられるが,本件においては,基準生活費に付加して給付される老齢加算が問題とされているのであって,以上にみてきたような,その導入の経緯及びその後の推移に照らすならば,比較(a)及び(b)を主要な根拠として老齢加算の減額・廃止を行ったとしても,現実の生活条件を無視して著しく低い基準を設定するなど,憲法及び生活保護法の趣旨・目的に反するとまではいえず,厚生労働大臣において,その裁量権の範囲の逸脱又は濫用になるということはできない。」と説示していること(原判決47頁)を「二重の基準論」として批判しているものと解される。
[268] しかし,原判決の上記説示は,基準生活費と加算では,その減額・廃止についての違法性の判断基準が一般的に異なるとしたものではなく,「老齢加算の導入の経緯及びその後の推移」に照らして,老齢加算の減額・廃止については,「法の要求する生活水準を満たすかどうかという観点から」の「被保護者の生活実態に係る調査」までは要請されないとしたものと解されるのであり,控訴人らの上記主張は原判決を正解しないものである。
[269] 当裁判所において,更に検討するに,原判決の認定(原判決11頁から15頁にかけての(1)及び30頁から33頁にかけての(2)ア)及び証拠(乙6,7)によれば,以下の事実が認められる。
[270](a) 老齢加算は,昭和34年度に70歳以上の国民年金被保険者に対する未拠出制の老齢福祉年金が設けられたことに伴い,生活保護の給付を受けている者に対しても同様の年金給付を行った上でこれを収入として認定するなどの調整を行うことに代え,昭和35年度から,老齢福祉年金と同額(月額1000円)を生活保護の加算として給付するものとして設けられたものであり,その後,老齢福祉年金については,制度創設後,年を追って増額が実施されていき,老齢加算も,当初,老齢福祉年金と同額に設定されていたため,これに合わせて逐次増額が図られていったものであること(すなわち,老齢加算は,高齢者に特別需要があることを直接の理由として創設されたものではなく,その金額も,この特別需要を満たすよう算定された訳ではなかったこと),
[271](b) 昭和50年10月以降老齢福祉年金が7500円から1万2000円に増額されることを踏まえ,老齢福祉年金と老齢加算額を同額とすることの妥当性が検討され,老齢加算について生活保護制度本来の立場に立って適切かつ合理的な算定を行い,その際,第1類費との間にある程度の均衡が保たれていることが望ましいことが提言され,厚生省は,昭和51年から,老齢加算を老齢福祉年金と同額とする方式をやめ,65歳以上の第1類基準額の男女平均の2分の1の額とするものとし,昭和51年1月以降は8000円,同年4月以降は8500円への増額にとどめたこと,
[272](c) 「昭和55年中間取りまとめ」では,老齢加算について,老齢者はそのそしゃく力が弱いため,他の年齢層に比し消化吸収がよく良質な食品を必要とするとともに,肉体的条件から暖房費,被服費,保険衛生費等に特別な配慮を必要とし,また,近隣,知人,親戚等への訪問や墓参等の社会的費用が他の年齢層に比し余分に必要となるという特別な需要が存在することに対応して設定されたものであり,その必要性は客観的に認められるとした上,現行の加算額は金額的にも特別需要にほぼ見合うものと考えられる旨の評価がされているが,その検証は,当時利用可能な資料を用いて特別需要額を推計したというにとどまるものであり,他の年齢層の消費実態との比較が行われた形跡はないこと,
[273](d) 昭和58年意見具申においても,「昭和55年中間取りまとめ」と同様の特別需要が認められるとした上,その額はおおむね現行の加算額で充たされていると結論付けていること,もっとも,同意見具申では,その検証のため,昭和54年全国消費実態調査結果を基に,51歳以上59歳以下の単身女性の消費支出と70歳以上74歳以下及び75歳以上の各単身女性の消費支出を比較しているのであるが,各支出科目の比較に当たっては,高齢者の各支出科目の実際の額ではなく,50歳代の消費支出(総額)を高齢者の各支出科目の構成比に基づいて案分して割り振って得られた額を,高齢者の支出科目の金額とみなし,これを50歳代の各支出科目の実際の額と比較しているものであり,また,上記比較は,高齢者の方が高くなっている各支出科目のみについて差額を合計しており,高齢者の方が低くなっている各支出科目については積算の対象から除外されていて通算されておらず,さらに,上記高齢者の実際の各消費支出(総額)は,50歳代のそれをいずれも下回っていることから,上記比較においては,いずれも高齢者の各支出科目の実際の額を上回った数値を用いていたことになるものであったこと,同様に,一般夫婦世帯(年間収入140万円未満)と老夫婦世帯(世帯主70歳,年間収入180万円未満)及び一般夫婦世帯(年間収入180万円未満)と老夫婦世帯(世帯主71歳以上75歳以下,年間収入180万円未満)の各消費支出についての各比較も行われているが,ここでも,上記単身女性の場合と同様の方法で各支出科目の比較を行ったものであり,一般夫婦世帯(年間収入140万円未満)と老夫婦世帯(世帯主70歳,年間収入180万円未満)との間でも,後者の実際の消費支出(総額)は前者のそれを下回っている一方で,一般夫婦世帯(年間収入180万円未満)と老夫婦世帯(世帯主71歳以上75歳以下,年間収入180万円未満)との間においては,後者の実際の消費支出(総額)は前者のそれを上回るものとなっており,両者の比較においては,逆に老夫婦世帯の各支出科目の実際の額を下回った数値を用いる結果となっているものであったことが認められる。
[274] 以上のとおり,老齢加算は,長年にわたって継続されてきたものではあるが,老齢福祉年金の創設に伴う政治的・技術的な理由から創設されたものであることは明らかであり,また,その後における老齢加算の増額の仕方や「昭和55年中間取りまとめ」及び昭和58年意見具申時の特別需要の存在についての検証方法をみても,一般国民の生活水準との比較において相対的に定められるべき最低生活保障水準の一部を構成する老齢加算について,これを基礎付ける特別需要の存在が科学的・客観的に裏付けられていたわけではなく,どちらかといえば,我が国における経済成長を背景に,老齢加算の制度を是としつつこれを維持することを前提とし,明確な裏付けのないまま老人福祉の維持・向上という見地からその存続が図られてきたにすぎないと評価するのが相当であって,その廃止の当否をめぐって,原判決のように基準生活費と異なる扱いをするのが不当であるとはいえない。
[275] これに対し,控訴人らは,(a)老齢加算は,生活保護本来の立場から創設されたものであり,老齢加算創設の必要性については,老齢福祉年金制度が創設される以前から議論されていたこと,(b)老齢加算の創設を担当していた厚生省の担当者も,養老施設関係者から聞き取りを行い,加齢に伴う心身の状況の変化に対応するために必要な需要(高齢者の特別需要)にはどのようなものがあるかについて調査し,その聞き取りを基に特別需要を積算したところ,その金額は,老齢福祉年金と同じ月額1000円となったこと,(c)昭和58年意見具申は,加算を除いた基準生活費のみによって特別需要も含めた高齢者の生活の需要を賄うことができる程度にまで基準生活費が改善されたという認識とはほど遠いものであり,したがって,老齢加算を除いた基準生活費のみによって特別需要も含めた高齢者の生活の需要を賄うことができるかについての検証を行うまでもないというのが当時の判断であったということができるのであり,かつ,その判断に不合理な点はないこと,(d)政府は,平成元年当時においても,70歳以上の第1類費相当の消費支出額は69歳以下のそれと比較して低いとの認識を持っていたのであり,70歳以上の「生活扶助相当消費支出額」が60歳代のそれと比較して低いこと(比較(a))を根拠とする老齢加算の廃止は,政府のこれまでの対応と矛盾すると主張する。
[276] しかし,上記(a)の主張については,証拠(甲54ないし57,当審証人冨家貴子)によれば,老齢加算創設の必要性について,老齢福祉年金制度が創設される以前から厚生省の関係者において議論されていたことは認められるが,老齢加算が高齢者に特別需要があることを直接の理由として創設されたものではないことは前記のとおりであり,また,上記の議論は,いわばア・プリオリ(先験的)に高齢者には,特別需要があるから,これに対応する加算等をすべきであるなどとするものであり,70歳以上の高齢者に他の年齢層と比較して逆に支出額が少ない需要項目があるかや,仮にこのような項目があるとした場合,特別需要に対する支出額が,支出額が少ない需要項目に対する支出額を上回るか,その金額はどの程度かについて科学的・客観的な検討がされた形跡はないから,上記判断を左右するものではない。
[277] また,上記(b)の主張についても,老齢加算導入時に老齢福祉年金の金額(月額1000円)と,厚生省の担当者が高齢者の特別需要を積算した金額が,ほぼ同額となったというのは,いかにも不自然であり,この積算が厳密にされたかは疑問であるから,前記判断を左右するものではない。なお,冨家貴子の陳述書(甲54・4頁)によれば,厚生省の担当者であった板山賢治も,老齢加算の金額について,
「実際に積み上げたが,一方で老齢福祉年金は月1000円に決まった。すると,これは政策的な配慮で,1000円に合わせなければならない。細かい数字は覚えていないが,実際に積み上げて1000円近くになった。老齢福祉年金が1000円だったから加算も1000円にした。しかし,それなりに理屈は合っていた。金額も一応合理的なものだった。」と述べ,上記積算が多分に政策的な配慮に基づいてされたことを示唆している。
[278] 上記(c)の主張については,原判決が説示するとおり(原判決31頁から33頁にかけての(イ)),昭和58年意見具申時の検証手法は,高齢者の実際の需要を多めに見込んだ可能性を否定できないのみならず,高齢者の需要を測定する方法としては,必ずしも首尾一貫したものとはいい難いのであって,もともと老齢加算の制度維持,高齢者に対する当時の給付金額の正当化を目的として採用された疑いを払拭できないものといわざるを得ないから,採用することはできない。
[279] 上記(d)の主張についても,仮に,政府が平成元年当時においても,70歳以上の第1類費相当の消費支出額は69歳以下のそれと比較して低いとの認識を持っており,70歳以上の「生活扶助相当消費支出額」が60歳代のそれと比較して低いこと(比較(a))を根拠とする老齢加算の廃止が政府のこれまでの対応と矛盾するとしても,これは,政府のこれまでの対応に問題があることを意味するにとどまり,問題がある以上,これを是正するのは,当然の措置というべきであるから,採用することはできない。
[280] 控訴人らは,(a)「平成15年中間取りまとめ」は,あくまで「中間」の報告書にすぎないこと,(b)「平成15年中間取りまとめ」は,単身高齢者の生活扶助基準を別途設定する必要性や,保護基準体系の中で高齢者世帯の最低生活基準が維持されるよう引き続き検討する必要性,さらに激変緩和措置について指摘しているのに,厚生労働大臣は,これらの点について検討することなく,わずか3年間で老齢加算を廃止しているから,この廃止は,「平成15年中間取りまとめ」の内容に反すること,(c)厚生労働大臣が専門委員会の審議結果である「平成15年中間取りまとめ」と矛盾,齟齬する措置を採る場合には,相応の合理的な根拠・理由が必要であるというべきであるところ,厚生労働大臣がそのような根拠・理由なくした老齢加算の廃止は,その裁量権の範囲を逸脱又は濫用したものであると主張する。
[281] しかし,原判決が説示するとおり(原判決45頁から46頁にかけてのク((イ)及び(ウ)),その趣旨・解釈はともかくとしても,老齢加算を廃止の方向で検討すべきことについては専門委員会において合意が得られたということができ,また,「平成15年中間取りまとめ」において,代替措置の検討・実施が老齢加算廃止の明示的な条件とされているとまではいえず,代替措置を実施することなく老齢加算を廃止した措置が,「平成15年中間取りまとめ」に反することにはならないというべきであるから,控訴人らの上記(a),(b)の主張はいずれも採用することができない。
[282] すなわち,前記1(2)に認定のとおり,「平成15年中間取りまとめ」は,
「したがって,一般に単身世帯数が増加している中で,とりわけ被保護者世帯の約7割が単身世帯であること,単身世帯における第1類費と第2類費については一般世帯の消費実態からみて,これらを区分する実質的な意味が乏しいことも踏まえ,単身世帯については,一般低所得世帯との均衡を踏まえて別途の生活扶助基準を設定することについて検討することが望ましい。」として,単身世帯について,一般低所得世帯との均衡を踏まえて別途の生活扶助基準を設定することについて検討する必要性を指摘したが,上記のとおり「望ましい」と表現するにとどまっており,これが老齢加算廃止の明示的な条件とされていたとまではいえないものである。また,3年間での段階的な老齢加算の廃止が激変緩和に当たらないということもできない。
[283] さらに,厚生労働省設置法(平成11年法律第97号)7条1項1号は,社会保障審議会のつかさどる事務として,厚生労働大臣の諮問に応じて社会保障に関する重要事項の調査審議等を規定し,社会保障審議会令(平成12年政令第282号)6条1項は,審議会及び分科会は,その定めるところにより,部会を置くことができると規定しているところ,弁論の全趣旨によれば,これらの規定に基づき,社会保障審議会に福祉部会が置かれ,同部会によって,専門委員会が設置されたことが認められる。このような専門委員会の組織上の位置付けに照らして,同委員会が厚生労働大臣の諮問機関であることは明らかであるから,同委員会による「平成15年中間取りまとめ」は,厚生労働大臣の保護基準の設定・改定について法的拘束力を有するものではなく,控訴人らの上記(c)の主張も採用することができない。
[284] 控訴人らは,老齢加算の廃止は,平成15年当時の政府(小泉純一郎内閣)による予算削減目標の達成という,もっぱら財政的な動機によるものであり,このような国の財政上の必要を絶対的に優先させ,対象国民の生活や人権への配慮を欠くか,劣後に置くような生活保護の行政措置が憲法25条の趣意に適合せず,法3条や8条等に違反することは明らかであると主張する。
[285] しかし,前記認定のとおり(原判決17頁),生活保護制度については,「社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する法律」(平成12年法律第111号)の法案審議時の付帯決議(衆議院及び参議院),平成15年の社会保障審議会意見及び財政審建議において,社会福祉基礎構造改革を踏まえた今後の社会福祉の状況変化や規制緩和,地方分権の進展,介護保険の施行状況等を踏まえつつ,生活保護制度についても見直しの必要が指摘されるなど,生活保護法が制定されてから50年以上が経過し,この間の社会経済情勢の変化に照らし,制度の在り方や保護基準の水準の妥当性について検討してこれを見直す必要があることが課題となっていたところ、厚生労働省では,平成15年8月,これらの課題について議論するため,厚生労働大臣の諮問に応じて社会保障に関する重要事項の調査審議を行う社会保障審議会の福祉部会内に,専門委員会を設置した経緯が認められる。そして,専門委員会は,上記の課題を審議するため開催されたものであり,老齢加算廃止の正当化の根拠を作出することを目的としていたものでないことは明らかである。また,専門委員会の設置以前に,財政審の建議や閣議決定事項において,老齢加算の廃止に向けた検討や見直しを行うべきことが明示されていたとしても,社会保障審議会や専門委員会は,独立した立場で調査審議を行うべきことが予定されているし,先行する他機関の決定にしても,検討・見直しを促す内容にとどまり,その結論を先取りして専門委員会の審議判断を拘束するような性質のものであるとは認め難いのであって,専門委員会はその独立した地位に基づき適性な審議を行って,老齢加算の見直しを含む生活保護制度の改正について結論を出すに至ったものと推認することができる。
[286] したがって,老齢加算廃止がもっぱら財政的な動機により行われたとする控訴人らの主張は,その前提を欠くものである。
[287] また,保護基準の設定に当たり,国の財政状態をも考慮しつつ適切な水準について政策判断を行うことは,厚生労働大臣の合目的的な裁量に委ねられていると解すべきことは既に説示したとおりであり,本件の老齢加算の廃止に当たっても,厚生労働大臣は,老齢加算に相当する特別需要の消滅に加え,社会経済情勢の変化やわが国の財政状態を踏まえてこれを判断しているのであって,そのような判断が憲法25条の趣旨に反し,法3条,8条に違反するなどということは到底できない。
[288]4 次に,老齢加算廃止後の保護基準が現実の生活条件を無視して著しく低い基準を設定する等憲法25条及び生活保護法の趣旨・目的に反するか否かについて検討する。
[289] 金澤教授を中心とするグループは,平成17年,京都において,高齢者を含め,若年単身者,中年夫婦ないし未婚子等,多くの世帯類型について,「持ち物財調査」,「生活実態調査」,「価格調査」を行い,マーケット・バスケット方式による最低生計費を算定したところ,単身高齢者の税込月額最低生計費の算定額は,1箇月当たり18万5061円であり,そこから,税・社会保険料,NHK受信料の各項目を控除し,生活扶助相当支出額を算出すると,予備費を含めて11万8112円(住居費別),予備費を含めない場合でも10万3112円(住居費別)となること,各種統計の消費者物価指数,消費支出の比較からみて,東京都の数値がこれ(京都の数値)を下回るものとは考えられないところ,東京都各区等(1級地―1)における老齢加算相当額を加えた生活扶助基準ですら9万3700円(平成19年度。なお,平成15年度は9万3850円)と上記最低生計費を下回る水準となっており,老齢加算相当額を除いた生活扶助基準はこれらを更に下回る水準となっていること(甲18,22,33)から,控訴人らは,老齢加算を廃止した後の生活扶助基準は「健康で文化的な最低限度の生活」の水準を満たすものではないと主張している。
[290] しかし,金澤教授の調査の内容を分析してみると,65歳以上の高齢単身世帯及び夫婦のみの世帯の各所得分布は,所得が上記調査で算定された最低生計費未満のものの割合が単身世帯で87.1パーセント,夫婦のみの世帯で52.1パーセントに達する(甲18)というのであって,端的にいうと,夫婦のみの世帯で5割余り,単身世帯については,実に9割近くの者が上記最低生計費を下回る所得しか得られていないとの結果となっている。これらの数字に照らせば,上記最低生計費は,現実を踏まえた「健康で文化的な最低限度の生活水準」とは見合うものではなく,意識的に在るべき数値として算定されたものと推認せざるを得ず,これを「健康で文化的な最低限度の生活水準」を示す基準とするのは困難である。
[291] そもそも,金澤教授が算定した「最低生計費」は,マーケット・バスケット方式を用いて理論生計費を算定したものであるところ,この算定方式は,いかなる項目についてどれだけの金額を必要な支出とみるかについて多様な考え方が成り立ち,品目及び数量の選定において恣意的とならざるを得ない側面があり,特に飲食物費を除く国民の消費が多様性化している今日において,その恣意性が強く現れるものである。したがって,この方式により算出された理論生計費を直ちに「健康で文化的な最低限度の生活」の水準を示すものと認めるのは困難である。厚生労働大臣が,保護基準の算定方式について,マーケット・バスケット方式から消費支出に準拠する方式へと変遷してきたのもそこに理由があると考えられる。
[292] 既に説示したとおり,健康で文化的な最低限度の生活なるものは,抽象的な相対的概念であり,その具体的内容は,文化の発達,国民経済の進展に伴つて向上するのはもとより,多数の不確定的要素を総合考量してはじめて決定できるものであり,何が健康で文化的な最低限度の生活であるかの認定判断は,厚生労働大臣の合目的的な裁量に委されているものと考えなければならないところ,以上の点を考慮すれば,金澤教授が算定した「最低生計費」を下回るからといって,直ちに老齢加算廃止後の生活扶助基準額が法3条の「健康で文化的な最低限度の生活」の水準を満たさないということはできず,控訴人らの上記主張は採用することができない。
[293](2) 控訴人らは,老齢加算廃止後の70歳以上の被保護者(控訴人ら)の生活が「健康で文化的な最低限度の生活」を下回っていると主張し,民医連調査報告(甲52)及び同追加報告(甲106)等を提出する。
[294] しかし,控訴人らの各個別事情からみた検討の結果は,原判決の「事実及び理由」欄の「第3 争点に対する判断」の3の(3)(原判決47頁24行目から55頁2行目まで)に記載のとおりであるから,これを引用する(ただし,原判決49頁5行目の「できるでけ」を「できるだけ」と改める。)が,原判決が詳細に説示するとおり,老齢加算廃止後の70歳以上の被保護者(控訴人ら)の生活が,「健康で文化的な最低限度の生活」の需要を満たしていないとまではいうことはできず,控訴人らの当審における主張・立証を踏まえても,この判断は左右されないというべきである。
[295] すなわち,控訴人らが当審で提出したC事件控訴人X3及びF事件控訴人X6の各陳述書(甲C1,2,甲F1,2)及びその当審における各本人尋問の結果並びに民医連調査報告及び同追加報告を検討しても,上記控訴人らを含む70歳以上の被保護者らが,老齢加算の廃止後,一層の節約を強いられ,日常生活で不自由を感じる場面が少なくないことは否定できないにせよ,その日常生活は,我が国における低所得者層の生活として社会的に是認できる範囲内にないとまでいうことはできず,「健康で文化的な最低限度の生活」を下回ると直ちに断定することはできないものである(なお,控訴人らが本件訴訟において取消しを求めている老齢加算の減額部分は,平成18年度からの3760円のみであり,控訴人らは,平成16年度の8260円の減額,平成17年度の5910円の減額については,いずれも不服申立てをしていなかったものである。)。
[296]5 さらに,老齢加算廃止に係る保護基準の改定が社会権規約に違反しているとの控訴人らの主張について検討する。
[297] 控訴人らは,老齢加算廃止に係る保護基準の改定は,社会権規約の解釈基準となる国連社会権規約委員会の定めた一般的意見第14・平成12年(2000年)に反するものであって,社会権規約の9条,11条1項前段及び15条1項の趣旨に反し,法8条に違反すると主張する。
[298] 確かに,社会権規約9条は,「この規約の締約国は,社会保険その他の社会保障についてのすべての者の権利を認める。」と規定し,同11条1項前段は,「この規約の締約国は,自己及びその家族のための相当な食糧,衣類及び住居を内容とする相当な生活水準についての並びに生活条件の不断の改善についてのすべての者の権利を認める。」と規定し,同15条1項は,「この規約の締約国は,すべての者の次の権利を認める。(a)文化的な生活に参加する権利,(b)科学の進歩及びその利用による利益を享受する権利,(c)自己の科学的,文学的又は芸術的作品より生ずる精神的及び物質的利益が保護されることを享受する権利」と規定している。しかし,社会権規約2条1項が,締約国に対し,立法措置その他のすべての適当な方法により同規約において認められる権利の完全な実現を漸進的に達成することを求めるとしていることに照らせば,これらは,締約国において,社会保障についての権利その他各条項所定の権利が,国の社会政策により保護されるに値するものであることを確認し,上記権利の実現に向けて積極的に社会保障政策を推進すべき政治的責任を負うことを宣明したものであって,個人に対し即時に具体的権利を付与すべきことを定めたものではないというべきである。
[299] このように社会権規約9条,11条1項前段及び15条1項は,いずれも,個人に対し即時に具体的権利を付与すべきことを定めたものではないのであって,老齢加算廃止に係る保護基準の改定がこれらの規定に違反するとの控訴人らの主張は,失当である。
[300] H事件控訴人Aが原判決後の平成21年12月7日に死亡したことは当裁判所に顕著であるところ,生活保護法の規定に基づく要保護者又は被保護者の保護受給権は,被保護者自身の最低限度の生活を維持するために当該個人に与えられた一身専属の権利であって,他にこれを譲渡し得ないし(法59条参照),相続の対象ともなり得ないというべきである。また,被保護者の生存中の扶助ですでに遅滞にあるものの給付を求める権利についても,医療扶助の場合はもちろんのこと,金銭給付を内容とするものであっても,法の予定する目的以外に流用することを許さないものであるから,当該被保護者の死亡によって当然消滅し,相続の対象となり得ないと解するのが相当である(朝日訴訟最高裁判決参照)。
[301] したがって,本件訴訟のうちH事件控訴人Aに関する部分は,平成21年12月7日,同控訴人の死亡により終了したものである。
[302] 以上の次第で,本件訴訟のうちH事件控訴人Aに関する部分については原判決を取消して訴訟の終了を宣言し,その余の控訴人らについては,原判決は相当であり,その各控訴は,いずれも理由がないから,これを棄却することとし,主文のとおり判決する。
裁判長裁判官 青柳馨 裁判官 小林敬子 裁判官 大野和明
(別紙1)
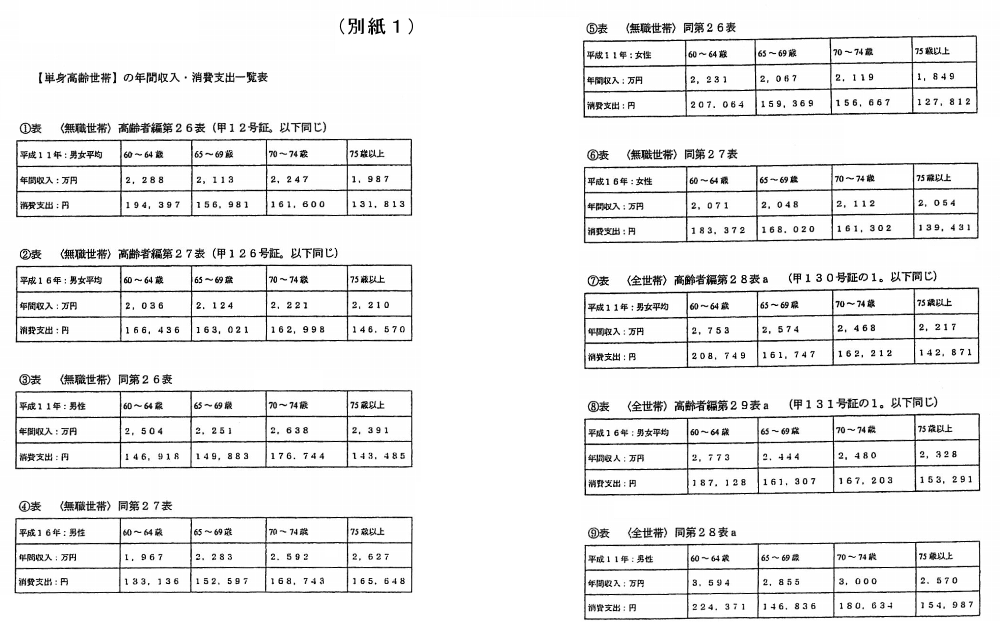
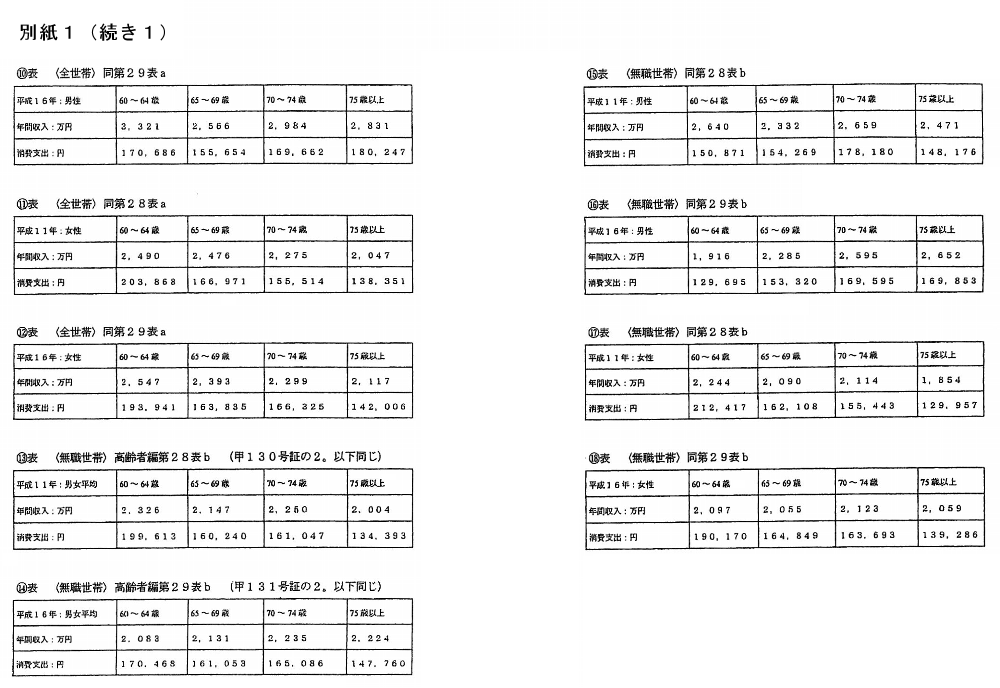
(別紙2)

(別紙3)